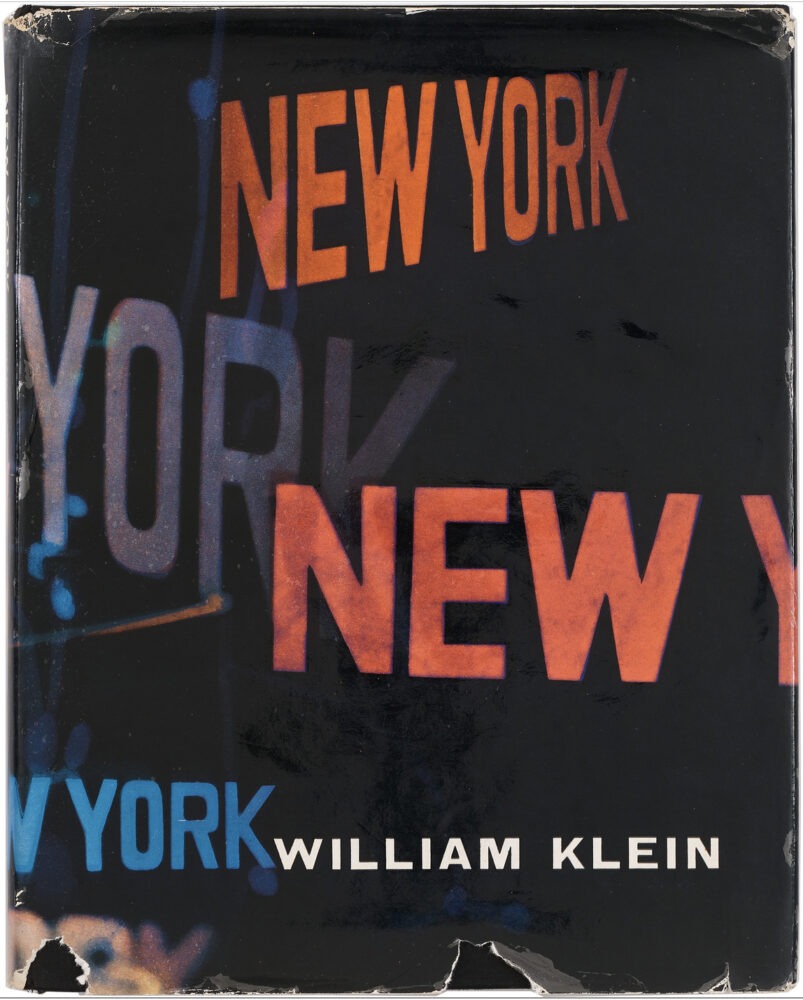現実逃避から写真家へ
ここまで見てきたように、ロシアやドイツをはじめとするヨーロッパの国々からアメリカに亡命してきたユダヤ系の写真家やアートディレクターたちは、ファッション・ジャーナリズムの首都であるニューヨークで中心的な地位をになった。1940年代以降になると、彼らに薫陶を受けた次の世代が台頭してくる。
とくに、『ヴォーグ』や『ハーパーズ・バザー』で活躍するスター級の写真家は、アドルフ・ド・メイヤー以来、ほとんどがヨーロッパ人だった。エドワード・スタイケンに限っては幼い段階でアメリカに渡ってはいるが、彼にしてもパリとアメリカを頻繁に行き来する特殊な立場だった。だが、第二次大戦後になると、アメリカで生まれ育ち、アメリカで教育を受けたいわば「純アメリカン・スターフォトグラファー」がニューヨークでファッション写真家として活躍していく。ことに、アーヴィング・ペンとリチャード・アヴェドンは現代までファッション写真界のレジェンドとして記憶される象徴的存在といっていい。
一般的にみれば、ペンとアヴェドンがファッション写真の歴史の象徴的存在たり得るのは、写真の出来栄えがすばらしく、名作とされる写真を多く残しているという事実で十分に語ることができるだろう。だが、じつはそれ以外にも理由はある。わたしたちが追っているアメリカへの人材移動の観点からみれば、実は2人はともにロシアからアメリカへ渡ってきたユダヤ人の息子だった。しかも、ともに親と似た出自をもつブロドヴィッチやリーバーマンに見出され写真家となっている。いわば最初の純アメリカン・スターフォトグラファーともいえる彼らは、アメリカ人として生まれ育ったものの、ロシアからのユダヤ移民2世という、ファッション・ジャーナリズム界における前世代の流れを踏襲するかたちで登場してきているのだ。
そうした世代は主に第二次大戦後に写真家として活動し始めるが、アーヴィング・ペンはやや早く、戦前からすでに名前を知られている。
ペンの父親、シャイム・ミハイルソンはユダヤ系ロシア人として生まれる。彼がアメリカに渡ってきたのは1908年のことだった。ロシアでは1881年から84年にかけてのユダヤ人に対する集団迫害行為が起こったのをきっかけに反ユダヤ感情が高まっており、1903年以降にはユダヤ人の国外脱出が増加していた。おそらく、ミハイルソンもそうしたうちのひとりだったのだろう。亡命と同時に彼はハリー・ウィリアム・ペンと改名し、時計職人兼精密彫刻家としてニュージャージーに居を構え、1913年にはジュエリーショップを開業している。ロシア革命とアメリカの第一次大戦参戦の年として記憶される1917年、息子のアーヴィングが生まれる。
一家は1920年にフィラデルフィアに引っ越すも、両親はアーヴィングがまだ幼い1925年頃に離婚する。アーヴィングは母とニューヨークで暮らすことになり、繊細な感性を次第にアートに向けるようになっていった。高校では美術やデザインを学び、34年にはフィラデルフィア工芸美術館学校に入学する。3年次からはブロドヴィッチのクラスに入り、デザインセンスに磨きをかけていく。興味深いことに、ここまでの段階でペンは絵こそ描いていたものの、積極的に写真を学んだり撮っていたという記録はない。実際、ペンはグラフィックデザイナーを志していたようで、1937年と38年にはクラスの成績優秀者として、夏のあいだ『ハーパーズ・バザー』でブロドヴィッチのアシスタントとしてインターンのようなことをしている。38年に二眼レフカメラのローライフレックスを買ったという記録はあるが、ブロドヴィッチのアシスタントを終えてからはフリーランスのグラフィックデザイナー兼アートディレクターとして活動していく。
ブロドヴィッチの仕事を手伝ったりと、一応は食べていくに事欠かなかったようではあるが、繊細な性格だったがゆえに、のちのちまでペンに起こる現実逃避癖がほどなく顔をのぞかせる。1941年、ブロドヴィッチから引き継いだ5番街の名門デパート、サックスの広告デザインの仕事を引き受けていたペンは、バイヤーや関係者からの矛盾をはらんだ指示に耐えかね、メキシコに逃避して絵を描くようになる。
本当はヨーロッパに行きたかったのだろうか? 写真史家のマリア・モリス・ハンブルグは2017年にペンの生誕100年を記念して開催された大回顧展〈アーヴィング・ペン センテニアル〉のカタログに寄せた巻頭エッセイを次のように書き始めている。
多くのアメリカ人の若者同様に文化やインスピレーション、海外での安価な生活を求めてパリへ渡航したかもしれないアーヴィング・ペンだったが、彼は時代を間違えて生まれた。1917年、彼の生まれた年、ドイツのUボートの攻撃がアメリカを第一次世界大戦に巻き込み、1941年、24歳の美術学校卒業生で新米アートディレクターだったペンが絵を描きたいと切望していた頃、パリはドイツに占領され、ヨーロッパはまたしても戦争の荒廃に襲われていた。その大陸が立ち入り禁止となったため、ペンはアメリカ南部を旅し、メキシコへ下ることを決めた。1
たしかに、ペンはパリに行ってみたかったのかもしれない。しかし、当時のアメリカの状況を考えれば、写真家アーヴィング・ペンを生み出す教育的環境はこれ以上ないほどに整っていた。さらに幸運だったのは、彼が帰国するのと前後してリーバーマンが『ヴォーグ』のアートディレクターに就任したことだった。
描けば描くほど自分には画家としての才能がないと悟ったペンは、筆を折って1942年11月にアメリカへ帰国した。それからほどなく、彼はもはや『ハーパーズ・バザー』がファッション帝国唯一の傑出した雑誌ではなくなったことを悟り、かつてサックスで顔を合わせたことのあるリーバーマンを訪ねた。心酔していた師のブロドヴィッチを再び頼らなかったのも不思議なことではあるが、それ以上に興味深いのは、彼もまた「ライバル誌に引き込まれる法則」の例にもれなかったことである。
リーバーマンはさっそくペンを雇い、表紙デザインを担当させる。当時、『ヴォーグ』の表紙はすでにイラストから写真に移行しており、ペンは立場上、場合によっては写真家たちに指示を出して表紙用の写真を撮らせなければならない。つまり、表紙担当のアートディレクターのようなものである。ある日、ペンはブロドヴィッチの仕事を手伝っていた際に目にした、『ハーパーズ・バザー』でデザイナー兼写真家をしていたレスリー・ギルの日用品を組み合わせた不思議な静物写真を思い出す。それをヒントにラフスケッチを描き、ホルストやビートン、ブルーメンフェルドら『ヴォーグ』のスター写真家に示してみせた。この構想をもとに写真を撮ってほしいという意味である。ところが、巨匠たちはみな一様にペンを冷たくあしらった。ここでペンの現実逃避癖が再び顔をのぞかせる。リーバーマンのもとに行って辞職を申し出たのだ。
しかし辞めるのを認められるどころか、ここがリーバーマンの辣腕の見せどころとなった。リーバーマンは、「それならばお前が自分で撮ればいいじゃないか」と言わんばかりにペンを諌め、大型カメラに精通した技術者を紹介し、スタジオをあてがったのである。かくして、1943年10月1日号の『ヴォーグ』で、ペンは写真家デビューをはたした。純アメリカン・スターフォトグラファーが頭角を見せた瞬間であった(図1)。

二人三脚の夢
第二次大戦が激化するにつれペンも軍務につかざるを得なくなり、1944年11月からまる1年、イタリアのナポリに渡る。帰国後、ペンとリーバーマンの本格的な二人三脚が始まった。ペンとブロドヴィッチが実務を通じてデザイン技術を教える徒弟的な師弟関係だったとすれば、ペンとリーバーマンはもっと精神的な側面の深い、お互いの中に自分を見出す関係を築いていく。『ヴォーグ』の編集者だったベッティーナ・バラードは「コンデ・ナストが成功と責任を彼〔リーバーマン〕に押し付ける以前に自身も抱いていた芸術家の夢を、ペンを通じて実現した」2と述べているし、当のペンも、「わたしは彼〔リーバーマン〕がなりたかった写真家だ」とのちに語っている3。
実際、ふたりのプロジェクトもまたリーバーマンの夢をペンが実行し、時にペンの至らない部分をリーバーマンがフォローしていくように進んでいく。例えば、リーバーマンは1946年からペンに芸術家たちのポートレートを撮るプロジェクトを任せる。1948年頃には2枚のパネルで作られた鋭角の空間にモデルを追い込んで撮るスタイルに固まっていった、ペンの初期の代表作となるシリーズである(図2)。

これは、1930年代からアメリカに多くの芸術家たちが亡命してきたことを背景に、リーバーマンが似た出自をもち、社交界で多くのそうした芸術家と知り合ったことをきっかけに思いついたプロジェクトである。当初ペンは現場での撮影を試みたがうまくいかず、窓のないスタジオで撮影するスタイルになった。このシリーズは1948年半ばまで『ヴォーグ』に断続的に掲載される。それと入れ替わるように、リーバーマンも40年代後半から自身で芸術家たちのアトリエを訪れ、その制作現場を撮影するプロジェクトを開始している。こちらは1960年に『アトリエの中の芸術家(The Artist in His Studio)』としてまとめられる。
他方、ペンはこの頃からファション写真も撮影しはじめるが、そもそもグラフィックデザイナーだったということもあり、その才能は静物写真の方により強く発揮される。おそらくペンはファッション業界で最も多くの静物写真を制作した写真家だろうし、のちにそれらの傑作集として『静物(Still Life)』が刊行されたことにも表れているだろう。モデルを起用した撮影でも、静物写真的な要素をもった彼の代表作は多い(図3)。

さらに、静物写真でもファッション写真でも共通していることだが、ペンの写真の画面構成はかなりシンプルである(図4)。ペン自身、煌びやかで豪華な生活にはまったく興味を示さなかったらしく、そうした信条が作品に反映されているともいえよう。だがそれと同時に、この頃ミニマリズム的な方向に傾倒していたリーバーマンの影響も受けているのではないだろうか。

マリア・モリス・ハンブルグは「ペンはブロドヴィッチのもとでの修業がなければペンではなかったが、リーバーマンがいなければ彼は花開くことはなかった」4と述べているが、実際、華やかで物語性に富んだ写真が誌面を彩っていた『ハーパーズ・バザー』ではペンの才能が花開くことはなかったのではないだろうか。他の写真家たちが編集スケジュールに合わせて社内のスタジオを共有していたなか、リーバーマンはペンにだけ専用のスタジオを用意したり、40年代後半からはオートクチュールのコレクション期間中にペンをパリに派遣して写真を撮らせるなど、周りの妬みも顧みずにペンを名実共にファッション写真界のスターに育てようと手を尽くした。
ただ、やはりペンの現実逃避癖はその後もしばしば見られる。のちに見るアヴェドンや同時代の他のファッション写真家が物語性に富んだセンセーショナルなファッション写真を次々に発表していくなか、ペンはファッション写真でもモデルの頭部と胴体のみを写す簡素な作風を好んでいたし、リーバーマンの『ヴォーグ』のアートディレクションも『ハーパーズ・バザー』に比べればシンプルなデザインだった。それは洗練されているともいえる一方、退屈という批判を生むことにもつながっていく。1952年の秋、ペンのファッション写真がページ上で燃え尽きていると批判され、ペンはほとんどファッション写真を撮らなくなる。以後は広告写真家としての活動の比重が増し、『ヴォーグ』には主に静物写真や民俗学的な興味に基づいたシリーズを制作する。彼のそれ以降の写真については、またあらためて見ていくことにしよう。