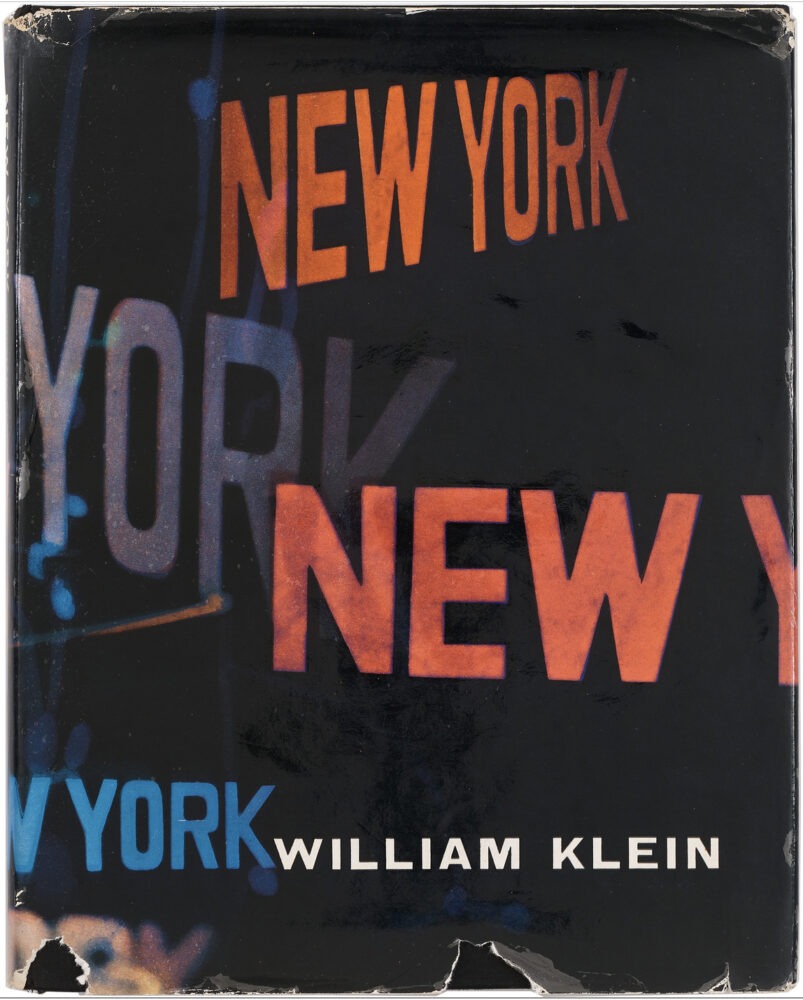運命の方からすり寄ってきた写真家
アーヴィング・ペンがグラフィック・デザイナーから写真家へと転身してファッション写真に関わっていったのに対し、もうひとりの純アメリカン・スターフォトグラファーとなるリチャード・アヴェドンは、ある意味でファッション写真の可能性を拓いていく、きわめて正統派のファッション写真家だったといっていい。
前回も触れたように、アヴェドンもまたユダヤ系アメリカ人で、ペンと歳は6つしか変わらない同世代の写真家である。だが、アヴェドン家はかなり早い段階でアメリカに移住しており、リチャードはユダヤ系アメリカ人3世だった。
父のジェイコブ・イズラエルに関する資料は多くは残っていないが、1974年にニューヨーク近代美術館が発表した経歴によれば、1889年にロシアのグロノド(現・ベラルーシ領)に生まれ、1890年にはアメリカへ渡っている。ただ、アメリカでの生活が厳しかったのか父親が出奔し、兄と共にユダヤ人ケア協会の養護施設に入っていた時期もあったという1。大学を出て教師をしていたが、1913年に兄のサムとブロードウェイにブラウス店を開店し、17年には事業を拡大して5番街39丁目に女性用の衣料品店「アヴェドンズ・フィフス・アベニュー」を開く。1922年に結婚、翌23年に長男としてリチャードが生まれた。
リチャードが生まれる前年にはアヴェドンズ・フィフス・アベニューが『ニューヨーク・タイムズ』や『ヴォーグ』に広告を出しているのが確認できる(図1)。

事業は好調のようにも見えたが1930年に倒産。老舗デパートがひしめく5番街で事業を維持していくのは簡単ではなかったようだ。とはいえ37年にはロードアイランド州のウーンソケットにふたたび女性用衣料品店を開店しているので、リチャードは比較的裕福に育ったと考えられる。12歳ころからカメラで遊び出し、幼い頃から『ヴォーグ』や『ハーパーズ・バザー』からお気に入りの写真を切り抜いてスクラップしたりするような少年時代だった。つまりまだ将来の夢を真剣に考えだす前から、彼の身近には商売、写真、ファッションという、後年に必要になる要素がすでに揃っていたということになる。
だが、本人はまだその要素がファッション写真家という職業に焦点を結ぶとは思っていない。高校を中退後、リチャード青年はコロンビア大学で哲学と詩を学びはじめる。詩人になることを目指していたが、コロンビア大学には正式に入学したわけではなく、市民講座のような拡張クラスに1年ほど在籍していたようだ。この時期、短期間近所の写真スタジオで使い走り兼アシスタントとして働いていた。ほとんどディレッタント的な生活を謳歌していたがまもなく第二次大戦が始まり、1942年から44年にかけて米国商船隊で軍務に就く。このとき、父親は息子に2眼レフカメラ、ローライフレックスを贈ったという。商船隊では身分証明書用の写真や商船隊員向けの雑誌『ザ・ヘルム』の写真を撮るカメラマンとして軍務に就いている。かたわら、余暇にも写真を撮るようになっていた。
除隊後、かつてのアヴェドンズ・フィフス・アベニューのすぐ近くにあった老舗デパートのボンウィット・テラーにギャラなしで広告写真を撮らせてもらえないか掛け合う。生粋のニューヨークの商売人の子であったアヴェドンにとっては、これくらいの意気込みがないと成功の手がかりは掴めないと思ったのだろう。
しかし不思議なのは、ここまでのリチャードの経歴を見ていると、彼がファッション写真家になるという運命の方から彼に歩み寄っているように映る。軍務に就く以前のアヴェドンはそのことにまったく気がついていないようだったのに、ここにきて、突然その運命の導きが目に見えたかのように突き進んでいくのだ。その気合いは並大抵のものではなく、モデルには当時ニューヨークで最も高額なギャラを取っていたビジュ・バーリントンをポケットマネーで雇っている。運良く、それらの写真をボンウィット・テラーのエレベーターに貼り出してもらうことに成功し、それらの写真や軍務時代に撮った写真などをポートフォリオにまとめると、それを携えてアレクセイ・ブロドヴィッチに持ち込む。これには少々伝説めいた逸話が付きまとう。『ザ・ニューヨーカー』誌にアヴェドンの最初の本格的な評伝を寄せたウィンスロップ・サージェントは、この時の面会を次のように描写している。
彼〔ブロドヴィッチ〕はアヴェドンのファッション写真をざっとめくって捨て、2人の兄弟の写真を選んだ。その一枚が彼の興味を引いたのである。ぼやけた感じが好きだったのである。こうしてアヴェドンは雇われた。ブロドヴィッチは当初、その若者の技術力に多少の懸念を抱いていたにもかかわらず、彼は雑誌の「ジュニア・バザー」と呼ばれるセクションに配属された。2
しかし、アヴェドンの目覚ましい活躍を考えれば、そのような伝説が生まれるのも納得できる。アヴェドンは『ハーパーズ・バザー』1944年11月号の、ティーエイジャー向けのコーナー「ジュニア・バザー」でデビューを飾った。商船隊を除隊してわずか数か月のことである。同時にニュースクール・フォー・ソーシャル・リサーチで41年から教鞭をとっていたブロドヴィッチに師事し、ファッション写真家としての地歩を固めていく。
生涯のコラボレーター、ディオールとの出会い
当時、『ヴォーグ』や『ハーパーズ・バザー』で仕事をする写真家にとって、年2回開催されるパリコレの時期にパリに渡ってオートクチュールを撮影するというのが最も重要な任務であり、スターフォトグラファーの証でもあった。だからこそ、リーバーマンはペンをそれにふさわしい格の写真家にしようと手を尽くしていたのだが、ペンがあまりその方向での成功を望まなかったのは前回見た通りである。
一方のアヴェドンはといえば、まさにファッション写真の申し子だった。1947年には早くもパリコレに派遣されている。このときの『ハーパーズ・バザー』用のオートクチュール撮影はすでにルイーズ・ダール=ヴォルフが受注していたこともあってあまり思うようには撮影できなかったが、ファッション史上のエポックとなるクリスチャン・ディオールのデビュー作であるニュールックの撮影をおこなっている(図2)。

生涯のコラボレーター、ディオール
アヴェドンとディオールの関係は晩年まで深く続いていくのだが、なんといってもそのエポックとなるのは、『ハーパーズ・バザー』アメリカ版の1955年9月号に独占掲載された〈ドヴィマと象〉だろう(図3)。

ドヴィマはこのころアメリカのファッション界で有名になっていたアイルランド系のアメリカ人で、本名をドロシー・ホーランという。ドロシーの「ド」、ヴィクトリーの「ヴィ」、敬愛していた母親(マザー)の「マ」を取ってドヴィマと名乗っていた。アヴェドンはドヴィマをサーカス団「シルク・ディヴェール」に連れて行き、彼女をバックヤードに繋がれている象と戯れさせた。この時ドヴィマが着用しているのは、当時19歳になりたてのイヴ・サン=ローランがディオールのメゾンで初めてデザインしたドレスだった。
象たちは脚を鎖で繋がれているとはいえ、残された数枚のカットを見るかぎり、片脚を上げたり鼻を振ったりと落ち着きなく動いている。そんな状況でドヴィマは象の動きに同調するかのように優雅なポーズを取る。アヴェドンの撮影もまた驚きで、8インチ×10インチの大型のフィルムを使うカメラで撮影している。そのなにがすごいのかといえば、この種のカメラはフィルムを一枚ずつホルダーに入れ、そのホルダーをカメラの背面に装填して撮影する。大型カメラは背面から被写体を覗いてピントや構図を確認する構造になっているので撮影時はフィルムホルダーに遮られ、一眼レフカメラのようにレンズ越しの状況を見ることができない。つまり、アヴェドンは構図やピントを合わせて以降、あとはシャッターチャンスが来るまで微塵もアングルの調整などをすることができず、カメラの横に立ってその瞬間を待つしかなかったのである。
先にも触れたように、アヴェドンとディオールは生涯にわたるコラボレーターとなった。クリスチャン・ディオールのデビューと、同メゾンでのサン=ローランのデビューなどエポックとなる衣裳を名作の写真として世に送り出し、アヴェドンの晩年にあたる2001年には、この年の秋冬コレクションでローンチされた男性服コレクション、ディオール・オムの広告を、緊張感のある黒白写真で世に送り出し、若きデザイナー、エディ・スリマンのスキニーでミニマルな世界観を見事に体現してみせた。
ディオール・オムの広告写真を待つまでもなく、アヴェドンにも、シンプルな背景を用いたミニマルな志向は見られる。だが、ファッション誌業界におけるアヴェドンは本質的にストーリーメーカーだった。〈ドヴィマと象〉はファッション・ジャーナリズムの黄金期である1950年代における、ファッション写真とアヴェドンの成功を示すひとつの到達点となった。
ところが、この写真は本家アメリカ版にしか掲載されなかった。のちに写真史上の傑作のひとつに数えられる本作は、初めから世界中に知られたイメージとはならなかったのである。とはいえ、1957年に公開されたオードリー・ヘップバーンとフレッド・アステアが主演を務めた映画『パリの恋人』では、これを彷彿とさせるシーンが出てくる。この映画はアヴェドン自身もビジュアル・コンサルタントを務め、アステア演じるファッション写真家のジョーはアヴェドンをモデルにしたといわれている。劇中ではジョーがドヴィマを撮影するシーンがあり、ここでドヴィマはあの象と戯れる写真を彷彿とさせるポーズをとっているのだ。このころ、アヴェドンはすでにファッションという枠を超えて広く知られる著名な写真家になっていた。それは、アヴェドン自身がこのように巨大なストーリーのキャストともなっていたからであるが、写真家としての彼を純粋に見つめた場合、1950年代においてもっとも物議を醸したファッション写真家だからでもあった。
- https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/5109/releases/MOMA_1974_0040_35.pdf?utm_source=chatgpt.com (2025年8月19日閲覧) ↩︎
- Winthrop Sargeant, “A Woman Entering a Taxi in the Rain,” The New Yorker, October 31, 1958 (https://www.newyorker.com/magazine/1958/11/08/a-woman-entering-a-taxi-in-the-rain). 2025年8月19日閲覧。なお、この伝説的な話しはその後もしばしば引用され、2009年にニューヨークの国際写真センターで開催された回顧展〈Avedon Fashion〉に際して刊行された書籍においても、キュレーターのキャロル・スクワイアーズが引用している。 ↩︎