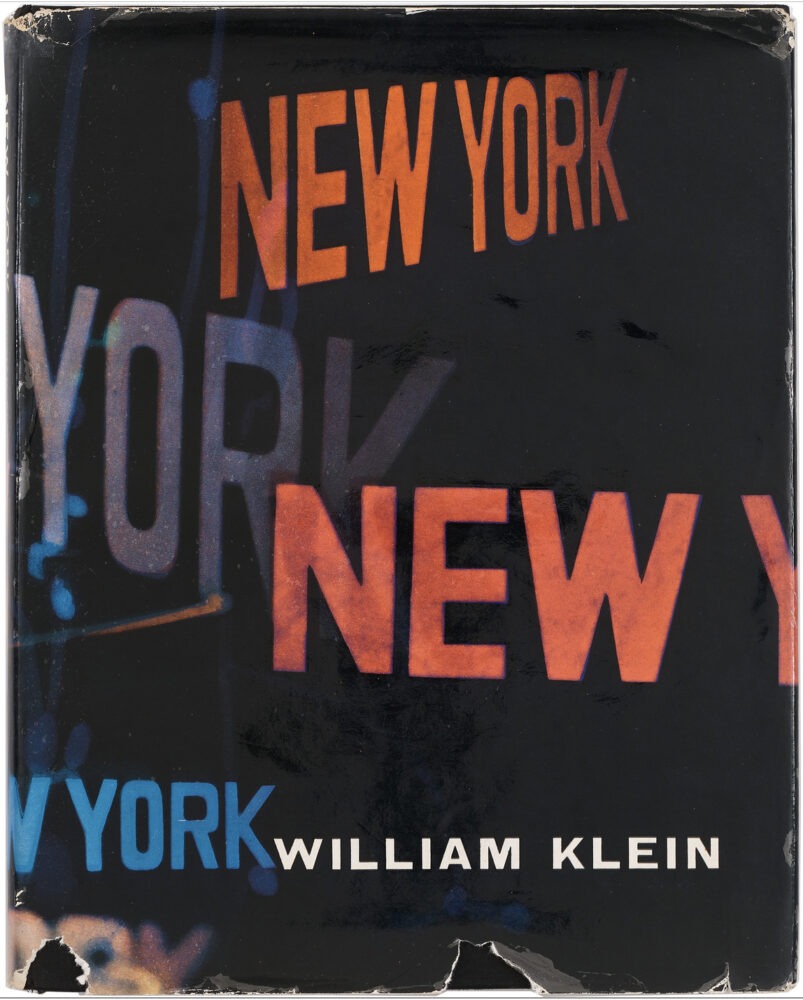『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』とフランス美術界の重鎮の青年期
フランス革命でファッションどころではなくなっていたフランスも、1793年から94年にかけてのジャコバン派による恐怖政治の時期を経て総裁政府時代(1795〜1799年)になると、ふたたびモードが花開くこととなる。このころには、おしゃれな人々、なかでもインフルエンサー級の女性をメルヴェイユーズ、男性をアンクロワイヤーブルと称するようになっていく。
そんな時代にあって白眉のファッション・プレートを掲載したモード新聞として挙げられるのが『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』である。1797年4月にパリで創刊、5日おきに発行されていた新聞で、パリのみならず地方在住の女性を対象にしたモード紙のさきがけとしても興味深い。『ギャルリー・デ・モード・エ・コスチューム・フランセ』がヴェルサイユやパリの貴族や大商人、あるいは海外をターゲットにしていたのに対し、フランス革命でパリと地方との格差が縮小した総裁政府時代にあっては、地方の裕福な女性たちが潜在的な読者層として注目されるようになっていた。
同誌で重要な役割を果たしたのが、創刊から編集に関わり、1799年にセレックが抜けたあとには編集長となったピエール・ド・ラ・メザンジェールである1。メザンジェールは、もともとロワール地方のラ・フレーシュという街のカトリックのコレージュで文学を教えていたが、フランス革命によりコレージュが閉鎖されたことで失職し、文筆家に転じる。そののち、『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』の発行者となるジャン=バティスト・セレックが元教員仲間だったという縁から同紙に携わるようになった。
『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』は「淑女と流行の新聞」とでも訳せるが、毎号、メルヴェイユーズやアンクロワイヤーブルを描いた1、2枚のファッション・プレートを掲載するメザンジェールの編集方針は大ヒットし、同時代のファッション・プレートと比較しても、その質の高さは歴然である。実際、それは19世紀にはなかば伝説になっていたようだ。『ペール・ゴリオ』などで知られる新聞小説の申し子バルザックは、『パリの新聞社のモノグラフ』で次のように記す。
ラ・メザンジェール氏は生前、『ジュルナル・デ・モード』の社主兼編集長をつとめた人物だが、彼こそはモードのための記録文書をつくりだすという天才的なアイディアを実践した最初の人にほかならない。すなわち、彼は、モードの変化を記録し、それを出版することにより、多くの職業をジャーナリズム帝国の版図の中に組み入れたのである。彼の選集は、稀覯本のひとつで、当時も非常な高値を呼んでいた。2
それは、あたかもメザンジェールがはじめてモード紙を作り上げた人物だといっているようにさえ聞こえる。前回の内容を踏まえればその主張自体は誤りだが、パリのガリエラ宮モード美術館の元学芸員であるフランソワーズ・テタール=ヴィトゥの指摘によれば、メザンジェールは大衆によく知られた画家に挿絵を担当させるほうが定期刊行物の売り上げが伸び、パリの潜在的な読者層をひきつけることができると考えていたという3。こうした戦略が、後世のバルザックの言につながっていったと考えられる。
メザンジェールが『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』の社主兼編集長になってまず目をつけたイラストレーターが、カルル・ヴェルネだった。戦争画で知られるカルルは1800年にマレンゴの戦いに従軍したことでナポレオンの知るところとなる。メザンジェールは1802年から彼に同紙のファッション・プレートを依頼するが、1808年には当時の現代美術展であるサロンでナポレオンに作品を絶賛されたほどで、メザンジェールの目論見はあたったといえるだろう。
だが、むしろ歴史家たちの評価が高いのは、1811年末にカルルからこの仕事を引き継いだ息子のオラース・ヴェルネだった。オラースもまた、オルレアン公(のちのルイ・フィリップ王)、皇帝ナポレオン3世と、七月王政期から第二帝政期にかけての時の国家元首たちのお抱え画家で、戦争画を多く描いていたことで知られている。詩人で美術評論家のシャルル・ボードレールは美術評論『1846年のサロン』でヴェルネのことを「絵を描く軍人」と評したほどだが、ヴェルネはキャリアを通じて肖像画家としての評価も高かった。アレクサンドル・デュマは「アングルやオラース・ヴェルネによる油彩の肖像画は3000フランもする」4とある記事で述べていて、19世紀にはフランスを代表する肖像画家のひとりと目されていた側面もうかがわせる。
そのヴェルネが『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』のファッション・プレートを描いていたのは1811年から1817年のことで、なんと弱冠22歳で父親からこの仕事を引き継いだことになる[図1]。
 『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』1815年2月5日付 フランス国立図書館蔵.jpg)
当時の絵画には厳然なヒエラルキーがあり、その上位は聖書や神話を主題とした歴史画(物語画)、あるいはヴェルネ家が携わった戦争画などで、ファッション画のような世俗的な主題は下位のものと考えられていた。当然、当時の画家たちのキャリアにとっての究極目標である美術学校の教授や美術アカデミーの会員になるには高位とされていた主題を扱っている必要がある。
ヴェルネはのちにわずか14席しかないフランス美術アカデミー絵画部門の会員やローマのフランス・アカデミーの院長を務めるなど、名実ともにフランス美術界の重鎮となるのだが、そのヴェルネも初期にはかつての父親同様に世俗的な仕事を請け負っていたのである。
最近までヴェルサイユ宮殿で開催されていた大回顧展でも1810年代に描かれた作品はそう多くは出ていなかったことを鑑みても、『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』での仕事はヴェルネの初期の画風を知る有力な資料ともいえよう。
ヴェルネは当時から描くのが早いことに言及されており、それは5日おきに発行されていた新聞のファッション・プレートを描くにあたって重要な能力だったに違いない。くわえて、美術史家のヴァレリー・バジューは1815年から1828年にかけてがヴェルネ作品におけるもっとも優れた時期だと指摘していて5、これは『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』にファッション・プレートを描いていた時期の最後の2年とも重なる。
『ギャルリー・デ・モード』の彩色ファッション・プレートに比べると、色彩は淡く、全体的にシンプルな描画である。かつ、彫り師ジョルジュ・ガティーヌの卓越した彫版によって繊細な印象を与えている。
新聞と政治 ナポレオンの影
もうひとつ興味深いのは、この初期の重要な仕事がヴェルネののちのキャリアにも影響を与えていることだ。1817年、オルレアン公ルイ=フィリップはヴェルネに油彩肖像画《スイスの風景の中のオルレアン公ルイ=フィリップ》を依頼している。この絵の中の公爵こそが、ローズ・ベルタンをアントワネットに引き合わせたシャルトル公爵夫人の息子で、のちに七月王政でルイ=フィリップ王となるその人である。
先代の父オルレアン公がフランス革命時に美術品のコレクションを失ったことを残念に思っていた彼は、スイスやイタリア、イギリスでの亡命生活を経てフランスに戻って以降、自分で現代美術のコレクションを築くことにした。その際、画家のフランソワ・ジェラールに手紙で意見を求めるものの、オルレアン公はその返信の中には名前のなかったヴェルネに目をつけたことが知られている。こういった、若い才能を発掘する眼力と嗜好は母親譲りであるように思えてならない。
1817年といえば、ナポレオンの退位とともに一度はフランスに戻ったものの、すぐに2年の間イングランドに追放されていたオルレアン公が再びフランスに戻った年であり、ヴェルネが『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』から手を引いた年にあたる。ヴェルネのキャリアアップがなぜこうもトントン拍子に運んだのかというと、それはジャーナリズムをめぐる政治の力学にほかならなかった。
『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』も、モード新聞といってもやはり新聞は新聞。政治的立場というのが重要になってくる。ナポレオンが失脚すると、ルイ18世と大貴族が亡命先からフランスに戻ってくることとなる。それを機にメザンジェールは正統王朝派に読者層を絞り、ナポレオニストだったヴェルネと訣別することになる6。そこでヴェルネを庇護したのが、このときにふたたびフランスの地を踏んだ、やはりナポレオン贔屓だったルイ=フィリップだったというわけだ。
彼がこの肖像画を気に入ったことは想像に難くない。なにしろ、彼はその後ヴェルネのアトリエを訪れたり、逆に居城に彼を招いたりとかなり親密だったようで、1830年に王になったときには30点ほどのヴェルネの作品を所有するまでになっていた7。
バジューはヴェルネが近代的なジャンルとなった肖像画の(主題としてのヒエラルキーが低かった)劣等感を払拭した人物であると評している。この時期のヴェルネの油彩肖像画とファッション画を見比べてみると、アカデミックな画風のファッション画というべきか、ファッション画的な肖像画ということができるのか迷う。ただ、後年の作も含め、ヴェルネによる肖像画における衣装のディテールの細かさや、モデルが背景よりもほんの少し明るく描かれているのは、必ずしもアカデミスム絵画の基礎をなす写実描法や明暗法の訓練だけで得られたものではないという感じがするのである。
最大のライバル紙、『ラ・モード』の登場
『ジュルナル・エ・ダム・エ・デ・モード』はモード新聞としては成功していた部類で、1831年まで予約購読者数は2500部を誇っていた。ちなみに、この数字はほぼ同時期にあたる1835年当時の日刊紙20紙の購読者を合わせた数字が約7万人であったことを考えれば、立派なものといえよう。この時代の新聞はかなり高価なものであったし、しかも各号のバラ売りをしておらず、定期購読だけだった。
『ジュルナル・エ・ダム・エ・デ・モード』の年間購読料は36フラン。現代の貨幣価値でおよそ3万6000円だが、当時の肉体労働者の平均月収が50フランほどだったことを考えれば決して安いものではない。それでも堅調に発行を続けていたのは、ファッション・プレートの質の高さにあったのだが、1829年には強敵が現れる。エミール・ド・ジラルダンとロトゥール=メズレーが創刊したモード新聞『ラ・モード、流行批評、風俗通信、サロン案内』である。
このジラルダンという人物については鹿島茂の『新聞王伝説 パリと世界を征服した男ジラルダン』に詳しいが、1828年に新聞各紙の興味をそそる記事をそのまま剽窃して寄せ集めることで安価を実現した新聞『ヴォルール』(盗っ人の意味)を創刊して大成功を収めた経歴のあるやり手のジャーナリストである。

ジラルダンは『ヴォルール』以降多くの新聞を発行するが、そこに共通する手法は、薄利多売や割安感を読者に与えるというもので、彼にとって2つめの新聞となる『ラ・モード』も例外ではない。年間購読料は『ジュルナル・エ・ダム・エ・デ・モード』と同じく36フランだったが、ページ数が約3倍の34ページという代物である。
創刊半年後には、発行部数は早くも『ジュルナル・エ・ダム・エ・デ・モード』に並ぶ2500部まで伸びた。さらに購読者を増やそうと画策したジラルダンは、予約購読者への抽選による景品を用意したり、従来1号につき1枚だったモード画を2枚に増やすなどのアイデアを実現していった。
ジラルダンは明らかに『ジュルナル・エ・ダム・エ・デ・モード』をライバルに据えていた。それはつまり地方在住の上流階級の女性を同紙のターゲットに考えていたということだが、創刊してみると、流行の発信地であるパリの上流階級の人々が熱心な読者になるというなんとも珍妙な現象が起きたのである。どうやらこれは、当時フランスにも浸透しつつあったイギリス流のおしゃれを信奉する人々の中心的存在であったベリー公妃がいち早く予約購読者になったことが強い後押しとなったようだ。そして、このモードの中心地を撹乱する現象は『ラ・モード』を新たな次元へといざなう引き金となってく。
ジラルダンの戦略に見る現代のファッション誌の源流
鹿島茂は『ラ・モード』について興味深い指摘をしている。それは、『ラ・モード』の記事が一見同じような装いをしているパリのおしゃれな人々の細かな差異(ディスタンクシオン)に触れることで、読者たる当の本人たちはそれが記事になっていることを確認して悦に入り、その差異性を作り出すのにさらに腐心するようになったというものである8。
そこに着目したジラルダンは、ファッション・リーダーたちの競争を助長するための奇策を思いつく。それは、鹿島も指摘するように、2枚に増やしたモード画にときおり馬車のイラストを掲載したことだ。これが驚くに値するのには二つの理由がある[図2]。

一つは、馬車こそ当時の上流階級にとって差異性を発揮するアイテムであったこと。そしてもうひとつは、馬車の製造所名と住所が記されており、製造所から広告料を取るというものだった。当時のフランスの新聞にはまだ広告の掲載はなく、純粋に購読料だけが収入源だったから、ここに広告料を加えることで収益を上げるというシステムが創出されたことになる。
だが、さらに重要だと思われるのは、そのメーカーや住所を記すという“キャプション”のありようではないだろうか。現代のファッション誌を開くと、ほぼ必ずページの端に、モデルが着用している服やアクセサリーのブランド名、価格が記されている。ファッション誌には鹿島らのいう差異性なり、自分もこのような装いをしたいという自己投影の欲望が作用する。こうしたキャプションはファッション誌において、それらの欲望を叶えるための入り口にもなっているのである。
『ラ・モード』が刊行されていた19世紀前半は既製服などまだない時代だったので、モード画やファッション・プレートにこうした実用的なキャプションをつけるという必要性はまったくなかった。しかし、20世紀になって写真がファッション誌に使用されるようになると、その当初からブランド名が写真の下ないしは横に添えられているのを見ることができる。つまり、ジラルダンはファッション誌がもつ、欲望を叶える入口としてのキャプションというシステムさえ先駆的に発明していたことになるのだ。
広告にせよキャプションにせよ、それは、のちの19世紀後半から創刊されるモード紙誌には、当たり前に採用されていくものなのである。
そして七月王政期に入ると、宮廷が質素倹約を重んじたために、フランスのファッション事情はまたも一時的に 衰退していくこととなる。そうした状況をいち早く察知してか、ジラルダンは1831年に『ラ・モード』の経営権を過激王党派に売却してしまう。
ここまで見てきたように、マリー=アントワネットの時代からナポレオンの時代にかけてのファッション・ジャーナリズムは、現代のファッション誌にまで引き継がれる編集手法を確立していった。この前後にも大小さまざまなモード新聞やコスチューム・プレートの版画集がフランスやイギリスで刊行されている。
フランスにかぎって少しだけ補足をしておくと、ヴェルネが去ったあとの『ジュルナル・エ・ダム・エ・デ・モード』では新たにルイ=マリー・ランテを迎える。メザンジェールの編集で1827年に刊行された版画集『コー地方、および古ノルマンディー地方のいくつかの郡の女性の衣装』は、コスチュームにとどまらず、風景が描き込まれており、もはやファッション画の枠を超えて、油彩の肖像画に匹敵する力作である。ランテ時代の『ジュルナル・エ・ダム・エ・デ・モード』のライバル紙とも目される『プティ・クーリエ・デ・ダム・ウ・ヌーヴォー・ジュルナル・デ・モード』は同じ衣装を着たモデルを正面と背後から描いたファッション・プレートを掲載するなど、全方位的に衣装を見られる新機軸を打ち出していった。
それらの動向もまた興味深いところではあるが、そろそろ時代をもう少し進めて、写真が登場して以降のファッション・ジャーナリズムを見てみることにしよう。
そのためにも、まず次節では肖像写真の歴史を簡単に見ておきたい。1839年にフランスでは写真術が公表され、第二帝政下の1850年代には技術革新や写真館同士の顧客獲得競争も相まって写真の撮影料金が下がり、爆発的に普及していく。
この第二帝政期の写真事情こそが、ファッション写真のもう一つの源流となる、肖像写真の新たな文化を花開かせていくこととなるのである。
- 1801年にセレックが暴漢に襲われて死去したのち、メザンジェールは『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』の株を買い取り、さらには競合紙『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・ヌヴォテ』を買収して社主兼編集長となった。 ↩︎
- Honoré de Balzac, Monographie de la presse Parisienne(Extrait de l’histoire naturelle du Bimane en société), 1843 ; 鹿島茂訳『ジャーナリストの生理学』講談社、2014年、pp. 242-243。 ↩︎
- Françoise Tétart-Vittu, “Carles et Horace Vernet et le Journal des dames et des modes de Pierre de La Mésangère”, Horace Vernet (1789-1863), Éditions Faton, 2023, p. 48. ↩︎
- “Alexander Dumas on Photography,” The Photographic News, August 10, 1866, p.379. 実際、ボードレールも『1846年のサロン』でヴェルネのことを「きわめて国民的な芸術家」と呼んでいる。 ↩︎
- Valérie Bajou, “Le Voltaire de la painture”, Horace Vernet (1789-1863), Éditions Faton, 2023, p. 102. ↩︎
- 鹿島茂「ファッション・プレートの誕生 版画という複製芸術のオリジナリティ」『モダン・パリの装い 19世紀から20世紀初頭のファッション・プレート』求龍堂、2013年、p. 24。 ↩︎
- その前年、1829年にヴェルネがローマのフランス・アカデミー院長に任命されるにあたっても、オルレアン公の後押しがあった。 ↩︎
- 鹿島茂『新聞王伝説 パリと世界を征服したジラルダン』筑摩書房、1991年、pp. 42-52。 ↩︎