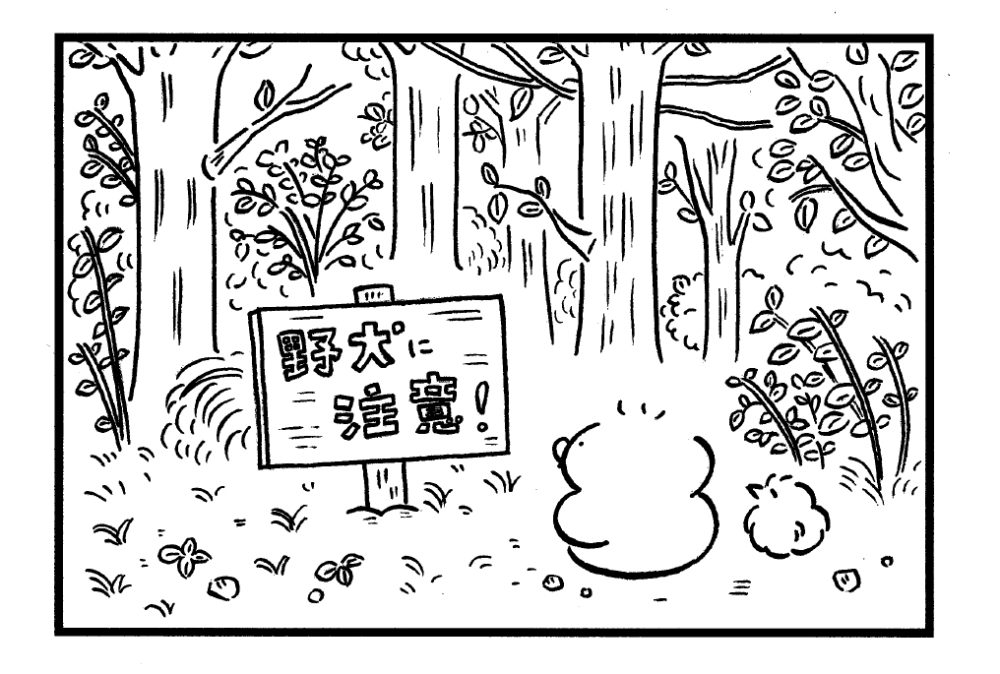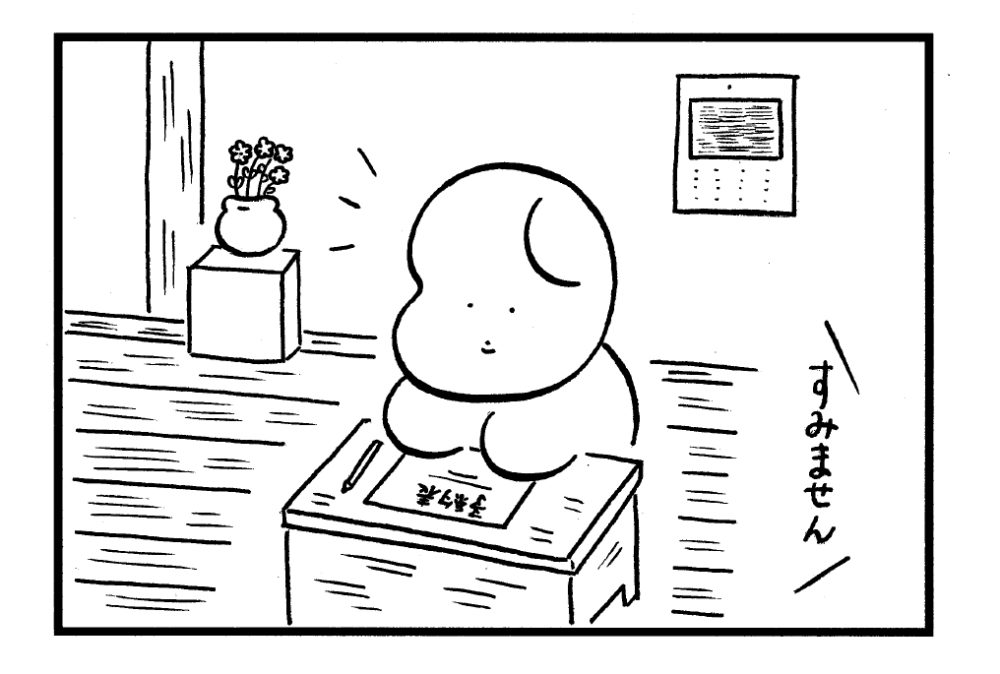「豊かさ」の誕生以前のファッション・ジャーナリズム
あるものごとの起源がどこに求められるのかを確定させるのは意外にむずかしい。それはファッション写真も例外ではないが、素因数分解的にファッション・イメージをひもとくと、大きくふたつの源流をみいだすことができる。ひとつは、ファッション誌の歴史から見た場合、それは写真が印刷媒体に掲載されるようになる前から存在する、服飾の流行を伝えるモード新聞に掲載されていたイラストやファッション・プレート、ないしコスチューム・プレートと称されるもの。もうひとつは、写真の歴史から考えた場合、それは肖像写真ということになる。いずれも肖像を主体にした表象というのが結節点になってくるが、ここではまずファッション・ジャーナリズム、すなわちモード新聞の成り立ちについて見ていきたい。
先に触れた、その要となるファッション・プレートとは、18世末から20世紀のはじめにかけて制作された、ファッション写真同様の役割をもった彩色版画のことをいう。厳密には、服飾史ではそれ単体で版画集のようなものとして出版されたものをコスチューム・プレート、挿絵入り新聞の口絵グラビアの役割を果たしていたものをファッション・プレートと呼ぶ。写真がまだなかった時代、大量に複製できる視覚情報伝達のメディウムは版画だった。版画自体の起源はルネサンス期にあたる1470年前後まで遡れるが、絵入り新聞などの定期刊行物ということになると、やはり18世紀まで待たねばならない。では、服飾の流行(モード)を伝える定期刊行物が登場した18世紀後半、もう少し具体的にいえば1770年代から80年代のヨーロッパとはどんな時代だったのかというと、モードの中心地フランスは、かのマリー・アントワネットの時代である。
活字や少数の版画で流行を伝えるファッション・ジャーナリズムが成立するおよそ10年前、イギリスでは産業革命が始まっていた。産業革命の成果は鉄やガラスの工業製品化がメインだと思われがちだが、最も大きな成果として現れてくるのは、16世紀以降手工業とほぼイコールの意味合いをもっていた繊維産業である。この産業革命を起点として中産階級が生まれ、これがファッションという文化を生み出す原動力になる。個々の生産量(収入)が増えることで服飾をはじめとするファッションに使える余裕ができる。それによって流行が生まれ、ファッションを扱うジャーナリズムが登場するという構図である。つまりモードは基本的に資本主義経済あってのものということになるが、流行を伝える最初期のモード新聞が登場した頃は、まだ資本主義経済は揺籃期だった。スコットランドの経済学者アンガス・マディソンは『世界経済 1000年の展望』 (The world economy: a millennial perspective, Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development)の中で、1820年以前には経済成長は実質的に存在せず、1600年から1820年までの間、西ヨーロッパにおける一人あたりの年間のGDP成長率は平均して0.15%程度だったとしている。いったい、経済統計が存在しない時代のGDPをどのようにして算出したのかという疑問が湧くが、ウィリアム・バーンスタインは『「豊かさ」の誕生』において、マディソンがとった一人あたりのGDP400ドルという仮定の数値の恣意性を指摘しつつも、一方ではその妥当性も主張している。数百年という時間軸の中では、一人あたりの年間生産額が倍だったと推計したとしても誤差が0.1%以下になるという彼らの検証には、たしかに説得力があろう1 。

実際、ここで見ていくアンシャン・レジーム末期のフランスに関しても、服飾の流行を追ったりファッション・ジャーナリズムを享受できたのは、王侯貴族か大商人だけだった。つまり、1820年以降に急速な経済成長が始まり、それによって中産階級が登場して資本主義経済にシフトしていく状況がバーンスタインのいう「豊かさ」の誕生だとすれば、モード新聞の始まりは豊かさ以前の話しということになる。
一般的に、イギリスもフランスも国力としては産業革命にいたる要件は揃っていたとされる。ところが七年戦争でイギリスがフランスに勝利したことから、フランスは植民地を獲得できず、18世末紀時点では産業革命を起こすことはできなかった。つまり、イギリスが資本主義へと舵を切っていく一方、フランスは大革命まで封建社会が続いていく。それでもなおフランスがモードの中心地だった一つの理由として考えられるのは、流行を牽引するカリスマと、その発信者がいたからにほかならない。その人物こそが、マリー・アントワネットと彼女の「モード大臣」ローズ・ベルタンだった。
「野暮ったい王妃」の輿入れ
ところで、ルイ16世時代の王妃マリー・アントワネットを中心とした宮廷の事情について、池田理代子の漫画『ベルサイユのばら』から学んだという読者も少なくないのではないだろうか。実際、『ベルばら』にはアントワネットがファッションに傾倒して異常な浪費をしたり、それがフランス革命への不穏な空気の醸成につながっていくさまが史実に基づいて事細かに描き出されている。

そもそも、マリー・アントワネットが1770年にフランスに嫁いだ際、時の国王ルイ15世の王妃マリー・レグザンスカはすでに亡くなっていたので、アントワネットははじめから宮廷内でもっとも身分の高い女性ではあった。とはいえ、結婚直後からルイ15世の公妾のデュ・バリー夫人との折り合いが悪いなど、宮廷内には敵も多かった。とくに、1774年にルイ16世が即位して王妃となって以降は、権力基盤の確立は重要度を増す。というのも、即位の時点ではまだ王太子が誕生していなかったからである。当時のフランスは王国基本法で王位の男系継承が定められていたため、ルイ16世の弟であるプロヴァンス伯が王位継承者として存在感を増していた。しかも彼はアントワネットを嫌っていたとされるので、宮廷内でいまだ不安定な権力基盤を確固たるものにするのは喫緊の課題だったのだ。そのための武器となったのがファッションである。
とうぜん、ファッションを権力基盤として利用するからには、そのモードが情報として流通し、自分がインフルエンサーとしての地位を獲得しなければならない。なぜ王太子妃時代にそうしなかったのかと言いたくなるところだが、王太子妃時代の彼女のファッションはあまりぱっとしなかったようだ。王太子妃の衣装係に任命されたのはヴィラール公爵夫人。彼女はもともとマリー・レグザンスカの衣装係だった人物で、30年も前に任命されたというありさまだった。フランスに足を踏み入れるにあたって与えられたお仕着せの衣装は、周囲の貴婦人たちと比べても冴えないものだったようだ。
少し時間を遡って、1770年に彼女がフランスに嫁ぐときの様子を見てみよう。アントワネットのフランスへの輿入れは、オーストリアとフランスの国境であるライン川の中洲に作られた離宮で行われた。フランス側に引き渡されるにあたって、アントワネットは侍女から着替えを促される。『ベルサイユのばら』では次のように描かれている。
オーストリア製のものはすべて……1本の糸すら身につけていくことはゆるされないのです。ぜんぶフランス製のものにきがえていただきます。〔……〕レースもリボンも十字架も指輪も…下着もでございます。 2
実際に、アントワネットは離宮でそのようなことを伝えられたのだろう。ヴィラール公夫人によって用意されたドレスに着替えることは、すなわちフランス王太子となる儀式なわけだが、それはファッション・インフルエンサー誕生の瞬間とはならなかった。他方で、フランス側の随員として居並んでいた貴婦人たちの多くは、当時宮廷で最も重用されていた「トレ・ガラン」というモード商のドレスを身につけていたという。それらのドレスは、従業員のひとりで、のちにアントワネットの「モード大臣」と称されるローズ・ベルタンことマリー=ジャンヌ・ベルタンによって仕立てられたものだった。
歴史家のミシェル・サポリは、『ローズ・ベルタン マリー=アントワネットのモード大臣』で、上記のエピソードを紹介した節のタイトルを「野暮ったい王太子妃アントワネット」としている。アントワネットがこのフランス随一のモード・クリエーターの衣装を纏うのは、王妃となる1774年まで待たなくてはならない。

モードの権力と「モード大臣」
ベルタンは、おりしもルイ16世が即位する前年の1773年にトレ・ガランから独立し、自分の店「オ・グラン・モゴル」(ムガル帝国の意味)を立ち上げていた。そもそもベルタンが王妃に面通しできるようになるには、しかるべき人物の紹介が必要である。その人物こそが、シャルトル公夫人ルイーズ・マリー・アデライド・ド・ブルボン=パンティエーヴルだった。ベルタンは、トレ・ガランに在籍していた1769年に、彼女の結婚式の衣装を担当した。これが大成功し、ベルタンの名前は結婚式に臨席した人々を通じてたちまちに知れわたる。さらに幸運だったのは、シャルトル公夫人は若い才能を世に送り出すのを生きがいとした人物で、ベルタンは以降寵愛を受け、アントワネットに紹介されることとなった。ちなみに、アントワネットの肖像画を多く描いたエリザベート・ヴィジェ=ルブランを引き立てたのも、シャルトル公夫人である。
さて、先王ルイ15世を死にいたらしめた天然痘が付き添っていた娘たちにも感染するという事態に発展したことで、ルイ16世夫妻はヴェルサイユから10キロほど北のマルリーに隔離されることとなった。ほどなくしてそこを訪れたのが、ベルタンを伴ったシャルトル夫人だった。サポリの考察によれば、それは即位から1か月ほどしか経っていない1774年6月20日から30日の間であったという。そこから大革命までの約15年、アントワネットとベルタンの黄金時代が続いていくこととなる。
圧倒的に情報の流通量が少ないアンシャン・レジーム期にあって、アントワネット時代の宮廷のファッションは信じられないスピードで移り変わっていた。縁なし帽などにいたっては、ひと月後にはすでに流行遅れというようなありさまである。サポリはフランソワ・メトラの『秘密書簡』を引きながら、1778年にオ・グラン・モゴルを訪れた貴婦人に対して、ベルタンがアントワネットと図って8日以内には新しい縁なし帽を登場させないと決めていると発言したエピソードを紹介している3 。これが、ベルタンが「モード大臣」と呼ばれるようになったきっかけだった。しばしば指摘されるように、この時代の装いとは、権力の反映である。ベルタンが持参した新作のドレスを早く見たいがために王妃が宮廷内の貴婦人たちの相手をないがしろにしたとか、ベルタンが宮廷内で平民とは思えないほど横柄な振る舞いをしていたなどのエピソードは枚挙にいとまがない。モード大臣の呼び名はアントワネットの厚い信頼によるものだけではなく、いかにモードが権力と直結していたかの証しであり、ベルタンの影響力の裏返しでもある。
そして、こうしたモードのめくるめく展開にジャーナリズムが反応してきたのである。
フランス初のモード新聞、その光と影
おりしも「モード大臣」誕生と同じ1778年、フランスで最初のモード新聞が創刊された。『ギャルリー・デ・モード・エ・コスチューム・フランセ』という、銅版画に着彩をほどこした6枚セットの分冊(カイエ)に、簡単な説明書きが添えられた旬刊のモード紙である【図1】。

フランスを中心としたヨーロッパの宮廷ファッションはこうしたモード紙の登場以前から流通の手段がないわけではなかった。たとえば、ファッション史の中でよく知られるものとして、流行の衣装を纏ったミニチュアの人形(フランス人形)がある。ただし、もちろんこれ自体が本物の衣装を摸したミニチュアのオートクチュールとでもいえるようなものだったから、その伝達能力には限りがあった4 。そこで重宝されたのが、当時の一大メディアである版画だった。とりわけ銅版画は、伝統的に油彩画を複製して伝える媒体として機能しており、これが西洋世界で絵画表現のトレンドを作り出すのに重要な役割をはたしていたのだ。
18世紀の時点でそうした版画を用いた視覚的な情報流通経路が確立されていたのだから、フランス発のモードの伝播に銅版画が利用されるのは自然な流れだったといえるだろう。精緻な線を彫れ、耐久度も比較的高いエングレーヴィングや木口木版は18世紀から19世紀にかけて新聞などの挿絵に用いられ、現代のファッション写真のような役割を果たしていたのだ。
『ギャルリー・デ・モード』第1年版の合本版の序文では、その影響力がモードにも発揮されたことが語られている。
『ギャルリー・デ・モード』は現時点でいくつかの有益な観点から考えることができるだろう。男女を問わず、新しい衣装や君臨するモードを知ることが容易になる。また、同時代の人たちと調和するために自分たちが何を望むのか、あるいは何をしなければならないかを教えてくれる。本書が海外に流通することによって、フランスのモードを手に入れたいという欲求を喚起することができるのだ。ヨーロッパ全体が、ファッションに関してはフランスの産業に依存していることはよく知られている。この嗜好は気まぐれの結果ではなく、フランス婦人たちの、装いに関するあらゆるものに対する独創的な才能によるものであり、何よりも、彼女たちの手から生まれる些細なものを特徴づける繊細なセンスによるものである。 5
まさに、フランスモードにおける輸出カタログの役割を目指していることがこの文章からうかがえる。そして、そのモードのインフルエンサー的存在がアントワネットだったのは、もはや説明の必要はないだろう。レイモン・ゴドリオは『フランスの女性ファション版画』の中で、同紙の版画がモード商の指示に基づいて描かれたものが多かったというコルニュの説を引いた直後に、その最たる人物としてベルタンを紹介している 6。
実際、アントワネットとベルタンの関係を考えれば、この示唆は当然というべきだろう。『ギャルリー・デ・モード』の版画にはベルタンの名前こそ出てこないが、同書を見てはるばる外国からフランスに衣装を仕立てに来た貴婦人たちがフランス一、すなわちヨーロッパ一のモード商であるオ・グラン・モゴルに直行したのは想像にかたくない。
ところで、先に引いた序文では「男女を問わず、新しい衣装や君臨するモードを知ることが容易になる」と書かれていたが、実際、同紙には少なからず男性の髪型や衣装のコスチューム・プレートも掲載されていた。とはいうものの、女性用のそれに比して圧倒的に少ないのは事実であるし、序文もほとんど女性のモードを想定して書かれている。つまり、実質的にこのモード新聞の想定読者は女性だったと考えて差し支えないだろう。では、そこにどのように男性読者を巻き込んでいったのかといえば、セクシュアルなイメージであった。
合本版を見ていくと、髪型を紹介する大量の版画に続いて衣装編のファッション・プレートがようやく登場するが、その1枚目は女性が石に片足を上げ、ストッキングを引っ張り上げているシーンという、にわかには信じがたいものである【図2】。序文では「本紙はあらゆるタイプのファッションの真の姿を伝えることを意図しているため、彼ら/彼女らの肖像を忠実に、できるだけ知性的に描くことが重要であった」とうたわれているにもかかわらず、キャプションには「彼女の美しい脚を見よ」と書かれているようなありさまだ。それが男性読者に投げかけられているのはいうまでもない。ページをめくっていくと、胸を露出したものなどさらに過激なイメージも散見される。現代でもファッション誌のほとんどが女性をターゲットにしたものでありながら起用されてきた写真家には男性が多いという指摘がしばしばなされるが、見る/見られることの非対称性がその最初期から存在していることには驚きを禁じ得ない。

美術史家の高橋裕子は、ルネサンスからロココの時代にかけての絵画にでは裸体で表される女性のほとんどは古代神話の女神やニンフ、ないし擬人像であり、その主題を理解するために古典の知識が必要であったという点で、教養人のための絵画であったと指摘している7 [7]。そうした教養のヴェールさえ纏っていない世俗的な絵、言い換えれば性的欲望に奉仕する目的のイメージという点では、その暴力性は公的な主題を描いた絵画よりも高いと言わざるを得ないだろう。
革命から革命へ
ところで、同紙の序文に目を通していて気になるのは、「革命」ということばが3度も使われていることだ。その意味するところは服飾や髪型の流行が大きく変化し、異常なまでに加速していったということである。だが、その後のフランスの行方を知っているわたしたちにとっては、いかにも意味深な単語に見えてしまう。実際、王政の廃止に向かうフランス革命自体、アントワネットとモードの関係が深く関係しているのだから、このことばは数奇としか言いようがない。
サポリによれば、1776年の夏にはすでにアントワネットの莫大な衣装代の一部を国王が肩代わりするなど、その浪費癖は周知の事実になっていたという。実際、公的な記録として、アントワネットが前年の1785年にベルタンに支払った金額は9万194リーヴル(約1億円)と、天文学的な数字になっていた。1785年といえば、ラ・モット夫人が引き起こした首飾り事件に無実のアントワネットが巻き込まれた年でもある。そのために彼女は裁判に出廷する羽目になるが、その場でラ・モット夫人がアントワネットの同性愛などのあらぬ証言をしたため、大衆の間には急速にアントワネットを嫌う風潮が形成されていく。
同時に、ベルタンの曖昧な請求書への多額の支払いは宮廷内でも問題視され、1786年8月には国王の諮問機関が召集され、緊縮財政の空気が広まっていった。実際、1787年のアントワネットからベルタンへの支払いは6万225リーヴルにまで下がっているので、1885年がこのモード革命=浪費のピークと見ることができるだろう。
かくも栄華はうつろいゆくと言おうか、モード革命がピークを超えた1778年、『ギャルリー・デ・モード』は廃刊にいたる。こうした事実と廃刊の関係を明言することはできないが、アントワネットとベルタン、そして『ギャルリー・デ・モード』が体現したアンシャン・レジーム末期の小さなモードの資本主義経済はこうして終わりを迎えた。そしてまもなくフランス革命が起こり、アントワネットの運命は断頭台へと歩むこととなる。ベルタンは処刑こそされなかったものの、革命後はかなりみじめな余生を送ったという。
- ウィリアム・バーンスタイン『「豊かさ」の誕生(上)』徳川家広訳、文庫版、日本経済新聞出版社、2015年、pp. 49-50。 ↩︎
- 池田理代子『ベルサイユのばら』集英社文庫版、第1巻、1976年、集英社、p. 45。 ↩︎
- ミシェル・サポリ『ローズ・ベルタン マリー=アントワネットのモード大臣』北浦春香訳、白水社、2012年、p. 42。『秘密書簡』はメトラが1775年から1793年までドイツのノイヴィートで発行していた週刊の秘密新聞で、フランス国外で発行されていたため検閲が甘かったといわれている。 ↩︎
- もっとも、当時の衣装は取り外し式のパーツが多かったため、フランス人形はそれをどのような順序で着付けていくのかを伝達する役割も担っていた。 ↩︎
- “Introduction”, Galerie des modes et costumes français, La ville de Coutances, 1779, p. III. ↩︎
- Raymond Gaudriault, La gravure de mode feminine en France, Les éditions de l’amateur, 1983, p. 35. ↩︎
- 高橋裕子『西洋絵画の歴史2 バロック・ロココの革新』小学館、2016年、p. 93。 ↩︎





 『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』1815年2月5日付 フランス国立図書館蔵.jpg)