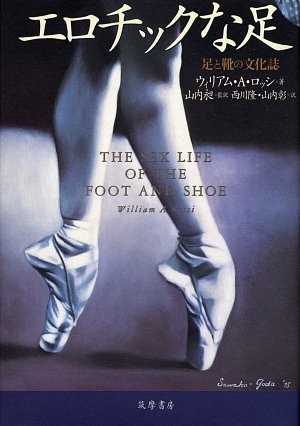intro 「ラブドールを想像/創造する」
「ラブドールについて連載をしてみませんか?」
ある日こんな便りが舞い込んできた。ラブドール、それはおもに男性の性欲処理を目的とした等身大愛玩人形の総称である。これだけ聞くと、「男性の欲望を満たすための道具でしかない」や「男性にとって生身の女性の代理物なのではないか」といったネガティブな感想を抱く読者もいるかもしれない。それを全否定することはできないが、だからといって全肯定することもできない。ラブドールをとりまく状況は、もう少し複雑なのだ。私は女性の身体に向けられた眼差しに関する表象文化の研究者で、その対象としているものの一つにラブドールがある。これまでにもラブドールに関する論考やインタビューなどを通して、ラブドールをとりまく状況の複雑さについて言及してきた。
そのため、今回のような依頼は初めてではなく、言ってしまえばよくある依頼の一つであった。しかし、連載となると少々事情が異なる。単純にラブドールの歴史や文化、それにまつわる問題――すなわちこれまで私がいろんなところで書いたり発言してきた内容――を書くだけでは変わり映えがない。私ひとりで書いていてもやがてネタが尽きてしまうだろうし、マンネリ化してしまう。私は編集担当者にそのことを素直に打ち明け、こんな提案をしてみた。
「往復書簡というのはいかがでしょうか?」
このやや風変わりな往復書簡の相手として白羽の矢が立ったのが、美術作家の菅実花さんである。菅さんは、2014年に始めたプロジェクト「Do Lovedolls Dream of Babies?」、のちに東京藝術大学の修了制作展(2016年)で発表した《The Future Mother》が注目を集めた。これは、ラブドールを妊婦の姿に加工しマタニティフォトを模して撮影した写真作品であり、私もこの作品を通して彼女の存在を知った。間接的に、いま私が研究しているものの後押しにもなった作品である。
菅実花《The Future Mother》(2016)その後、有り難いことに菅さんと直接お会いする機会に恵まれた。共通する対象(ラブドール)があるというのはもちろんのこと、ほぼ同年代であることや触れてきたものが類似していることなどから、気がづくと放っておけば夜を明かすほど談笑する仲になっていた。とはいえ、単に仲がいいから往復書簡の相手をお願いしたというわけではない。私は研究者として、菅さんは美術作家として、同じ対象を扱いつつも異なるアプローチをおこなってきた。また、「女性がラブドールを研究/表現対象にする」ことへの他者からの眼差しとそれにともなう葛藤も、同じようで異なる側面もあるだろう。そんな菅さんとであれば、ラブドールについて一緒に論じることができるのではないか。そういった目論見があった。
また、前述したようなラブドールをとりまく状況の複雑さについても、おそらくこの往復書簡が進むにつれて触れていくことになるだろう。ただし、そこで繰り広げられるやりとりが必ずしも「唯一正しい」見解ではないことに留意していただきたい。なにせラブドール論は始まったばかりなのだから。
「ラブドールソウゾウロン」。この往復書簡のタイトルは、「女ふたりでラブドールを組み立てる」というコンセプトから連想してつけられたものだ。ソウゾウには「想像」と「創造」の両方の意味を込めた。毎回お題となるテーマ――ラブドールを構成する各パーツから端を発したもの――から出発し、それについて研究者と美術作家のふたりが「想像」しつつ「創造」していく。さながら『フランケンシュタイン』のヴィクターがおこなった営みのようにみえるかもしれない。しかし、私たちはこれから想像/創造する子を「呪われた子」としてではなく「祝福される子」として生み出したい。読者はぜひそれを見守ってほしい。
さて、ここからは往復書簡の相手である菅さんに向けた最初の投げかけをしようと思う。いつも「実花さん」と呼んでいるので、以降、そう書くことを許してほしい。
01 肌
S to K
実花さんに最初に投げかけたいテーマは、ラブドールの「肌」についてです。
私がラブドールの存在を知ったのは、古い記憶だと大学生頃だったと記憶しています。その当時は「そんなものがあるんだ」程度で、今のような関心を持って触れたわけではありませんでした。しかし、是枝裕和監督の『空気人形』(2009年)を観て、今に近い興味を持つようになりました。主人公の「のぞみ」は現在の主流であるシリコン製のラブドールではなく、かつて「ダッチワイフ」と呼ばれていた頃によくあったビニール製の空気式人形として描かれています。それは、物語の中核をなす演出――空気の出し入れが生命を左右する――を表現するためにあえて空気式人形を採用したと思われますが、個人的に印象的だったのは、のぞみが雨水に触れてビニール素材から人間のような「肌」を獲得したところです。乾いたビニールから潤いのある「肌」へと変化することで、のぞみの姿形は人間と全く同じになります――ただし、肉体を得たわけではないというところがこの作品のミソであり、最大の悲劇だといえるでしょう。
ラブドールの発展のなかでとりわけ大きな変化の一つとして、素材が挙げられると思います。前述したように、現在はシリコン製が主流となっていますが、人間の肌に近い素材――いま最も近い素材はエラストマー(TPE)――にたどり着くまでさまざまな試行錯誤があったことは、実花さんもご存知でしょう。人と最も接触する「肌」がラブドールにとって重要な要素だという認識は、実際に触ってみるまであまり考えたことがなかった視点でした。しっとりとして弾力のある「肌」に、思わず感動した記憶があります。それまで私はラブドールの造形ばかりに注目していましたが、ラブドールの魅力は実際に触れてみなければわからないとその頃から思うようになりました。
実花さんは作品制作のために実際にラブドールをお迎えしているので、私よりもラブドールに触れている頻度が格段に多いと思います。そんな実花さんがラブドールの「肌」についてどんなことを考えられているのかお伺いしたいです。もちろん、作品制作を通してでも構いませんし、個人的な関心からでも構いません。また、差し支えなければ自己紹介も兼ねて実花さんがラブドールの何に惹かれたかについてもぜひ教えてください。