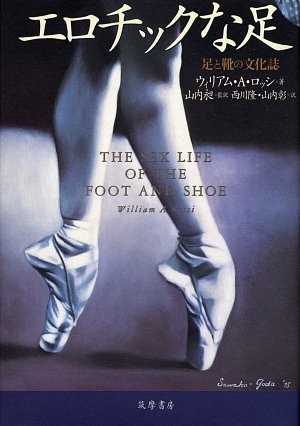返信ありがとうございます。記憶を遡っていくと、私たちはラブドールを扱っているという共通点以外に、フィクション上の人形やロボットに興味があるという点で意気投合しましたね。前回から今回にかけて話題となる内容でいうと、E.T.A.ホフマンの短編小説「砂男」(1817)やヴィリエ・ド・リラダンのSF小説『未來のイヴ』(1886)、フリッツ・ラング監督の映画『メトロポリス』(1926)あたりでしょうか。そのため、ついついこのあたりの話をし始めると脱線しがちになってしまいます。今後、必要に応じて触れていく機会があるかもしれませんので、それまでちょっと話題を温めておきますね。

実花さんが立てた「ラブドールは現実の女性に似ている必要はない」という仮説ですが、興味深く読ませていただきました。ここで参考になりそうなのが、前回実花さんが紹介してくださったオリエント工業の公式書籍『愛人形』に収録されている造形師、ドールメイク、ドールディレクターのインタビュー記事です。ドールディレクターをしている大澤瑞紀さんは、人間とラブドールでは「美しい」と感じるプロポーションには違いがあり、ある程度のデフォルメを要することについて話をされています。ドールメイクを担当している草野真希子さんも、ラブドールと人間では異なるメイクを施していること――「ファンタジー」を加えている――について言及されていました。また、造形師の靏久暢行さんは、ラブドールのヘッドは完璧な美人を目指しているのではないことを明言しています。靏久さんは、魅力的に見えるドールというのは、単純に見た目がいいだけではなく、ふとした時の表情であるといいます。基本的にラブドールのヘッドにはあえて特定の表情をつけておらず、ユーザーによって捉え方が異なるように作られているそうです。その意味では、自分の感情の写し鏡的な存在ともいえるかもしれません。
ただ、人間と持ち合わせているものが似ていると、どうしても比較してしまったり、人間を基準にその良し悪しをはかってしまう側面があることも否めません。前に紹介した『現代思想』のルッキズム特集で、私は次のように述べました。
ラブドールは単純に人間の女性をそのまま模したもの(=「リアル」)ではなく、草野の言葉を借りるならば「ファンタジー」を取り入れた身体――それは「見た目」から生じる理想的な関係性も含む――であり、それを求めてユーザーたちはラブドールをお迎えする。しかし、人間の女性の身体から完全に切り離されて造形されたものではなく、基準(=比較対象)となるのが人間の女性のなかでも美しい、プロポーションが整った女性であり、そこからいかに不自然に見せないようにするかといった引き算や足し算が行われているということも各インタビューからうかがえる。ゆえに、その違いにかなり意識的でない限り、明確な「リアル」と「ファンタジー」の境界が分かりづらいともいえる。そのため、「リアル」に「ファンタジー」を押し付けてしまう危険性もある。
(関根麻里恵「ラブドールの 「見た目」 に関するいくつかの覚書」『現代思想』49(13)、2021年、221頁)
似ている必要はないものの、参照元になっているものが人間の女性であるがゆえにその線引が非常に難しいというのは事実としてあります。哲学者の西條玲奈さんは、「人工物がジェンダーをもつとはどのようなことなのか」(『立命館大学人文科学研究所紀要』〔120〕、2019年、pp. 199-216)という論文のなかで、本来はジェンダーというものがないとされる人工物においてさえ、社会において特定のジェンダーと結びつけられがちな性質(西條さんはこれを「ジェンダーマーカー」と呼んでいます)を含んでいるとジェンダーが帰属されうることについて指摘しています。ラブドールに当てはめてみると、ラブドールも人形という人工物ではありますが、外見的には人間の女性に近いジェンダーマーカーを所有しているために、女性に帰属されうるといえるでしょう。
「美少女」というキーワードは、我々が好むSFでも繰り返し登場しますし、『ふしぎの国のアリス』でおなじみのルイス・キャロルや1980年代に日本で起こった「美少女ブーム」など、長いこと関心を寄せられてきた対象です。最近ではアバター上の「バ美肉(バーチャル美少女受肉)」もありますね。正直なところ、まだ「美少女」というものをうまく咀嚼しきれていない部分が多いため、いずれまたきちんと「美少女」について私なりの見解をお伝えできるようにしたいです。その代わりに一つ、バーチャル上の美少女アバターについて分析をしている松浦優さんの「メタファーとしての美少女」(『現代思想』2022年9月号所収)論考は、もしかしたら実花さんの関心に近いのではないかと思います。

さて、個人的に関心を持ったのが実花さんが紹介してくださった作品《Untitled 16》と台北の個展用に作られたPVにおける「手」の表現です。前者は、一見すると一人の女性が身体を折り曲げているようにも見えますが、よく見ると不自然。さらによく見ると、顔に触れている手と太ももに触れている手の質感で人間かドールかの見分けがつき、右側の上半身はドール、左側の下半身は人間(=実花さん)であることがわかります。これを見たときに、すごく新鮮に思った記憶があります。これまで作品上に二人が一緒に写っていたとしても、二人が触れ合っているものはあまりなかったので、お互いの身体に手が触れ合っているだけでこんなにも親密さが増す表現になるのか、とドギマギしました。後者のPVも視聴しましたが、これもおそらく実花さんだったら表現しないであろうシチュエーションで映されていて、これまた新鮮に感じました。写真と動画という性質の違いもあるかもですが、プライベートな空間でオフショット的に撮られた「素」の二人のような演出が印象的です。
ここで思い出してみたのが、この連載の第3回で紹介したしぐさの分析の項目です。その項目で考えると、《Untitled 16》は「5. 服従儀礼」に当てはまると思うのですが、よくよく考えてみると、この分析は男女の組み合せないしは女性のみのレイアウトやしぐさにフォーカスされていますが、女性同士の組み合わせの場合はどのように読み解けるかには言及されていません。おそらく男女の組み合わせをそのまま流用するだけでは取りこぼしてしまう要素が多分にあると思うので、これは今後の個人的な課題として考えていきたいです。

「目線」についても作品をご紹介いただきありがとうございます。《#selfiewithme》は展覧会ではよくスライドショーで展示されていて、さまざまなバリエーションのセルフィーを拝見していましたが、確かに目線がカメラに向けられていることで「楽しそう」という感情が読み取れますね。インカメラで撮影しているというのもポイントな気がします。
余談になりますが、2022年にトーキョーアーツアンドスペース本郷で行われた実花さんの個展〈鏡の国〉では、会場でのセルフィーを推奨していましたよね。私自身、あまりセルフィーをしないのですが、せっかくなので撮影をしました。最初は鏡の前でアウトカメラを用いて撮影をしたのですが、そうすると(私だけかもですが)スマホ画面を見てしまって目線がどうしても下を向いてしまい、あまり感情や意思を感じられない仕上がりに。セルフィーをしていた他の鑑賞者にこっそり目をやると、インカメラで撮影をしていたのでそれを真似したところ、レンズが目の前にあるので必然的に視線が正面を向く形になり、(個人比ではありますが)マスクをしているもののとたんに感情や意思を感じられる写真になりました。普段からセルフィーしている人からすれば当たり前なのかもしれませんが、私自身、カメラを向けられることに不慣れなところがあるため、個人的にはちょっとした発見につながりました。また、展示内容的にも、アウトカメラよりもインカメラで撮影したほうが分身的なものを感じやすかった気がします。


それでは実花さんからいただいた「顔立ち」についてお話していきたいと思います。よく二人で話す際、ラブドールは「メーカーによって顔立ちが違うよね」という話になりますね。例えば、オリエント工業は丸みを帯びた輪郭にタレ目がちな可愛い系のヘッド、アルテトキオ(EXDOLL)はシュッとした輪郭にややツリ目がちなクール系のヘッドが多い印象です。ただ、大枠で見たときに日本のメーカーは可愛い系が多い気がします。一方、中国メーカーのラブドールは、どちらかというとクール系のヘッド一択のような印象を受けました。
もちろん例外もありますが、こうした状況から国による理想的な顔立ちが類型化されているのかもしれません。そのため、一言で「美少女」的といっても可愛い系なのかクール系なのかという違いもありますし、より詳細に見ていったら別の系統がある可能性もあります。
今回、実花さんから返信いただいた内容をまるっと内包している事例として、私が長らく調査協力をお願いしている「人間ラブドール製造所」があります。2017年12月に東大阪で始まった逆転変身専門店で、「体験を通して自分を愛でられる人間を創造する」という理念を掲げラブドールになりきる体験を提供しています。私自身も初期の頃に一度体験をさせていただきました。
私自身の体験や実際に「人間ラブドール」になった体験者たちについては、『ポスト・ヒューマンスタディーズへの招待』(堀之内出版、2022年)に詳しく書いています。ここでは「顔立ち」と前回の私からの質問である「目線」に関する部分を抽出して紹介させてください。

最初に施されるのは「眼球の入れ替え」で、ここではやや色素の薄いカラーコンタクトレンズを入れます。私は目が悪いので、もともとつけていたコンタクトレンズからこちらに入れ直した際、視界がぼんやりしていてほとんどなにも見えていませんでした。しかし、これがそのあとの撮影で活かされることになります。
カラーコンタクトレンズを入れ終わった後、ラブドール風のメイクをしてもらうのですが、ここでポイントになるのが目元周りです。つけまつげをつけて長さとボリュームを増し、涙袋を入れ、二重幅を広めに作ることによってラブドールっぽさが演出されます。また、唇も中央から外に向かってグラデーションになるように色とツヤを入れていました。私は元の目が奥二重に近いので、あまりはっきりとした二重ではなく、どちらかというとツリ目がちです。しかし、先のメイクによってかなりタレ目になりました。あとから聞いた際に「オリエント工業のヘッドを意識した」とおっしゃっていたので、系統的には可愛い系にしてくださったのだと思います。
その後、いくつかの工程を経て「製品撮影」を行うのですが、すべてポージングはカメラマンに委ねられます。ただし、目線だけは眼球を動かしてもらうわけにはいかないので、指で目線を誘導してもらいます。前述したように、すでに視界がぼんやりとしていた私は、いい意味で意思のない目を演出できていました。

そして撮影が終了したあとに「ひとり遊び」の時間が設けられます。写真の選定・レタッチをしてもらっている間、好きなように過ごしていい時間です。多くの場合、ここでセルフィーを撮ったりするそうなので私もしてみました。面白いことに、どんなに視界がぼやけていたとしても、セルフィーのときにはレンズに目を向けようとするのです。自分ではあまり意識していなかったのですが、さっきまではラブドールのように振る舞っていたはずなのに、急に意思を持った人間がそこには写し出されていました。

仮に日本のメーカーに可愛い系の顔立ちが多いとした場合、その要素は目元によって構成されているといえるかもしれません。実花さんはどのように思われるでしょうか。
それに加えて新たな質問ですが、昨年発表された《Sisterhood》で、初めて複数のラブドールを写した作品を作られましたよね。その際、ボディも使い分けされていたかと思いますが、ボディの選定はどのようになされたのでしょうか。おそらくヘッドだけではなくボディでもそれぞれの役割を表現していたのではないかと推測するのですが、ぜひそのあたりのお話をうかがってみたいです。