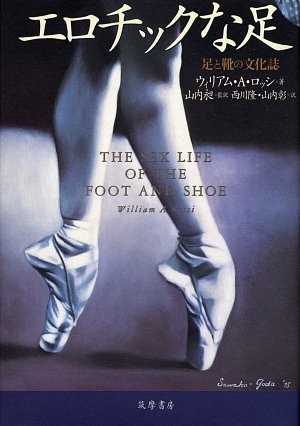返信ありがとうございます。研究者である麻里恵さんが整理してくれた概念によって、私が実際の経験に基づいて得た知見が立体的になっていくのが嬉しいです。
吉浦康裕監督は『イヴの時間』(2008年)のあとも『アイの歌声を聴かせて』(2021年)でアンドロイドと人間の関わりを描いていますね。アンドロイドの製造技術が発展し、人間と区別できない社会が訪れたという設定の物語は数多くあります。わざわざタイトルを上げるまでもないほど有名ですが、リドリー・スコット監督の『ブレードランナー』(1982年)や、スティーヴン・スピルバーグ監督の『A.I.』(2001年)などです。どちらも、通常アンドロイドと人間が区別される社会において、人間の領域にアンドロイドが踏み込むことで、軋轢が引き起こされます。
しかし、実際のアンドロイドの製造技術としては、同一空間内で肉眼で見分けがつかない水準になるには、まだ時間がかかりそうです。中国やアメリカのラブドールメーカーの中には、ラブドール本体の内部に駆動装置を入れて動かしているところもあります。しかし、動画で見る限りでは、リアルな人間と錯覚するほどではありません。人間と同じ基準で見るとまだ不気味さが勝ります。なのでアンドロイドは、今のところは「ぎこちなさに萌える」という方向性で受容するに限られるように思います。
「DS Robotic Doll Video… Coming Soon! Enjoy the Montage of the robotics project so far!」(DS Doll Robotics, YouTube)
さて、「肌」の話題に戻りましょう。
麻里恵さんも映画『空気人形』(2009年)の「パーティングライン」の描写の違和感に気が付かれていたのですね。素材についての知識がないとわからない部分なので、おそらく多くの人にとっては気にならない程度の演出上の「嘘」なのだと思います。実際のラブドールを知っているからこそ引っ掛かるのですが、物語として何を表現するために改変したのかを見つける糸口でもありますね。
タナダユキの『ロマンスドール』は小説(2009年)の後に映画(2020年)が製作されました。私は映画を観た後に小説を読んだのですが、素材選択についての改変があったことはすっかり失念していました。たしかに「そのこ1号」をシリコンで作るのか、エラストマーで作るのかといった違いは、監督がどう設定するか、あるいは協力メーカーの都合か、といった観点で考えることが可能ですね。それ以外には、小説が書かれてから約10年後に映画化されたという要素があります。つまり、当時は最先端の素材だったエラストマー製のラブドールが、実際にたくさん生産されるようになった後で映画が作られたことに起因しているのではないか、ということです。
現在、現実的にメーカーが「エラストマー製で勝負する」場合、少し人形についての知識があれば、「価格を下げて造形を妥協するということ?」と頭に浮かんでしまいます。私も実際にエラストマー製の人形を見たことがありますが、塗装が浮いていて不自然な感じがしました。
私個人の感覚としては、エラストマーの触感はスライムのようで、あまり好きになれませんでした。シリコンは反発感のある弾力をもっているので、肌のハリのような感じがあります。しかし、エラストマーは低反発ウレタンのような触感でぐにゅっと凹むので、中に硬い芯が入っているスライムのようでした。
なので、実際に作られた人形を監督がリサーチした結果なのではないかと私は予想します。もちろん、空気人形のように、映画上の嘘として小説版のままの設定にすることもできたと思いますが、タナダユキ監督はオリエント工業の工場をほとんど再現したセットを作って撮影しているので、リアリティの水準を現実に近いところに求めたのだと思います。
「高橋一生・蒼井優出演・映画「ロマンスドール」BD&DVDメイキング映像の一部を公開!ラブドールの制作現場も。【7月3日(金)発売】」(ハピネットピクチャーズ, YouTube)
麻里恵さんが書かれている通り、人形は自然治癒しないから、「肌」が本当に全てを記憶しているのです。修復しても修復痕が残ります。最近、私の持っている人形も経年劣化で爪の先やひじ、膝の裏などがひび割れてきました。人形から「メンテナンス不足だ」と怒られている気分です。私も冬場は乾燥して、ひじや頬の皮向けが辛いので、一緒に保湿を頑張るしかないですね。
本題の「脚」ですが、ご指摘の通り、筋肉の動きは非常に重要です。私は生身の人間の造形に関して言うと、筋肉の形が美しいことに惹かれます。全体のポーズと筋肉の伸縮が連動して、機能と形が結びつくことで作られる造形が好きです。
私は専門的な美術の教育を受けてきました。絵画の基礎を学ぶにあたって、実際に人物モデルを観察しながら描く人物デッサンを毎週行いました。モデルは男性も女性も、年齢も様々で、着衣もヌードも描きました。美術教育、特に絵画の基礎において人物デッサンで重要なのは、骨と筋肉です。デッサンでは骨と筋肉の形を観察し、一人の人間として破綻なく表現することが求められます。
骨の形は生まれ持った要素が大きいのに対して、筋肉は後天的に鍛えて自分の体の形を造形することができます。モデルさんの筋肉の形は、モデルさん本人が日頃から努力しコントロールして表現してくれているものなのです。
一方で、人形には筋肉がありません。ポージングに対して、身体の形が連動しないのです。たとえば、人間はつま先を伸ばせばふくらはぎの形が筋肉の伸縮によって変化しますが、人形は足首以外の形はほとんど変わりません。なので、私の琴線にはあまり触れません。表面の皮膚だけが動くので、違和感が大きいです。したがって、形というよりも、無理に立たせていることから引き起こされる破損の方に意識が向きます。
「脚の演出」についての分類は面白いですね。
脚に限らず、あらゆる身体の部位はそれそのものがエロティックなのではなく、演出されて初めてその観点を持つことができるものだと、私も思います。
私の作品のうち、《The Silent Woman》という連作があります。これはモノクロの比較的小さめな写真作品です。大きな《The Future Mother》は完璧なポーズと照明を必要とする作品ですが、その制作中のちょっといいなと思った瞬間に、スナップショット的な撮影をしています。
これは、人形の頭を外した時に、妊婦さんの視界はこんな風なのかも、と思ってシャッターを切った一枚です。

菅実花《The Silent Woman 15》(2016)
なかには、わざと既視感がある図像に寄せているものもあります。この作品で私が参考にしていたのはストレートフォトグラフィと広告写真です。
なかでも、イモージェン・カニンガムのヌード写真は、身体を四角いフレームを分断する幾何学として捉えていて、よく参照しました。被写体の属性、年齢、その人個人の個性は考慮されず、写真の構図を構成する一要素として還元されるのです。モノクロームなので、平面上で白から黒までの色がどのように配置されるか、というところまで分解されます。
一方で、広告写真は記号を伝えるものなので、どのような身体なのかを認識させる必要があります。何らかの商品やサービスのイメージを伝えるためには、モダニズムのように身体を後景化させてはいけないので、適切な情報を盛り込むことが必要になります。被写体そのものの情報に加えてポーズやシチュエーションなどの演出が施され、身体の部位に対してフェティシズムを感じさせる余地が出てきます。
被写体を形や構図に還元したモダニズム写真における身体の扱いと広告写真における身体の扱いは、目的が異なりますが、どちらも身体そのものを生々しく捉えようとしないという点が共通しています。
なぜ私がこの作品で、この二つを参考にしたのかというと、人形の身体はそもそも全く生々しさを含んでいないからです。人形は最初からシンプルなツルツルした、デフォルメされた身体をもっています。
人間の身体は複雑なのに、多くの写真表現においては単純化されている。だから、人形で表現するとマッチしすぎて、逆に違和感がなくなります。そんなことを考えながら撮影していました。

菅実花《The Silent Woman 32》(2017)
リクエストしてくださった「エロティックさを軽減させた女性の身体の見せ方」についてお答えしましょう。
一番は、「堂々とすること」です。あらゆるものとの関係を断ち切って、自立していることが重要です。
《The Future Mother》はもっともそれを強く意識した作品です。
逆の例がわかりやすいので、単身の女性像のポーズでエロティックさを強調する例をあげます。「恥じらいのヴィーナス」のポーズは、美術表現においては古代ギリシャから続く定番ですが、強くエロティシズムを喚起します。
2023年から2024年にかけて東京都美術館、福岡市美術館などを巡回する「永遠の都ローマ展」で展示されている《カピトリーノのヴィーナス》もその代表作のひとつです。これは古代ギリシアの彫刻家プラクシテレスの女神像(前4世紀)に基づく2世紀の作品で、水浴後のヴィーナスが右手で胸を、左手で下腹部を隠しています。これは、女性本人は性的アピールをする気がなく、他者から性的に見られる目線を意識して、自らの身体を隠すというポーズです。エロティックな表現といっても、主体的に相手を誘うのではなく、弱く拒むことで逆に性的な印象を与えます。

《カピトリーノのヴィーナス》(カピトリーノ美術館 © José Luiz Bernardes Ribeiro, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53996071による)
ヌードであることとエロティックであることはイコールではありません。むしろ、人目を気にして中途半端に隠そうとしているという意志が透けて見えることが性的な印象を喚起します。麻里恵さんの表でいうと、「5.服従儀礼」「6.公認のしりごみ」に該当するでしょうか。
つまり、エロティックさは他者との関係性によって演出されます。撮影状況として被写体の近くに他者がいない、かつ作品として鑑賞者の存在も気にしないくらい自立した姿がもっともエロティックから遠ざかるのです。
ただし、展覧会となると制約を受けます。日本を含むいくつかの国では、展覧会で出展するときに施設側から「乳房を隠していないから展示不可」といった制限がかかる場合があるので、すべての作品が展示不可にならないように、ポーズのバリエーションをつけて作っています。
では逆に、私が今まで制作してきた作品の中で、ストレートにエロティックさを押し出した作品をお見せしましょう。
これは、今までお見せしてきた「ラブドールは胎児に夢を見るか?/Do Lovedools Dream of Babies?」シリーズではなく、「あなたを離さない/I Won’t Let You Go」という別のシリーズの作品です。私自身の頭部を石膏で型取りして、そっくりに造形してもらった人形と一緒に撮影したセルフポートレートです。作品のテーマとしては「クローン」を設定しました。もし体細胞クローン技術による人工的な一卵性双生児が存在したら、よくあるSFの物語のように悲惨な人生をおくるのではなく、幸せになれるのだろうか?と想像したのです。

菅実花《Untitled 09》(2020)
「ラブドールは胎児の夢を見るか?」に対して受けた批判として、「女性性と妊娠・出産を結びつけすぎている」「結局は美しい妊婦であれというイデオロギーを強化している」というものがありました。私としては「女性的な外見のシリコン製人形は女性なのか?」という疑問があるのですが、外見的特徴と性別を切り離せないと考える人にとってはそれ自体が無効な問いのようでした。
私が「ラブドールは胎児の夢を見るか?」で最も考えたかった「人間と非人間の境界」は、妊娠するアンドロイドとそれに宿った胎児がテクノロジーによって人工的に操作された生命であるとしたら、どこまでが人間といえるのだろうか?というものでした。
しかし、作品が持つそれ以外の要素によって探究が妨げられるのならば、別の問い方をするべきだと考え、新しいシリーズを始めました。人工的な生殖の一形態としてクローンをとらえられないだろうかと思ったのです。
この作品シリーズでの被写体は、片方が人間である私で、片方が型取りによって作ってもらった人形です。人形製作は引き続き、オリエント工業にお願いしました。これまでの仕事を通して信頼関係があることはもちろんのこと、人形の造形の方向性が、女性の求める人工的な美の方向性と合致していることがその理由です。未来の人間の姿を想像すると、オリエント工業製の人形と非常に近い外見になると予想できます。
《Untitled》では、意図的にソフトフォーカスに写すことで、人間と人形の区別をわかりづらくしています。境界線をぼかすことで、どこからどこまでが自己と言えるのだろうか?ということも問いに含めました。
この作品で最も意識したことは二人の関係性です。双子として密着して撮影し、肌や髪、服に触れている箇所も意図的に見せています。しかし、肌の露出はほとんどなく、全てふわふわもこもこの冬服で、体型もわかりません。
これは、「ラブドールは胎児の夢を見るか?」がエロティックすぎるという批判を受けたことに対して、「ヌードとエロティックを同一視するなんて浅はかだ。本物のエロティックさは露出度ではなく関係性で決まる」というアンサーです。
この作品では脚はほとんど写していません。主に顔、髪、上半身、そして手を中心に撮影しています(唯一写っている脚は私のもので、人形の脚は写していません)。
麻里恵さんが挙げてくださったラブドール写真の三つ分類のうち、私は美術作家としての表現なので③にあたります。
麻里恵さんは、関係性の表現について、これらのうちで何か気になるトピックはありますか?
①のメーカーや②の個人ユーザーによる写真だと、どのようなことが読み解けるでしょうか?