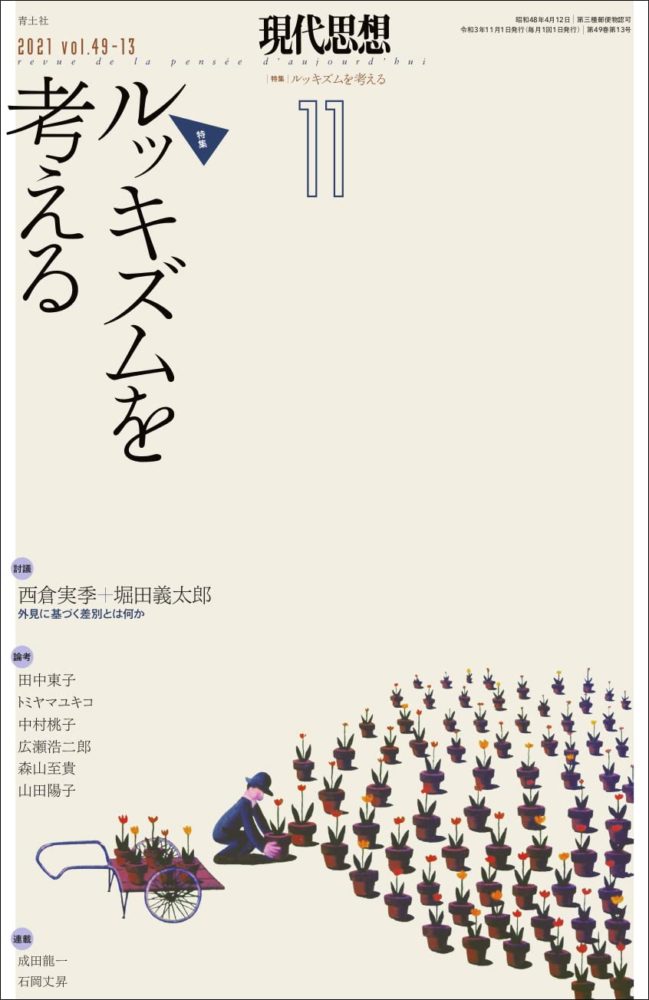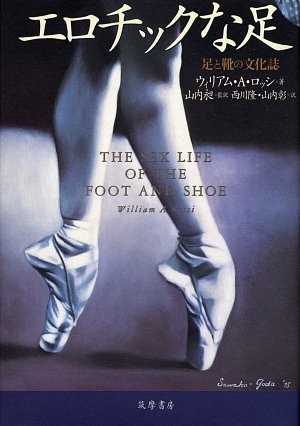返信ありがとうございます。まだ二往復目ですが、どんどん内容が深まっていく実感があり、私もワクワクしながら実花さんの返信を拝読しております。
おっしゃるとおり、アンドロイドやロボットと人間の関係について描かれた物語は枚挙にいとまがありません。キリスト教圏においては、人間の脅威となる存在として描かれやすい一方、日本だと手塚治虫の『鉄腕アトム』や藤子・F・不二雄の『ドラえもん』を筆頭に、親しみやすい存在として描かれる傾向にあることがよく指摘されます。近年では業田良家の『機械仕掛けの愛』(2010年〜2021年)や山田胡瓜の『AIの遺伝子』シリーズ(2015年〜)など、日本では映画以上にマンガの題材として好んで扱われている印象があります。また、2023年に『鉄腕アトム』の1エピソード「地上最大のロボット」をリメイクした浦沢直樹の『PLUTO』(2003年〜2009年)がアニメーション化されましたが、そこではアンドロイドやロボットの「記憶」というものに焦点が当てられていました(「記憶」をめぐる題材としては『攻殻機動隊』シリーズも外せませんね)。
「『PLUTO』予告編-Netflix」(YouTube)
これらの作品はすでに日常生活にアンドロイドやロボットが馴染んでいる時代が舞台となっているため、見た目による違いとは異なる水準で区別される要素が入り込んでいます。実花さんがおっしゃるように、まだまだ実際のアンドロイドは見てすぐ人間とは異なることがわかりますし、「ぎこちなさに萌える」というのは言い得て妙だと思いました。どこか応援したくなる気持ちというか、愛でるような眼差しがあるように感じます。
『ロマンスドール』(2020)における素材選択の改変について、原作が書かれた当時と映画が制作された当時の時代性、すなわち素材に対する評価がある程度共有されるようになったことが関与しているというのはあり得ると思います。私も何度かエラストマー製のラブドールを見て触ったことがありますが――実際にパートナーとして迎えるユーザーのなかには、柔らかい肌を求めている方もいらっしゃると思うので良し悪しはさておき――、実花さん同様、柔らかすぎる感触に少し戸惑った記憶があります。以前、『現代思想』のルッキズム特集で寄稿した論考のなかで歳を取らないけれど文字通り劣化してしまうラブドールについて少し触れたのですが、エラストマーは変色のしやすさもあいまって、シリコン以上に「自然治癒」のなさが際立って見えるような感じがしました。
また、「肌が全てを記憶している」というのはラブドールと人間の関係を考える上で重要な指摘だと思います。この点について、今後改めて検討できたら幸いです。
「脚」に関して、確かに筋肉の動きは人形では再現しづらい部分の一つですね。何度か実花さんとラブドールのポージングやアンドロイドの動きについて話したことがありますが、そこでも関節の動き、いわゆる可動域や筋肉がいかにリアル(に見えるか)に着目しながら話されていたことが印象に残っています。今はいかに見た目をリアルに見せるかというところに重点が置かれていますが、将来的にリアルな筋肉の伸縮が再現可能になったらまた違った展開が出てくるかもしれませんね。
「脚の演出」については、個人的にとても関心がある部分だったので、ある程度の同意を得られて嬉しいです。また、実際に実花さんが作品づくりをするにあたって意識している点も同時にうかがうことができ、大変勉強になりました。《The Silent Woman》は個人的にも好きなシリーズなのですが、なぜ好きなのかがようやく腑に落ちました。この作品で実花さんはストレート・フォトグラフィと広告写真を参考にして撮影されたとおっしゃっていましたが、私が好きなウジェーヌ・アジェもまた、ストレート・フォトグラフィ的ないしはカタログ的なアプローチをしていることに気が付きました。
アジェは30代半ばからアーティストたちのデッサンや作品制作の参考資料となる写真を撮り続け、40代に入ってからは新しい世紀を目前に劇的な変化を遂げていくパリの町並みを「記録」していました。ヴァルター・ベンヤミンは彼の写真が「犯行現場を撮影しているようだ」と評価されることについて言及していますが、実花さんの《The Silent Woman》にも同じようなものを感じました。さすがに「犯行現場」は仰々しいかもしれませんが、実花さんが作品の制作中に発見したラブドールの様子を「記録」し、それを資料として見させてもらっているという感じでしょうか。もちろん、それゆえに作品として成立していないとかそういうことをいいたいのではなく、通常の作品を見るスタンスとはまた違ったスタンス――作品を味わうのではなく、資料を読み込むような感覚――が個人的にはありました。もしかしたら意図しない作品の見方かもしれませんが、いち鑑賞者の感想として受け取ってもらえたら幸いです。
さて、私からのリクエストにお答えいただきありがとうございます。「エロティックさを軽減させた女性の身体の見せ方」の返答として、あらゆる関係性を断ち切って「堂々とすること」を、そして逆にエロティックさは「他者との関係性によって演出される」というポイントを挙げていただきました。
「ヌードであることとエロティックであることはイコールではありません」というのは、私も常々感じていることです。少し話は脱線するかもしれませんが、昨年、初めてストリップショーを見る機会に恵まれました。踊り子さんたちによるパフォーマンスの力強さに圧倒され、演目によっては目を潤ませてしまうくらい心震える経験でした。ヌードが恥ずべきものではなく自分のものとして取り戻しているようにみえるパフォーマンスに、観ているこちらが清々しい気持ちになったのはいうまでもありません。男性によって価値づけられ続けてきた女性の身体の見せ方からどのようにずらしていくか、今のストリップショーにはそのようなものが賭けられているな気がしました。これは、昨今のラブドールの受容のされ方ともつながる部分かもしれません。
翻って考えてみると、女性たちは「堂々とすること」を教わらずに生きてきたような気もします。それは身近な環境にも由来するかもしれませんし、メディアのなかで堂々と振る舞う女性のイメージを見つけることが難しいからかもしれません。実花さんが挙げてくださったような彫刻もまた、美術作品として価値づけされているがゆえに美術館や展覧会などで展示されているわけですが、そうした価値づけが誰によって行われているかを常に意識していくことも必要だと強く感じました。
また、エロティックに見せる演出として関係性というのを挙げていただいたのは非常に興味深いです。
そこで思い浮かべたのは、写真家・苅部太郎が手掛けたラブドール(沙織さん)とユーザー(中島さん)との関係を第三者の視点から写した『Saori』シリーズです。第三者の視点からというとどこか覗き見的なものを感じさせますが、不思議とそんな様子を感じさせません。ではただの記録写真かというとそうでもなく、ラブドール単体で撮影されるものからは感じられにくい、沙織さんと中島さんの親密な関係を読み取ることができます。
特に気に入っているのが、中島さんが沙織さんの前髪を手で整えている写真と、沙織さんの手が写された写真です。個人的に「手」という部位に心惹かれることが多いのですが、例えば手が印象的な文学に、川端康成の『片腕』(初出は1963年)であったり、ヴィリエ・ド・リラダンの『未来のイヴ』(1886年)に登場する手の描写が挙げられます。これもまたどこかフェティシズムと結びつけられやすいですが、今回はそれとは少し異なる視点から手について考えてみたいと思います。

2017年に開催されたオリエント工業40周年記念展〈今と昔の愛人形〉にて筆者が撮影
「手」という部位には、関係性や感情を表象する機能を有しているのではないかと考えています。というのも、手は能動的であり、そして手の動きはとても雄弁であるように見えるからです。伊藤亜紗さんの著書『手の倫理』(2020年)において、接触には「さわる」と「ふれる」という二種類が存在し、前者は人や物に一方的に接触すること、後者は相互的な関係を生み出そうとすることだと述べています。ラブドールは物である、と言い切ってしまえば「さわる」になるかもしれませんが、ユーザーの多くは「ふれる」ことで関係を構築しているといえるでしょう。そして、ふれた手の動きによって関係性が表出しているように見える。実花さんの「あなたを離さない/I Won’t Let You Go」シリーズの《Untitled》も、手ではありませんが頬を接触させている(=ふれあっている)ことで親密さが表現されており、これまでの作品よりもドキッとした記憶があります。
関係性の表現という点から考えると、前回の記事で提示した①のメーカーにはそうした要素をあまり感じることができないかもしれません。一方、②の個人ユーザーによる写真では、ポージングよりも目線(=目の表現)によって関係性を捉えられている場合もあります。有名な話ではありますが、篠山紀信さんが「女子大生シリーズ」に応募してきた宮崎美子さんのスナップ写真をみて「信頼した相手にしか向けないような絶妙な表情を浮かべている」と評価したように、撮る-撮られる関係性にその写真の出来栄えが反映されるといえるでしょう。とくに目線が信頼関係を物語る要素として見ることができそうです。
実花さんが作品を制作するにあたって、モデルさんの目線は意識するものでしょうか。また、「あなたを離さない/I Won’t Let You Go」シリーズではモデルさんと一緒に写っているものが多いですが、このシリーズと他の作品とで目線をどのように変えているかなどありましたら、ぜひ教えてほしいです。