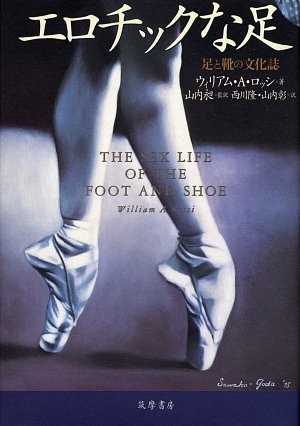返信ありがとうございます。この連載は「ラブドール」とタイトルに謳っていますが、回を追うごとに、人形やロボットを含めた女性の表象について身体を軸に考える視点が明確になってきた感覚があります。
人間そっくりのロボットがいる世界を描いた創作について整理していただき、ありがとうございます。欧米ではロボットは畏怖の対象になりやすいが、日本はロボットを愛でる視点が強いという特徴は、やはり宗教観にも関係がありそうです。おおもとは魂や人格、生命についての観念の差なのかもしれません。
ロボットものの創作物で「記憶」がテーマになるというのも非常に興味深いですね! 深く掘り下げたいところですが、話が脱線していくのが目に見えているので、別の機会に書きたいと思います。
前回の執筆後に、一つの仮説が自分の中で立ち現れてきました。エラストマー製のラブドールが「柔らかすぎる触感で違和感がある」ことと、ラブドール全般がポージングの際に想定される筋肉の形が連動しないことを前回で取り上げました。ここにラブドールの中には現実離れしたプロポーションの人形も存在していることを加えて考えると、「ラブドールは現実の女性に似ている必要はない」のだと思えてきます。
アニメーションや漫画、イラストなどの平面の創作物を例に考えてみましょう。人体の表現は作画によってデフォルメの度合いに違いがあります。劇画の場合は実際の人体に近いプロポーションで細かい筋肉まで描写するのに対して、カートゥーン調の場合は関節でさえ省略されることがあります。作画のテイストは、表現される内容がシリアスなのか、コメディなのか、主題は何かといった内容全般とのマッチングによって決定されるものです。
これを人形の造形に当てはめて考えると、ラブドールに何を求めるかによって、必要とされる造形が変わってくるように思いました。
私が「ラブドールは現実の女性に似ている必要はない」と考えた理由は、ラブドールに求められるものが、いわゆる「概念としての美少女」である場合が多いからだと推測したからです。
ラブドールを購入した人たちの理由は様々です。障害のある方、妻を亡くした方など、色々な方がいることは、オリエント工業の公式書籍『愛人形』(2017)からもわかります。中には、過去の恋愛に傷つき、人間との恋愛に嫌気がさして、人形に癒しを求める人もいます。

この場合、求められるラブドールは、害が無く、柔らかく、可愛く、癒されるものに性的な要素がくっついたものではないかと思うのです。そして性的な要素として、ヘテロセクシャル男性の性的対象である女性の形になったのではないか。さらに単に女性というだけではなく「若さ」が可愛らしさや害の無さと結びついて「美少女」となった。これはあくまで概念なので、現実の女性の若い頃とはあまり関係がありません。可愛らしく柔らかく安全で、でもぬいぐるみほどデフォルメがされていない、性欲を解消できる何かです。
現代美術では会田誠の《イデア》(2000)という映像作品がこの「美少女」をよく表しています。作品は、壁に大きく書かれた「美少女」という文字に向かって会田誠本人がマスターベーションをしているという内容です。実は「美少女」は表象は重要ではなく、概念があれば成立するのではないかと思えてきます。
まとめると、柔らかすぎるスライムのようなラブドールは「美少女型スライム」として存在する意義があるということになります。
ところが、この「ラブドールは現実の女性に似ている必要はない」という価値観をわかりにくくしているのが、私のような存在なのです。私はわざわざラブドールのメーカーにオーダーメイドで自分そっくりの人形を発注し、それと一緒にセルフポートレートを撮影しています。
ど直球に見ると、いわゆる「人形になりたい」願望のある女性のように見えると思います。しかし私にはこの願望がないので、推測するだけですが、おそらく女性の「人形になりたい」というのは、言い換えると「美しい姿で何もしないでいたい」ということではないでしょうか。これは「美少女」といっても他者から見た対象としての「美少女」ではなくて、あくまでも個人で完結するナルシシズムと結びついた現実逃避のように見えます。女性的なデカダンスとでもいうべき退廃的で耽美な思想です。
女優の西条美咲は人形に扮した写真集を何冊も出版しているのですが、雑誌『トーキングヘッズ NO.42』(2010)p.56のインタビューで、「時間の止まった世界で、高貴で、心も身体も一切の汚れのない永遠の少女としてとどまっていると、精神的にもさまざまなことに寛大になっていくのがわかるんです」と語っています。

私はこれとは逆に、あくまでもネタバレ込みでの展覧会を行います。つまり、人形と見分けがつきづらい表現はあくまで写真に撮った時にのみあらわれる表面的なイリュージョンであって、本質ではないというメッセージになるように展覧会を構成しています。インターネットだと、画像一枚だけが表示されて、私が展覧会で組んでいる構造とは別のメッセージを受け取る人もいるかもしれません。しかし、私はあくまでプロのアーティストとして展覧会を主軸にしているので、ネット画像ひとつで判断してほしくないというのが本音です。
私自身の作品制作では、人形と人間は見分けがつかなくなる瞬間があるのではないか、という写真ならではの錯覚を利用して、「人間と非人間の境界を問う」ことをしています。つまり、人形を人間に寄せていく方向で作っているのですが、今のロボット産業を見ていると、現実の産業として目指すべきはこの方向ではないように感じます。
ラブドールが「美少女型スライム」であるのと同じように、ロボットも現実の人間や動物を模倣しない方向性がメインになるだろうと思います。
ここからは、返信のパートに戻りたいと思います。
麻里恵さんがあげてくださったウジェーヌ・アジェには、ショーウィンドウのマネキンを撮影した写真がいくつもありますね。お書きいただいた通り、アジェは自らを写真家として見做しておらず、あくまで他者が創作に利用するための資料として撮影し、実際に街並みを記録した資料として写真をフランス政府に買い取ってもらうことで生計を立てていました。
しかし鑑賞者は、そこから美的な造形を読み取ることができます。マネキンを撮影した「人形写真」はやはり人形が人間的に見えるイリュージョンが起こっているのです。
写真家がはっきりと狙いを持って人形を撮影した最も初期の作例は1925年以降のバウハウスにあります。これらをアジェの作例と比較すると、バウハウスの作品群は明らかに人形のイリュージョン性を主題として入れているのに対して、アジェは人形を風景の中の一つの要素として写り込ませているという違いがあります。
写真は、撮り方次第で同じようなモチーフを扱っていても感じ方が変わってきます。平面表現の解像度が上がると、同じ作品を再び鑑賞したときに、そこに含まれたメッセージがだんだんと見えてきますね。
私が前回あげた《カピトリーノのヴィーナス》にまつわるエピソードをもう一つ書きたいと思います。
私が《カピトリーノのヴィーナス》(カッパヴィーナス)を知ったのは、美大受験のために通った美術受験予備校でデッサンのモチーフの石膏像として描いたからです。石膏像は、元のオリジナルの像から石膏で型を取って複製したもので、その多くが胸像です。元が全身像であっても、石膏像にするときに胸や腕を切って、台座をつけて、胸像として商品化されたのです。

予備校では、その像のバックグラウンドなどは全く知らされずに、目の前に見えているものを鉛筆で再現するための練習用のモチーフとして置かれます。
像によって難易度がそれぞれ違うのですが、カッパヴィーナスは比較的デッサン難易度が低めなので、初心者から中級者あたりに描くことが多いものです。石膏像のカッパヴィーナスは胸像で、胸下と二の腕に切り口があります。腕はついていないので、もとが恥じらいポーズだったことはわからないのです。私は、全く知識がないままデッサンをしながら「なんだか頼りなさそうな表情をしている」と思っていました。
一方で、他の有名な女性像に、ミロのヴィーナスがあります。ミロのヴィーナスは、頭部から鎖骨付近までの首像と、腰に切り口がある半身像(トルソー)の二種類があります。
正直、頭部だけの首像を見ると、それほど魅力的とは思えず、「同じヴィーナス像でもカッパちゃんの方が顔立ちがかわいい」と思っていました。ミロのヴィーナスはすました表情で、捉えどころがないのです。

ところが、ミロのヴィーナスの半身像と対面すると、堂々として力強く、非常に美しいのです。ミロのヴィーナスは現存する像自体の腕が失われているので、当初どのようなポーズだったのか知る由はありません。しかし、カッパヴィーナスのような恥じらいポーズではないように見えます。肩の動きから左腕を上げていると予測できること以上に、造形の力強さ(実は腹筋が表現されている)、体の厚み、表情などが、自分の身体を恥じらって隠そうとしているようには見えないのです。

ただし、ミロのヴィーナス半身像はデッサンの難易度が高いので、かなりハイレベルな専攻を受験する多浪生くらいしか、描く機会がありません。
石膏像は平面絵画の造形言語を学習するための教材ですが、これらを描くことによって暗黙のうちに価値観をインストールしているのです。元の彫刻の作者が何を表そうとしたのか。それを良しとして作品を残してきたのはどんな人たちか。私たちはそれを学んで何を身につけているのか。学校だけでなく、美術館もそうですが、どのような表象が良しとされてきたのかを、俯瞰して見ていく必要がありますね。
その上で、価値観をひっくり返すために、既存のフォーマットを流用することがあると思います。
私はストリップショーを見たことがないので、麻里恵さんのご感想は非常に興味深いです。「堂々とする」ということは、「自分の身体は自分のものだ」と表明することだと言い換えられるのかもしれませんね。
例えば身体が目的に沿って使用される写真の例として、ポルノグラフィーやグラビア写真があります。女性が被写体で、ヌードもしくは、水着や下着などのコスチュームを身につけていて、多少なりとも性的な欲望を喚起させるためのものです。
この場合、女性の身体は目的に沿って被写体として使用されます。評価の軸は、他者から見てエロティックに見えるかどうかです。なので、それ以外の個性や面白みを出す工夫は副次的なものとなります。
被写体の女性がエロティックな表現をしたい場合、他者に影響を与えたいという願望があると想像できます。自分に、他者に性的な欲望を喚起させる力があることを確認したいのではないでしょうか。表現者というのは、ほとんど無意識かもしれませんが、自分に力があることを誇示したいものです。その中でもエロいというのはわかりやすい指標です(もちろん不特定多数から性的に見られたくないという欲求を同時に落ち合わせることも自然なことです)。
この場合、双方の目的が合致していて健全です。もしそうでない場合は、後から苦しむことになります。撮影者や企画者との権力に差があり、被写体としてどのように撮られるかをコントロールすることができない状況に陥り、意に沿わない撮影を断れないような場合には、後からトラブルになることがあります。
人形が被写体の場合、人形には自我も意思もないので、後から「あれは自分の望んだ表現ではなかった」という告発は起こりません。人形写真は人形遊びだから、ラブドールを撮影した写真というのは、撮影者が人形をどのように捉え、何を見出しているかだけが現れるのです。
その観点から行くと、苅部太郎の《沙織》(2016-2020)は、ユーザーの中島さんとラブドールの沙織さんの関係性をとらえた写真でありつつ、中島さんが沙織さんをどう思っているかを取材した作品なのだと思います。
ラブドールの「手」に関して、実際に所有してポージングしている経験から言うと、ラブドールは自分の手で顔に触れることが非常に難しいです。人間よりも体が硬くて関節の可動域が狭いため、腕を上げられないうえ、肘が90度よりも曲がらないのです。エラストマー製の方が可動域が大きいものが多いですが、最近はシリコン製でも可動域の狭さが改善されつつあります。しかし、人間を基準にするとどちらもポージングの制約が多いです。
《Untitled》では、せっかく人間である私が画面内にいるので、触れる表現も試みています。

2020年に撮影して、これまでの東京や横浜での展覧会ではシリーズの一部を展示していました。先日、台北で初めてこのシリーズをフルセットで展示したのですが、そのときに作っていただいたPVが、まさに「ふれる」ことをメインにしています。
やっと、最後のご質問の「目線」の話題に入ることができます。私の場合、明確に人形が「見ている」ように見える写真を意識的に制作しています。実は、シリーズの中では《#selfiewithme》というスマートフォンの自撮りアプリで撮影しているものが最もその要素が強いものです。

この作品は、自撮り棒を使って、スマートフォンのインカメラで撮影しています。シャッターを切る基準は、スマートフォンの画面内に映る人形が、何か意思を持って一緒に楽しんで撮影をしてくれている表情になった時なのです。
その瞬間がいつなのか、具体的に説明すると、やはり目線ということになります。一言で言えば、画面越しに目が合ったらシャッターチャンスです。実際には人形には意思も自我もなく、何かを見ることはありません。でも、このときは確かに一緒に自撮りを楽しんでいるように思えるのです。
私の型取りで作っていただいたオーダーメイドヘッドはかなり真顔に近く、口角だけ若干上がっています。それでも、目が合うことによって「楽しい」という感情を読み取ってしまうのです。目線を遠くに向けているときにはツンとした印象になるので、不思議です。
ラブドールの顔立ちについて、麻里恵さんが感じ取っていることはありますか? 私は今回の前半に書いたように、「美少女」的な造形が多いように思っていますが、まだ他の観点もありそうです。麻里恵さんのリサーチもお聞きしたいです。