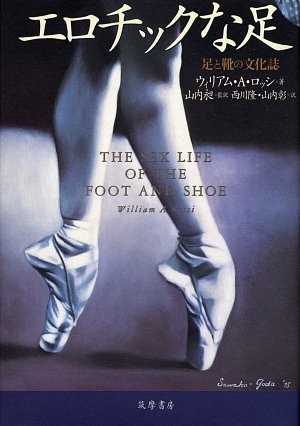ご返信ありがとうございます。人形論は面白くて、現実の人形をひと息で飛び越えてフィクションの人造人間に言及します。それが可能なのは、ひとえに人間の持つイマジネーションの力なのだと思います。
私たちが関心を持っている人形やロボットについて、哲学研究者・思想評論家の金森修は『人形論』(2012)の中で「亜人」という語で表しています。亜人は人間未満とも言い換えられます。その中で金森は、人間が人間らしく生きていける圏外に置かれた時に、人間と見做されなくなり、「人間の亜人化」が起こることを指摘しています。
ロボットがフィクションで扱われる際、物語の効果として、人間に対する差別や迫害の比喩として使われることがありますが、それは人形がこの「亜人」という要素を持ち合わせているからでしょう。
作り手は、現実世界で直面する困難を一度概念化し、フィクションとして創作します。鑑賞者はその創作物を受容することで、現実に向き合うことができるのです。抽象化されていることで、時代や地域を超えて鑑賞可能な作品になります。この効果は、私が創作活動を行う上で念頭に置いていることです。
そしてこれは、あくまでもフィクション上の話です。

私が前回書いた「ラブドールは人間に似ている必要はない」という主張、そして「女性の形をしている人形は女性だと言えるのか?」という問いは、実は評論家・澁澤龍彦のエッセイ「黒いダイヤモンドのごとく…」(『西欧芸術論集成下』pp.26-27)を思い出して考えていたことでもあります。
澁澤は『ホフマン物語』のオランピアやデューラー派による木製の人形、ベルメールの少女人形をあげ、「呪われたナルシストの光学においては、少女は妖精であり、妖精は天使であり、天使は人形であり、人形は少女なのであって、人間そのものの姿はついに見えないのである。」と書いています。
澁澤龍彦は女性的なものをエロティックな客体として捉える視点が強い評者だと思いますが、概念としての美少女性は、人間とは結びつかないとする方向性でしょう。

そして以下は、私の行動と考えですが、私は人形を「擬人化」=「人間扱い」しません。
つまり、人間と同じ食卓を囲んで「お腹が空いているよね?」と声をかけるようなロールプレイングはしません。
その代わり、人形に負荷がかからないように気をつけます。素材が劣化しずらい体勢を維持し、素材に適切な気温や湿度などの環境を整えることを心がけています。人形が快適な環境と人間が快適な環境は違うからです。
人形の身体は、大まかな形こそ似せられていますが、やはり骨も筋肉も臓器もないのです。代謝もエイジングもありません。人間の生とは全く違うわけです。自分の実感として、自分の型取りで作った人形を、女性として同じだとは思えませんでした。人形の体型を形作るのは横長の骨盤でもなければ皮下脂肪でもなく、ホルモンも出なければ月経もないのです。水っぽい血の通った身体からはとても遠いです。
もちろん、表現の側から見れば「ジェンダーマーカー」は理にかなっているのだと思います。表現がステレオタイプを形づくり、それに世論が左右されていくと、現実の女性にも影響します。
しかし、人形と人間を重ね合わせて同一視し、その観念が人間の側のロールに影響していくということは、私の実感からはとても遠いです。
これは人形が身近にあるから思うことなのでしょうか。

《Untitled16》は、典型的な意味を示すポーズではない方向で、関係性を表現できないかを探ってみた作品です。鑑賞体験としては一瞬だけ一人の人が体を折り曲げているように見えるが、すぐに違うと気がつく程度の違和感を持たせることを考えました。
女性同士の仕草の分析がないというのは、たしかにそうかもしれません。
実は没にした作品で、もっとベタベタ触れ合っているものがありましたが、レズビアン的な性愛に見えるので却下しました。後に展覧会タイトルにも採用したのですが、作品のテーマでもあるシスターフッドからは離れていくので、今回はそぐわないと判断したからです。
また、女性三人がパーティーをしている場面を設定した《Happy Dinner Party》を作って実感したのは、シチュエーションによって同じようなポーズや触れ合いでも示される意味がかなり左右されるということです。三人の女性の場合は、ポーズの分析はどのようになるのでしょうね?
これも、互いに手が触れ合っているシーンを撮影しましたが、最終的には展示しませんでした。やはり性愛のニュアンスが強くなりすぎると感じたからです。
ポーズのコードも文化的なものなので、時代と地域が変わると意味合いが異なる場合もあり難しいものです。手を繋ぐのは友情の表現としてあると思いますが、このシチュエーションの成人女性同士になると違和感を感じました。でもこれも、2024年の日本では、という限定的なものかもしれません。今後どうなるかはわからないし、他の文化圏でどうなのかわからないからです。

「人間ラブドール製造所」の撮影体験の特徴は、人間が人形を演じることにあります。前回紹介した、西条美咲が人形に扮して写真を撮ったのと同じようなシチュエーションでの撮影が行えるサービスと言えます。
もちろん出来上がった写真はよく演出されているのですが、「人間ラブドール製造所」の方は、写真という結果よりも、人形になりきる体験の方が遥かに充実しているように見えるのが面白いです。
もしこれが「あなたを美しく撮ります」というサービスだったら、ここまでの体験にはならないのではないか、と予想します。
特に現代の日本では、自分自身をそのまま肯定するのが難しいように思います。ラブドールという、「美しく愛される人形を演じる」というクッションがあることで、客体としての人形=自分を受け入れることができて、満足感を得るのではないかと思います。
プロモーションビデオを見ると、モデルは人形に扮した後、カメラマンによって身体を触って動かされることでポーズを変更される、というアクションがあります。通常のファッションモデルの撮影の場合でも、髪や服をアシスタントが直すことはありますが、体を触ってポーズを変えることは珍しいでしょう。やさしく触れられるという行為も、大切にされ愛されているという実感として重要なのかもしれません(夢を壊すようで申し訳ないですが、実際にはラブドールはかなり硬いので、座っている体勢のまま腰の角度を変える時は、プロレス技をかけるような感じで羽交い締めにしてポージングの軸を作ります。かなりの重労働なので、優しく触れるだけでポーズが変更できたら、どれだけありがたいことか……)。
また、これは私自身のことになりますが、そもそも私は写真に撮られることが嫌いです。なので、子供の時の写真はほとんど残っていません。自分がアーティストとして作品制作をしていく中で、2017年ごろに「自分の顔を型取りして作った人形と一緒にセルフポートレートを撮る」というプロットが浮上してきたので、相当悩みました。「これはかなり面白い作品になりそうだ。でももし人形を発注してセルフポートレートを試みたとして、自分の姿が嫌すぎて一枚も作品として発表できないかもしれない」と自問自答したのです。
しかし、誰か別の人にお願いしてモデルになってもらうお金がありませんでした。自分がモデルとカメラマンを兼任すれば制作できるけれど、それ以外では実現不可能だったのです。私がこの制作を実行しようという最後の一押しは、「どんな人がモデルであったとしても、撮り方次第でどんなふうにも見せられる。腕の見せ所は仕上げにかかっているのだから、プロとして腹を括れ!」というプライドでした。
実際に、オリエント工業の造形師さんが私の頭部を解釈して造形してくださった人形が届くと、「こんなふうにコンプレックスを良い方向に捉えてくれたんだ」と感動したのです。だから、自分の姿を人形に寄せていけば、何も不安なく撮影ができました。作品として発表できるクオリティかどうかの判断は、私が人形に似ているかを判断すれば良かったのです。そしていつの間にか写真に撮られること自体が嫌いではなくなっていました。
素晴らしい人形を作るプロフェッショナルによる造形を基準にすれば、自分自身の姿はその価値観の範疇に収まるので、余計なノイズを引き起こさないという安心感はとても大きかったです。
「未来の人間の外見はどんどん人工的になっていく」ということも作品コンセプトの中に入れていたので、それを体現できているかどうか客観的に判断したかったという要素もありました。

麻里恵さん自身の実践から書いていただいた「目線が合わないと人形のように見え、セルフィーで目線が感じられるようになると急に人間らしくなる」という実感は、まさに私が人形を撮影するときにひしひしと感じることです。
目線の設定がうまくいかなかった写真は、やはりそのように鑑賞者から指摘されることがあります。目線は人形写真において、クオリティに直結する部分です。人は目線から生命感を読み取っていることに間違いなさそうです。
もちろん頑張って目線を設定している作品がほとんどなのですが、想像させる方が人間的に感じられるのではないか、と思ったので、《Happy Dinner Party 52》はあえてトリミングで目を写さないようにしています。
ちなみに、私の型取りで作った頭部と私が横に並んで撮影すると、顎から頭頂部までが全く同じ大きさに写っている場合でも、虹彩のサイズは人形のほうが一回り大きいです。
人間の虹彩の大きさはだいたい11mmと言われています。これは子供から老人までほとんど同じだそうです。骨が成長する前から眼球のサイズは成人と同じくらいの大きさなので、子供の目は大きいというわけです。
人形には、11mmよりも大きな虹彩のアクリルアイが嵌め込まれているので、サイズに違いが出るのだと思います。この差を解消するには着色径が11mmよりも大きいカラーコンタクトを装着すれば良いわけです。一般的にカラコンを入れると眼球そのものが大きいように錯覚させることができるので、相対的に顔が小さく見えたり、子供のような顔立ちに感じられて若く可愛らしく見える効果があります。
つまり人形の裸眼は最初からカラコンサイズなので、麻里恵さんのご指摘の通り、人形の顔立ちを可愛らしく演出しているのは目元によって構成されると言って良いでしょう。
ご質問のボディの選定についてお答えしましょう。実はこの作品の場合、それほど重要ではありませんでした。なぜなら、体型が隠れる服装にすることを先に決めていたからです。
年末年始の女子会で、お酒なし、愚痴も言い合える友人同士の関係性だとしたら、ボディラインを強調する服は着なさそう。たぶん洗濯機で洗えて、部屋着よりはちょっと素敵な要素があって、でも別に高級じゃない服を着ているはず……なので、ほぼ私の私物の服を選びました。これらの服が着られるボディならば、特にこだわりがなかったのです。
オリエント工業のボディを使用しましたが、2体が「やすらぎ」、一体が「アンジェ」でした。
本当は背が高かったりふくよかだったり、さまざまな体型の人がいるともっとリアリティがでたのかもしれませんが、どちらも重量の問題で、私一人で動かすことができないため、断念しました。
逆に、過去のマタニティフォトの作品《The Future Mother》の場合は、かなりこだわりました。リアリティと人形らしさのバランスが重要だったので、あまりにも人間離れしたプロポーションのものは選ばないと決めていました。体型がはっきり映るものに関しては、やはりコンセプトに合う精度が必要ですね。
さまざまなラブドールを見ていると、髪型はロングヘアが多いように思います。人間ラブドールは、「典型的なラブドール」というステレオタイプを援用した表現ですが、そちらもやはりロングヘアが多いです。
これらは何の影響なのだろう?と気になりました。なにかリサーチなどありましたら教えてください。