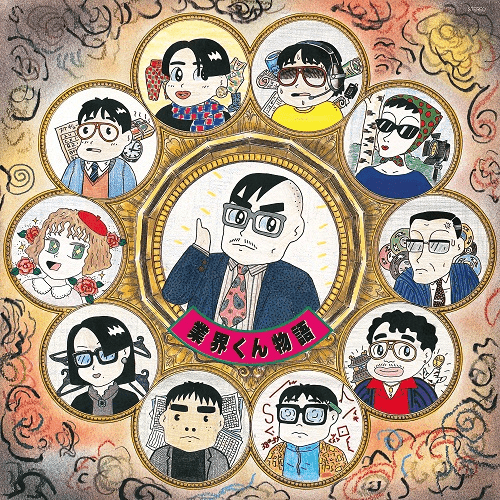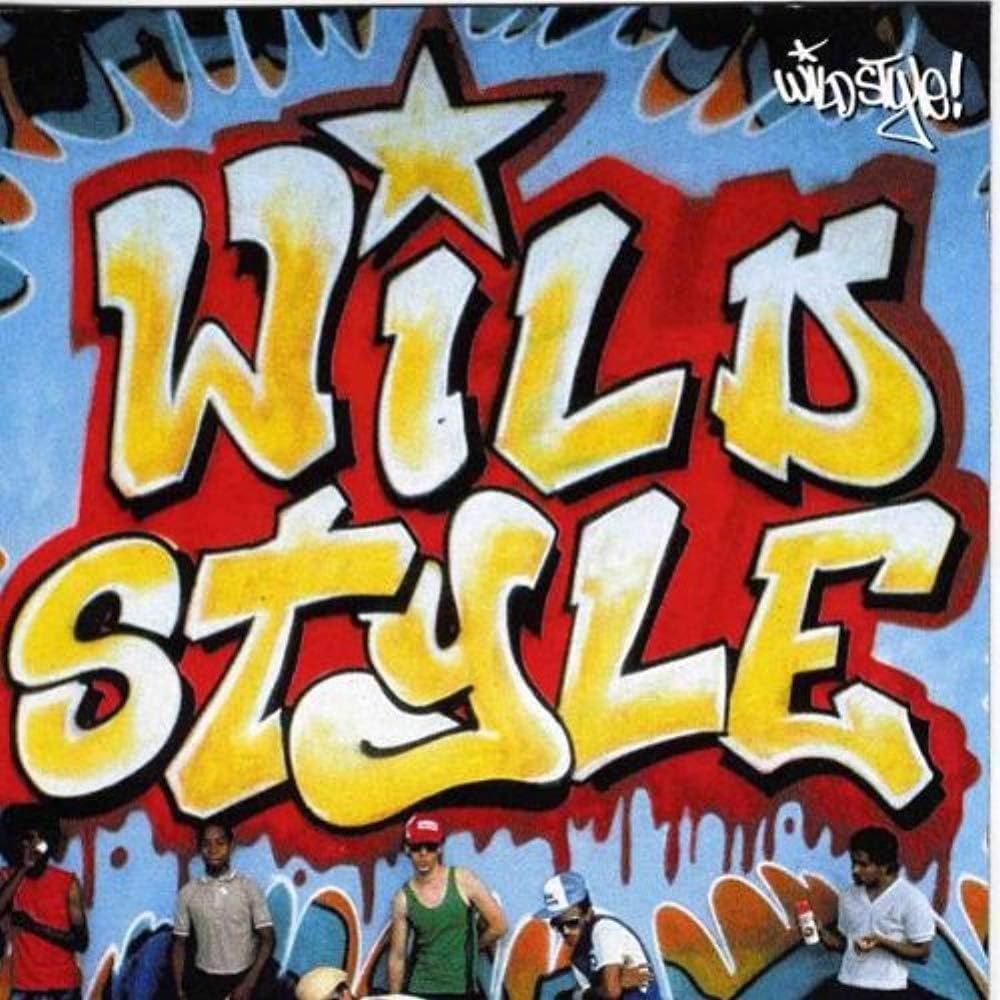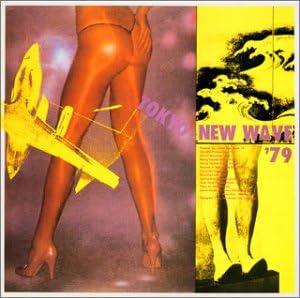自明のこの事実を少しでも頭から追い出したいからこそ私たちは音楽を聴いているともいえるが、ポップ音楽をひとつのアート作品として価値判断しようとする“聴く”という行為は、文化や政治が居留守の空間において私たちの見知らぬ何者かによって仕掛けられるのではなく、それらの要素がフルに稼働する私(あなた)もメンバーである空間=社会の裡においてこそ、言うまでもなく、可能となる。
ある曲を聴くときに私たちそれぞれの耳に流れ込んでくる様々な音の要素とその組み合わせ、例えば、電気仕掛けのギターの歪み、1990年代の希少な南部産ラップの叫びのサンプリング、また愛についてのセリフまでのすべてとその絡み合いを私たちの聞く能力がどう拾いあげて味わうのか、そこに顕れる音の特徴をどう他から区別してどう娯しむかは、現実の聞き手それぞれに任されている。
音楽を聴く――知覚することにもし限界があるとするなら、それは社会の裡において形成され獲得されてきた具体的な一人の人間のストリートでの経験から“教養の体系”までひっくるめて設定せざるをえない。同時にその限界がいかにあるのかは聞き手たる彼/彼女/その他を、階級やジェンダー、収入、学歴などの要素が絡み合う現実の社会の現実の場所の裡に位置づけることを可能にする。
1人の人間、個人、もしくは“個”と書くことにより良かれと抽象化したつもりになっても、私たちそれぞれは実際にはいつも具体的な、政治的な条件の裡にしか存在することはできない。その世代の生んだ代表的なアーティストの一人とされる山下達郎によると、音楽の記録に利用されるテクノロジーの発達と“政治の季節”が生んだドロップアウトたちが職業的作曲家たちの代わりに音楽の世界に入り込んでいったことなどが1968年以降の日本の新しいポップ音楽シーンを設えたという。ポップ音楽はアートの内と外に働きかけた新しい言語だった。
以前も触れたように、新しいポップ音楽自体の価値をこの時代のカルチャー/アートの配置の体系に位置づけたのもまた、山下のようなアーティストとECDのような彼らが作る音楽の聞き手、その双方の中間にあった渋谷陽一たちの『ロッキング・オン』や(当時はニュー)『ミュージック・マガジン』その他ジャーナリズム/メディア自身だった。そもそもこの新しいロックと呼ばれる音楽を、そもそも労働者階級の手慰みからアート作品だと騒ぎたて評価していき、売り上げとは別に“芸術的に”腑分けし始めたのもまた彼ら自身だ。
明治維新、韓国併合、その後の世界の歴史に日本が足を踏み入れ複雑な相互関係のなかに存在感を増していった1932年を経て、二つの世界規模の戦争が終わった1945年8月15日以降のアメリカ/ヨーロッパ/アジアとの関係の空間と時間において“ロック”は起きて、その形式と内容には見紛うことなきその時代の署名がある。最後まで止まることのできなかったナショナリズムと植民地主義の日本にとっての敗戦という結果がテクノロジー/マス・メディアとともに文化的国境を無効化していった時代――冷戦下“戦後民主主義”が信じられた期間――その束の間の幾つかの新しいアートの一種としてロックは作り出され、1960年生まれのECDがその時代の申し子であること言うまでもない。ロックはそこに参加した彼らが作った。ポピュラー音楽研究のサイモン・フリスは、当時のブリティッシュ・ポップ/ロックとその産業丸ごとを変えた若者の間に芽生えた考えについて詳細に記した著書『サウンドの力』で次のように記している。
芸術家としてのロック・スターという考えは少しずつ広まっていった。イギリスでその最初のきっかけとなったのは、一九六五年、エリック・クラプトンが「バンドがコマーシャルになったから」という理由でヤードバーズを脱退したことだ(中略)。ロックンロールのイデオロギーの変化に関して(中略)もっと重要なのは、ボブ・ディランの商業的成功で力をえたアメリカのフォークの議論だった 。[1]
フリスによると「フォークのミュージシャンは圧倒的に教育の高い中産階級だが、自分たちの活動を詩人、小説家、画家のようなほかのブルジョワ芸術家と同じものだと考え」、「音楽はしたがって自己表現、社会へのコメントと定義され、人気よりも真実が重要とされた」。また「フォークの演奏家はマスの音楽生産のしきたりを伝統的に、またラジカルに拒絶する姿勢を保っていた」。フリスによると、例えば、ジョン・レノンは当時をこう回想したという。
ぼくは自分の感情について考えはじめていた。一体いつからそうなったのかはわからない。「アイム・ア・ルーザー」「悲しみをぶっとばせ」のような歌の事だけど。自分をある状況に投影するのではなく、本でやったように自分自身について感じたことをただ表現したい、そうしてみようと思った。ディランがそう気づかせてくれたんだと思う。(中略)それから客観的にでなく主観的に歌を書いて、本当の自分になり始めたんだと思う 。[2]
そうして気がつくと「1960年代の終わりには、大西洋のどちら側のミュージシャンも芸術形態としてのロックと娯楽としてのロックを区別していた。ロックは複雑な音楽形態だった」。
フランクフルト学派の哲学者/音楽学者のテオドール・W・アドルノがウィーンでボロクソにくさし、より若き異能の作家ボリス・ヴィアンが同時期のパリで夢中になったジャズを筆頭に、1940年代のヨーロッパの大衆音楽の嗜好は既に十分にアメリカ化されていた。そのうえで1950年代、アメリカ西海岸の白人の10代の少年・少女がブラック・ダンス・ミュージック=R&Bや初期のロックンロールに夢中になっていたことに業界人が気がつくことが発端となるその産業化は、人種主義と切り離せないまま生まれてきた合衆国建国の構造を孕むこの極めてアメリカ的な現象を、日本やヨーロッパへ、アフリカやアジアへも離散させ、地球を丸ごと覆うように拡げていった。
あまりにも20世紀的/アメリカ的である映画という形式を選んだヴィム・ヴェンダースのいうところの“文化的な植民地主義”といえるほどの波及の強さをもって、とりわけロックン・ロールは異人種が混ざっていかざるをえない文脈の空間を作りだすのだから、それぞれの場のアートにもポリティクスとも曖昧に融合していくことは誰にも止めることはできない。アメリカやヨーロッパの少女たちは40年代に既にシナトラのステージを経験して失神騒ぎ(!)を起こしていたが、既にリヴァプールの白人かつ労働者階級を中心に結成されたビートルズはシナトラと比較するとより“黒く”“性的”といえるダンス・ミュージックをもって路地裏の小さなクラブから出発し、数年後の1965年にはニューヨークの野球場でのコンサートを満杯にしていた。1966年の彼らの武道館コンサートについてティーンのオーディエンスへ共感した日本の戦後のルポ・ライターの巨人、竹中労はポリティクスの視点から評価したが、アートとしてロックをどう迎えるべきかの歴史的な知識は彼にあっただろうか? そもそも、ポップ音楽を楽しむのに知識はいるべきなのか。もしそうなら、それはどのような知識なのだろうか?
アートの定義の階級的な引き下げを仕掛けたプロテスト・フォークから引き抜かれたアイデアの遺伝子をもっての、グローバルに新しい言語としてのロックの登場と発展の影響は、私たちが知るようにその後巨大に膨張していくポップ音楽産業とともに形を変えながら生きながらえていく。日本のポップ音楽産業のソフトの売り上げの最盛期は1998年で、その売上は6075億円である。音楽フェスは2000年代にまずなによりも“ロック・フェスティヴァル”として始まり定着していった。音楽をなによりも欲望したECDの生きた――彼は98年に38歳であり、翌年にメジャー最後のアルバム『MELTING POT』をリリースしている――時代とぴったり重なり合う。

ECD, “MELTING POT”1999
受験が近づき机に向かう時間が増えたせいもあってラジオで音楽を聞く時間は増えることはあっても減ることはなかったのだ。カーペンターズが次々とヒットを飛ばし、元ビートルズの四人がそろってチャートを賑わす、さらにザ・スウィートやスレイド、ジョーディー、そしてスージー・クアトロといった若い英国勢も活躍していたこの頃のラジオは理屈抜きに楽しかった。マイク・オールドフィールドの「チューブラーベルズ」の大ヒットも忘れられない。ロバータ・フラックやスリー・ディグリーズとMFSB、ダイアナ・ロス、ジャクソン5、スタイリスティックスなど、その頃チャート・インする機会が増えつつあった黒人アーティストたちの曲にも僕は自然に親しんでいた。中でもスティーヴィー・ワンダーの「悪夢」とクール&ザ・ギャングの「ファンキー・スタッフ」はラジオでかかるのが楽しみだった。[3]
スティーヴィー・ワンダー「悪夢」(YouTubeより)
クール & ザ・ギャング「ファンキー・スタッフ」(YouTubeより)
「毎週登場する黒人アーティストについてほとんど無知だったけれど、番組の雰囲気が好きで毎週欠かさず」少年のECDが観ていた週末の深夜のテレビ番組『ソウル・トレイン』の枠で、「デビッド・ボウイのTVショウ『1980フロア・ショウ』が放映されたことがあった」[4]。
僕は今でもこの『1980フロア・ショー』こそデビッド・ボウイが発表したどのアルバムをもしのぐ最高傑作ではないかと思っている。TVに貼り付くように見入っていた僕の横から画面をのぞき込み、丁度アップになったデビッド・ボウイの顔を見た父が「何だ、このバケモノ」と言ったことも忘れられない。その時、僕は父に対して「ザマアミロ」と言ってやりたかった。自分が愛するものが親には理解されない。僕はそれでかまわないと思ったし、むしろ、「理解されない」ということこそ守ろうとした。それは今に至るまで変わらない。[5]
スパークスを初めて聞いたのも七四年のことだった。イギリスでブレイクするきっかけとなったアルバム『キモノ・マイ・ハウス』をいち早く紹介したのはやはりロッキング・オンだった。「両性具有」、「粘膜」そんな言葉を使ってラッセル・メイルの歌声を絶賛する岩谷宏のスパークス論を読んで、僕は迷わず『キモノ・マイ・ハウス』を購入した。ラッセル・メイルの声を聞いて僕は新しい人類の声というものがあるとしたらこんな声なんじゃないか、と思った 。[6]
1980 Floor Show(YouTubeより)
家族と住んでいた車庫の跡地の六畳一間の家が「10歳までの記憶はまるで人間のそれとは思えないものだった。その家の板一枚の薄い壁は、外の音を遮断することがなかった。まるで路上で暮らしているようだった」[7]と短編「中野区中野1-64-2」で思い出すECDは、その生家の近所で外国人のように見える少女との出会ったと続ける。
僕の家の前の通りを右側に行った突き当たりにとてつもなく大きな邸宅があった。なにしろその屋敷の門は学校の校門と同じくらい立派なものだった。(中略)その先は芝生でおおわれた小高い丘が視界を遮っていた。おまけに芝生の上にはミロのヴィーナスの像のレプリカがこちらを向いて立っていた。[8]
好奇心から「太いブナの木や椎の木で鬱蒼としている」「邸宅の敷地の一番外側」から侵入して邸宅に近づいていった彼は住人の老婆に見つかり、しかし叱責されずに苺のショートケーキをもらってキャシーと呼ばれる少女に紹介される。
声に応えて現れたのは同じ歳くらいの女の子だった。髪は栗色でゆるくウェーヴがかかっている。眼は青くないけれどずいぶんと薄い茶色だ。白いワンピースを着ていた。[9]
2人は打ち解け「外人の女の子と友達だということは自分が特別な存在になったようで得意だったが、他の誰にも彼女のことはしゃべら」ず、この付き合いはその後数回で慌ただしい毎日のどこかへすぐに忘れられていく。
彼女が外人である、ということよりも、同じ歳ぐらいのはずの彼女を何故、自分が通う小学校で見たことがないのか、そっちの方が不思議だった。
私立の小学校とかアメリカン・スクールとか、そういった自分が通う公立の小学校以外の学校の存在を僕は知らなかった。だから、それまで、彼女を僕が見たことがなかったのは、何かの理由でこの屋敷に閉じ込められているのだ、とそう早合点した。[10]
僕は三七歳になるまで童貞だった。初めて見たのがキャシーの股間だったら僕の人生は全く違ったものになっていたかも知れない。[11]
このセンテンスの正確な意味は不明でも性がのしかかってくる重荷だということは伝わってくるので、性が強迫的になる前の忘れられない異性との遭遇は、裕福でない家に生まれ育った少年の「ヰタ・セクスアリス」のようでもあり、村上春樹の小説のような不思議な始まりを持ちながら、ドラマは展開されず、ただECDとキャシーとの間の距離が強調された挙句、ブツッと終わる。いかにもECDらしいが、その距離に、ロックンロールが、深く決定的に貫通するのは偶然ではない。
アメリカ的自由主義の“あるべき姿”としての逞しく麗しい男女のイメージを世界に向けて映し出していた映画にも、異なった性と人種は、少し思い出すだけでも、例えば、1959年のジョン・カサヴェテスの『アメリカの影』にそのストリートで重なり合う姿を見せていたし、1971年にはメルヴィン・ピープルズの『スウィート・スウィート・バック』が元主人と元奴隷が共に生きる空間の勧善懲悪をひっくり返して見せて、1973年にはウィリアム・フリードキンの『真夜中のパーティ』がエスタブリッシュメント側に紛れ込んだ際で逡巡する性的な“他者”たちの姿を取り上げていた。アメリカ映画自体の何かが、多分、その前提の制度が変わってきていた。
しかし映画とまったく異なったメディアである、ECDの名前の挙げたデヴィッド・ボウイ、スパークス、もしくは多くのロック/ポップ・アーティストたちのサウンドも、特にまだ未経験なことが多い人間にとって心と体からどうしても追い払えない熱病のように差し迫った、プライヴェートでパーソナルな問題に直接触れながら、部屋の内部にある小さなガジェット=ラジオテレビやレコードプレイヤーからそれぞれの聞き手へと達していく。聞き手にもたらされるこの体験は、フリスによるなら“エロティシズム”と切り離せない。
歌うことは身体的な快楽であり、だれかが歌うのを聞いて楽しいのは、それが何かほかのものを表現しているからでも、声がその背後にある「個人」を表象しているからでもなく、サウンドそれ自体が直接的に肉感的なアピールを持っているからなのだ。(中略)私たちはロック・サウンドの物質性に反応し、ロックの体験は本質的にエロティックなのだ。言語による自己の確認(常にコントロールされているブルジョワ美学のありかた)ではなく、悦楽に自己が溶解していることに関係する[12]
聞き手の耳元で剥き出しになったエロティシズムは、公けとなった革命の瓦解のあとに顕れたサブカルチャーへと言葉による終わらない解釈に曝されながら収容される。そのありようが当時のロックの意味となる。
[1] サイモン・フリス『サウンドの力』細川周平・竹田賢一訳、晶文社、1991年p. 93。
[2] 同前、p. 94。
[3] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p. 44。
[4] 同前。
[5] 同前、p. 45。
[6] 同前、p .40。
[7] ECD「中野区中野1-64-2」『失点イン・ザ・パーク』太田出版、2005年、p. 150。
[8] 同前、p.1 53。
[9] 同前、p. 164。
[10] 同前。
[11] 同前、p. 168。
[12] フリス『サウンドの力』、p. 199。