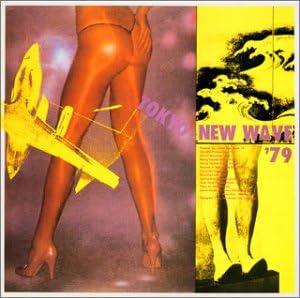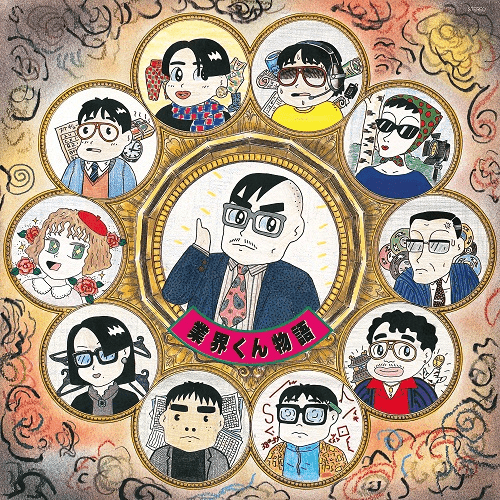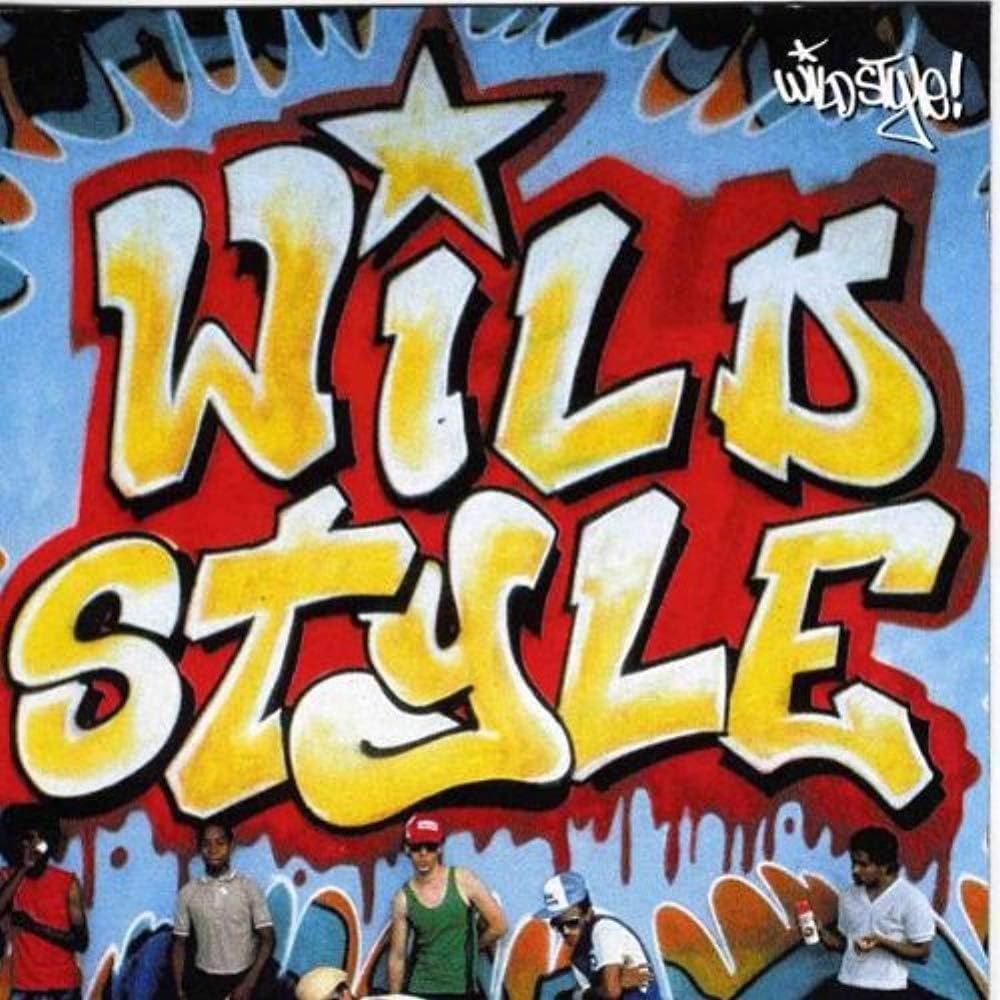吉祥寺のあったレコード店「ジョージア」の後藤美孝はインディ・レーベル「PASS レコード」を設立し、東京ロッカーズと自分たち自身を呼んでいた幾つかの東京のパンク・バンドの集合体のなかからフリクション、その流れにあるBOYS BOYS、また埼玉の突然段ボール、横浜のグンジョーガクレヨン、大阪のPHEWなどの音源をリリースした。フリクションとPHEWはそれぞれプロデューサーをやってのけた故・坂本龍一の優れた采配による音像が残されている。
「ジョージア」以外、吉祥寺には「伊勢丹の南向かいのショッピング・ビルにもマニアックな輸入盤専門店があった」[1]。その街のもう一方の側に山崎春美『天國のをりものが』によるなら「さて、佐藤隆史という一人の男、これがどういう風の吹き回しか、コンテンポラリー・ジャズ喫茶を開店するのである」[2]
吉祥寺マイナーが開店したのは七八年のことだが、僕が初めて行ったのは七九年になってからのことだと思う。マイナーがあった吉祥寺北口の東側というのは、今でもそうだが、当時からいわゆるピンク街で、洒落た喫茶店が多かった西側とは対照的なエリアだった。マイナーで初めて見たのはおそらく自殺のライブだと思う。マイナーにステージはなかった。客の頭と頭の間からやっと、ヴォーカルの川上浄ののっぺりした白い顔を見ることができたのだから、客はそれなりに入っていたのだろう。イギー・ポップを拡大解釈してネジ曲がってしまったような川上浄のパフォーマンスはゾッとするほど気味が悪かった。それは子供の頃にテレビで恐れた『四谷怪談』のお岩さんのような暗い情念さえ感じさせた。その片鱗はオムニバス盤『東京ニューウェイヴ』に収録された二曲からもうかがえる。[3]
ECDは吉祥寺マイナーで光束夜、工藤冬里、SYZE、自殺、白石民夫、灰野敬二といった人々の演奏を聴いていただけでなく「店内の黒い壁面にディスプレイされた自販機本『 JAM』『 X-マガジン』の表紙。著名な山口百恵のゴミ袋漁りの記事が載った『JAM』を買ったのはマイナーでのことだった」[4]、「『 JAM』は僕にとっての七〇年の『少年マガジン』、七三年の『ロッキング・オン』以来のエポック・メイキングな雑誌だった」[5]という。
僕はその時点で手に入る『X-マガジン』『JAM』のバック・ナンバーの全てを買い揃え、隅から隅までなめるように読んだ。グルジェフやスーフィー、ケネス・アンガーにジョン・ウォーターズ、それにL.A.F.M.S.。それらはその後の『HEAVEN』へと続く高杉弾の一連の雑誌でしか知ることのできないサブ・カルチャーの秘境だった。[6]
こうした体験はECDだけにもたらされたのではない。彼と同じ世代に属する北海道から進学のために10代半ばから東京に滞在していた、現在、精神科医/評論家、香山リカは、『X-マガジン(一号で廃刊)』『JAM』『HEAVEN』の編集スタッフが”HEAVEN EXPRESS”として参加した別冊宝島『センス・パワー(1980年)』を手にとり受けた大きな影響を回想している。健康の問題などにより同様に10代半ばで自由な時間を持ち「東京のインディーズ音楽シーンに関わりを持っていた」[7]、現、メディア論研究者/和光大学准教授の野々村文宏はそのシーンの関連で出入りしていたクラブのパーティで山崎春美と知り合い、その後『HEAVEN』の副編集長になっている。1980年代の初めには香山、野々村ともに山崎のプロジェクト/表現により深く関わった経験を持つ。
10代の気紛れとしか説明のできない、潔癖症と形容してもいいような些細な理由でそれまで心酔していた岩谷宏にECDが失望したことは記したが、そのことを彼は山崎春美と初めて会った読書会の思い出と共に遺している。
「岩谷宏より先に会場に来ていた山崎春美を見て、これが岩谷宏ではないのか、と早やとちりしたのを覚えている。今、考えれば、当時、岩谷宏は三十代、山崎春美はまだ十代だった。年齢だけ考えてもはなはだしい勘違いなのだが、その時の僕は山崎春美の鋭い目つきに、本物の岩谷宏をうわまわる何かを感じ取ってしまったのだ」[8]
細かい世代の話をするなら、『JAM』『 HEAVEN』の中心的なメンバーは年齢が数年上の日本大学芸術学部で知り合った高杉弾/佐山順一郎、隅田川乱一/美沢真之助、近藤十四郎といった人々であり、そこに自由に振る舞う余裕があるだけでなくその自由の限界を試すまで早熟であった「敏感なこどもたち」[9]、例えば、彼らと知り合いその坩堝へ先行していった山崎、それからそこに野々村そして他の人々が参加していった構図がそこにあったように見える。この「敏感なこどもたち」のなかで山崎は雑誌『遊』を出していた松岡正剛率いる工作舎に属していたこともあってフリーランスのライティングと編集にも積極的に取り組んでいき、数年間で“天才”とまで呼ばれるようになっていく。
 『JAM』創刊号(1979年3月)
『JAM』創刊号(1979年3月)一方、『JAM』『 HEAVEN』もしくは工作舎を通じてではなく、山崎が明治大学の“現代の音楽ゼミナール”に出入りすることで通じて知り合っていった、ここにも野々村の言葉をここにも応用するなら“こどもたち”、つまり3人の10代の少年たち、山崎、大里俊晴、浜野純によってガセネタが結成される。
「思い返してみれば、僕が元パール兄弟の窪田晴男氏と初めて出会ったのがお互い十七歳の時だった。〔……〕山崎春美と会ったのも、町田町蔵を初めて見たのも、まだ彼らが十代の頃だった」[10]
山崎と劇団「名無し人」を通して知り合うECD自身も、紛れもなくそんな敏感なこどもたち、当時のマスコミを席巻した言葉で言うのなら“新人類”の1人だったろう。
『JAM』『 HEAVEN』のエッセンスが注ぎ込まれたような『センスパワー!』の副題には「センス・エリートになるための《感性トレーニングの技術》」とある。バブル経済に感謝すべきである大方の生活の不安が払拭された日本のあの時代に、サブカルチャーのマーケットで成功を収めていたJICC出版局(現・宝島社)が出版したこの“MOOK(雑誌と単行本の中間のようなもの)”の”INTRODUCTION”では「感覚は、ぼく等ひとりひとりが確実に跨っている乗物」であり、「ぼく等は、この乗物に乗って他者と出会い、モノと付き合い、世界を見ている」ことが前提とされている。2000年代的には“デザイン・シンキング”とでもいうべきか、ここでいわれる「感性」の「エリート」になるために、この本は“5つのグループの競作”からなっており、そのうちのひとつが”HEAVEN EXPRESS”なのだが、彼らの責任編集の頁を開くなら『ポップ・アヴァンギャルド』の巻頭言にはこうある。
ポップ・アヴァンギャルドに歴史はない。何の理性的基盤も持っていないし、思想性の展開もない。しいて言えば、「ある状態が破れる時の感覚」を逆に作り出そうとする、「眠っている頭の中の秩序」に対応するもうひとつの秩序である。いわゆる「例外」とか「特殊」「異常」「変態」とか呼ばれるフリークな存在が持つ自己破壊性は、僕たちにとってまぎれもなく「例の」であり、「あれ」なのである。「例のあれ」をすべての出発点にしている以上、そこから作り出される世界は非常にあいまいであり、溶解性をおびている。[11]
コンピューターで整合性がとられたのではないレイアウトと判別できるモノトーンの頁に、奇怪で機械的にも機会的にも見えるコラージュとエッセイやブック・リスト、アーティストの名前などが並べられていく。その最後に位置する見開きでは「言葉で物事が考えられなくなったときに捨て鉢な行動に出るでしょ」、「犯罪とかさ。いきなりなぐったりね。そーゆーことがポップ・アヴァンギャルドの本質」であり、それは「霊的衝動」であると念が押される。そしてその必要とされる「霊的衝動」の「ジャンプ」は、セックスもしくはドラッグ、そしてなによりも主体自らをもってしてのメディア化がその最終形という変貌の必要性が唆されていく。「もう書店では文化は買えない」、「自動販売機で国家が買えることだってある」といった『JAM』『HEAVEN』本誌のキャッチ・コピーは有名だが、『センス・パワー』でもそれは変わらない。例えば、「部分は常に全体である」、「物質の将来」、もしくは「自分と他人の区別がつかない」。
一方、この編集と執筆に関わっていた、そして高杉/佐内たちより少なくとも四歳年下であった山崎春美は『JAM』『HEAVEN』の(彼以前に決まっていた)編集方針について次のように回想している――「その当時『HEAVEN』は、どこかの雑誌見て「この写真いいな」と言ってパクって掲載してたの。ロスの『WET』とか、ああいう雑誌からヴィジュアルを1ページ、ボンと丸ごと『HEAVEN』に持ってくる。そういうこと、やる人いなかったからね。[12]。
既出の文学やら思想でも、それぞれの言葉とイメージにまとわりついてくるどろどろした暗い顔つきのイデオロギーとかを避ける手段だとしてのどこかからボンと丸ごと持ってくる「なんでもいいじゃん、なんでもアリだよね」[13]の下に、ファウンド・オブジェクトを選ぶその行為そのものの仕方を含めて展示することは表現だとする。そのとき、ファウンド・オブジェクトとして並べられた「なんでもいいじゃん、なんでもアリだよね」、もしくは「なんでもいいじゃん、なんでもアリだよね」の一例として並置された性器でも、目を覆いたくなる肉体の損傷の画像でも、または動物でも円錐形の石の写真でも、未成年の少年・少女に見える人々のイメージでも、もしくは新聞の三面記事や思想書の翻訳からの言葉でも、それらそれぞれ自体はもちろん芸術表現ではありえない。そこでの特定の対象を特別と見做すことによって勝手に崇拝したり毀損したりする理由の否定がまず前提としてあるからだが、ここでそのことを持ち出すのは「なんでもいいじゃん、なんでもアリだよね」が、文学者で優れたラップの試みを残している、いとうせいこうの云うところのサンプリング手法の解釈“盗みの美学”という言葉へとつながっていくからに他ならない。このことは後にヒップホップと出会ったECDの音楽自体のありかたと関わってくるので、また触れる。もちろん、このことはデジタルでサウンドを複製するサンプリングを通して表現の自由なる御大層なお題目と関係してくる。
ところで、この公の編集方針があるとしても、敏感なこどもたちの先頭に立った山崎春美は、『ポップ・アヴァンギャルド』では「例の」「あれ」と避けられ曖昧にされていた主体と対象の峻別をそのアートの実践の初めから身をもって、つまり容赦なくはっきりさせようとしてきたように思える。
もちろん、現在も増え続けていながら、文学から音楽、パフォーマンス・アートなどなど広範囲にわたる山崎春美の運動の軌跡と作品群についてここで要約などできるわけがない。しかし、例えば、ロック以降のサウンドと言葉の発現として何がありうるか、その驚くべき先行的試行の記録といえる大里俊晴(ギター)、佐藤薫(テープ、パーカッション、ドラムス)、野々村文宏(プリペアード・ピアノ)らとの1982年のタコのライヴ[14]ひとつとってみても、記録されたパフォーマンス(サウンド)の際立ちはいうまでもなく、この編成にプリペアード・ピアノを組み込むこと、そのサウンドの渦中における山崎の日本の話し/聞く/書く言葉を使っての働きかけ方、全体ライヴ・パフォーマンスを12インチ45回転のアナログ盤シングルで記録としてリリースすること、アートワーク、タイトル、すべてにおいて類を見ない水準の高さと日本ではあまり馴染みのない大きな視野、世界への視線がある。しかしどんなに成功裏に終わったか/終わっていくと見える表現でも、私たちを包囲するばかりか血と肉と骨へ取り込まれていくものとしての詩語の制度性を知り尽くすだけでなく、前衛として役割をまっとうしなければならない山崎の、その多くがインター=メディアなプロジェクトは、ときに予告なしに途切れるように終わらなければならない。
『JAM』『 HEAVEN』に関わっていた人々のうちどのグループの一体誰が早熟か否かなどということではなく、もちろん様々な意味で振り返る意味のある『JAM』『 HEAVEN』の雑誌出版史での突出した評価とは別にして、もし山崎の作品群や意識と雑誌メディア『JAM』『 HEAVEN』との分別を特徴づける外的な条件があるとするなら、まずそのうちのひとつは個人それぞれの資質や才能とは別に、後年、山崎がはっきりと回想する「(自分の年齢では、当時)学生闘争とかないから。〔……〕僕の年代では全然ないので」[15]という、他の何でもありえない、紛れもない現実の世界でどこのどちらの側に立つのかが鋭く問われることの、つまりセクショナリズムどころか政治が表から一切消失した日本のあの時期をどう捉えるか、その視線との関連にあるとここでは暫定的にしておきたい。そのとき、その時代に自称知識人たちが是とした曖昧なる日本の私であることを山崎は断固として拒否していた。そのことはECDの軌跡を私たちが考えていくうえでも意識されるべきだ。そのうえで、例えば、ウィリアム・バロウズとブリオン・ガイシンの遺した系譜を日本において考えるなどという問いに答えようとするなら、山崎春美の名前がまず挙げられなくてはいけない。
『竹田賢一×山崎春美×松村晋也(司会) 吃音の美、痙攣する愛』(Youtubeより)
春美の部屋にはのちにロリータ順子としてタコのメンバーになる篠崎順子も出入りしていた。まだ現役の女子高生だったはずだ。出演者だけでは芝居は成り立たない。誰が招集したのか、衣装やメイクなどのスタッフのひとりとして篠崎順子も混じっていた〔……〕[16]
公演の本番は目黒区民会館で行われた。二百人くらいのキャパシティのホールが七割くらい入っていたと思う。僕の記憶に残っているのは客席の真中の通路を春美が舞台に向けて這うように出ていく姿だけだ。[17]
たった一回きりの最初の公演を終えて、一度だけメンバーが集まることがあった。山本の実家の近くの新代田の駅のとなりにある区民センターでのことだった。その会合を最後に峯岸と春美は劇団を去った。しかし、同じ『ビューティフル・ピープル』の再演がもう決定していた。[18]
マーケティング会社の社員がプロデューサーとして参加することになった。〔……〕再演の会場は青山ベル・コモンズの最上階のイベントスペース「クレイドル・サロン」に決まった。〔……〕十代の男女が数人新しくメンバーとして加わった。この時点で二十歳を過ぎていた山本以外は役者全員が十代という劇団となった。〔……〕『週刊現代』と『クロワッサン』に「美少年劇団」という見出しで記事が載った。[19]
[1] ECD『いるべき場所』、p.76、メディア総合研究所、2007年。
[2] 山崎春美『天國のをりものが 山崎春美著作集1976-2013』河出書房新社、2013年、p. 30。
[3] ECD『いるべき場所』、p. 76。
[4] 同前、p. 77。
[5] 同前。
[6] 同前、p. 78。
[7] 山崎春美『天國のをりものが』、p. 358。
[8] ECD『いるべき場所』、p. 58。
[9] 山崎春美『天国のおりものが』、p. 358。
[10] ECD『何もしないで生きていらんねぇ』本の雑誌社、2011年、p. 207。
[11] 『別冊宝島20 センス・パワー』JICC出版局、1980年、p. 212。
[12] 「“著作権”無視の場所ばっかり行ってた」、赤田祐一、ばるぼら『20世紀エディトリアル・オデッセイ 時代を創った雑誌たち』誠文堂新光社、2014年。
[13] 同前。
[14] 『タコ/セカンド(ライヴ)』、CHAOS 00002、1984年。
[15] 『竹田賢一×山崎春美×松村晋也(司会) 吃音の美、痙攣する愛』https://youtu.be/V4G47m2vGws?si=ZZ9KIu1Sc1qajhc9 聞き取り文責:荏開津。
[16] ECD『いるべき場所』、p. 64。
[17] 同前、p. 66。
[18] 同前、p. 66。
[19] 同前、p. 67。