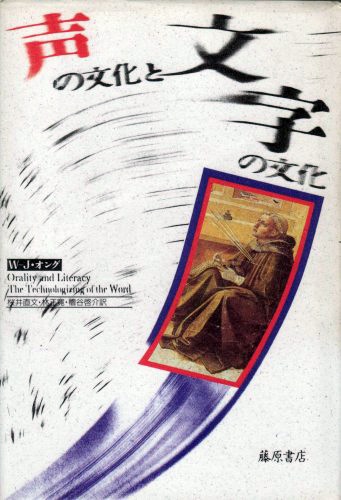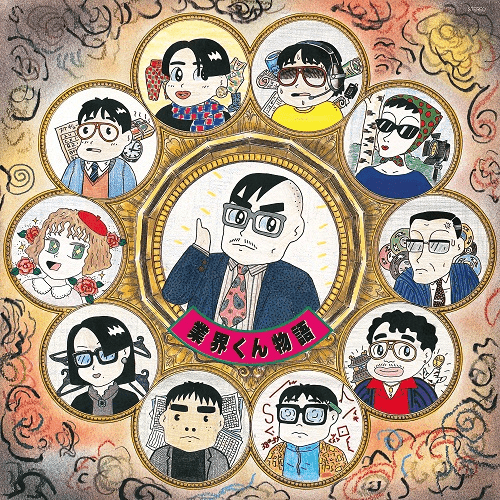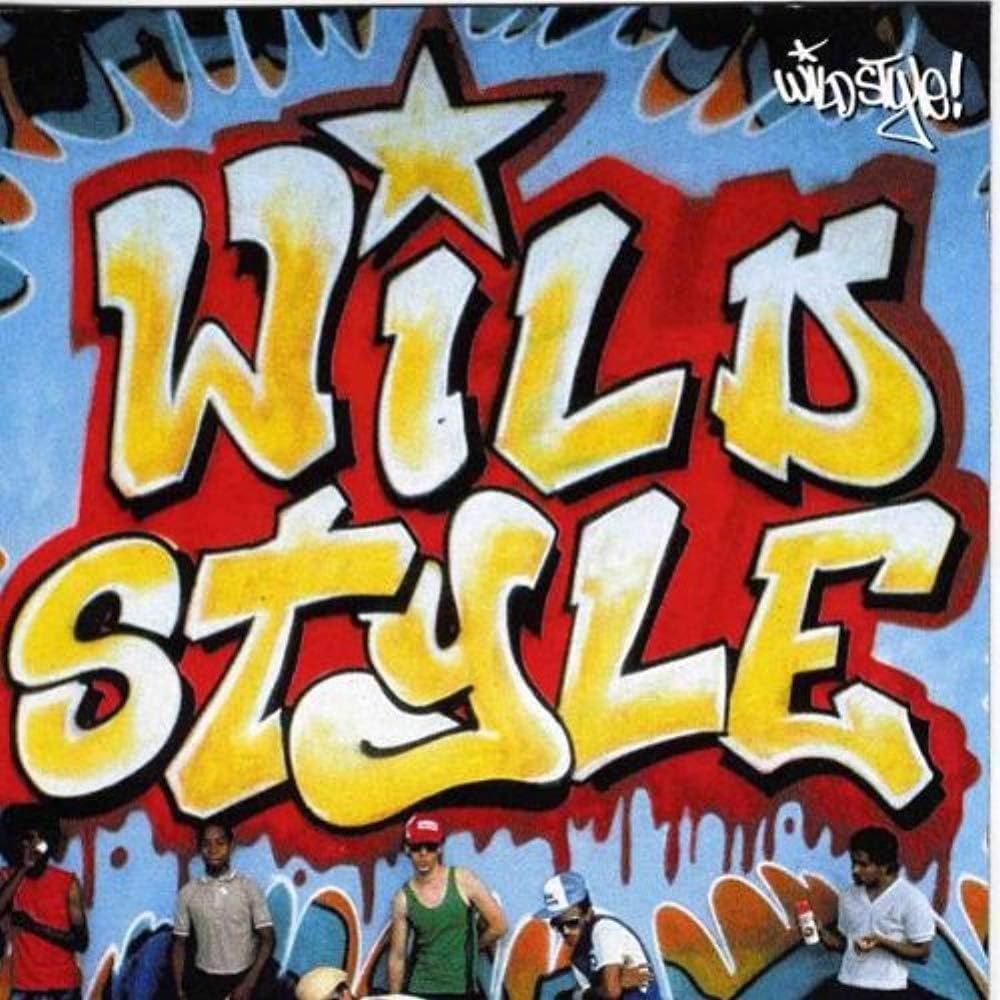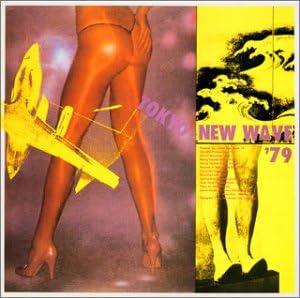一般的にいってロックの創造性、その内実の魅力が失われたことは、日本のロックのそれまでの熱心な聞き手にはすぐに感じられるものだった――「1977年といえば、まだパンクの勃興は明らかでなく、かといって、前年が終末感漂うイーグルスの『ホテル・カリフォルニア』だったから、ロックの元気は明らかになかった。」[1]
少年時代を振り返りロックの元気のなさを記したサエキけんぞうや彼の仲間たちの後年の音楽と態度は、遠くから近くから当初はさざ波にも見えても、実際には東京のロック・シーンのみならず日本のアートとカルチャーに大きく共振していくし、またこの動きはECDとも遭遇し、彼に持続して影響を与える。
その1977年、細野晴臣はソロ・アルバム『PARAISO』をレコーディングしており、翌78年2月に坂本龍一、高橋幸宏を自宅に招待してイエロー・マジック・オーケストラの結成を持ちかけているのは有名な挿話だが、田中雄二の労作『シン・YMO』(2022)に再録されている『PARAISO』プレス・キットの細野晴臣による「ディジタル・ミュージックとアナログ・ミュージック〔……〕あらゆる対極を結ぶ世界が間近に来ている」[2]は、幽体離脱体験を含む複雑で極めて個人史的な流れがあったにせよ、身体性とつながっていた伝統的な楽器という形をしたもの以外のテクノロジーを内側に取り込む畏れを引き受ける意思の確認ができる驚くべき言葉だ。もちろん、この変動はポップ音楽産業の周辺のみならず、ありとあらゆる芸術の領域で起こっていた。そのほんの一例を挙げよう。
名門ノースウェスタン大学で美術を学び、今年のDIC川村記念美術館の展示も素晴らしかったジョセフ・アルバースの色彩や構成の理論に基づいて1950年代にはパリやマドリッドで絵画に取り組んでいた中谷芙二子は、1964年に戻った東京でロバート・ラウシェンバーグとデヴィッド・チュードアに出会う。彼らの紹介から、中谷は、1966年、ラウシェンバーグ、チュードアにジョン・ケージなどという芸術家たちと科学者、技術者たちの史上初の大規模なコラボレーション・イベント〈九つの夕べ:演劇とエンジニアリング〉のパフォーマンスに参加、1970年、大阪万博ではペプシ館で《霧の彫刻》を発表する。その後、中谷は新しいメディアであるビデオを取り上げる。そのなかには政治的な場へ赴く作品、例えば『水俣病を告発する会 テント村ビデオ日記』(1972)も含まれる。
1967年、世界初の携行可能な小型ビデオ“ポータパック”をSONYが開発したこともあり、日本では1970年代から80年代にかけてビデオ・アートは盛んになっていった。中谷芙二子以外にも、飯村隆彦、出光真子、かわなかのぶひろ、久保田成子、小林はくどう、松本俊夫といった作家たちに加え、日本に留学した後にニューヨークに拠点を移し活動を始めたナム・ジュン・パイクとの結びつきも強くあった。
松本俊夫がモナリサの色をグルグルと変えてしまった[3]ように、こうした変化は“ポータパック”の粗い画像の表層にのみでなく社会のありとあらゆる局面で起こっていて、また起こりうることを人々は予測できた。急進的な政治行動は失敗に終わり、そのあとの空洞をギターで表現可能な限りの情動で埋め合わせしていた既定路線のロック/ポップの感受性の見地からは、しかし枠組みの変更へ赴くことそのこと自体が“軽さ”や他と解釈されて受け止められただろう。初期の大型コンピューターのプログラミングを含めて延々とスタジオで地味な作業に取り組んでいたYMOのファーストのレコーディングの際に3人から話を聞くインタヴューアの戸惑いはその表れでもある。
その戸惑いは、ポータパックを持って街に出てチッソ本社の前の抗議運動にて患者たちの話を聞くことは、アトリエの奥での秘密裏に行われる天才と裸体の女性モデルとの一対一の重々しい視線の交接と絡められる絵筆の技術の組み合わせと異なるばかりでなく、その行為は政治行動で芸術として認められないと訴える気持ちと、アートの領域の逸脱への反動という点で繋がっている。ならばどこまでがアートなのか。実際には中谷芙二子や松本俊夫はほんの一例で、異なる同じときの裡において発達した新たなテクノロジーがストリートで新しいアート、つまりヒップホップを生み出していた。
全体にいえるのは政治にうんざりしていようがそうでなかろうが、桐山襲いうところの「伝説」[4]に準えられるトラウマを遺してぽっかりと生み出された空白、当時のいう“シラケ”とどのように対処する態度をとるかが課題だったのである。
ジョン・ライドンが率いたパブリック・イメージ・リミテッドは、一時期“メディア・カンパニー”を自称してヴィデオを制作していたし、セカンド・アルバム『メタル・ボックス』ではまだロック・バンドらしき編成だったものを崩し、1981年『フラワーズ・オブ・ロマンス』を発表する。そして、その後そのアプローチの方向性の見直しがなされた一因は、ライドンが当時移り住んでいたニューヨークにて感受したラップの経験だったように思える。
1983年、演劇活動を続けながらその熱意が徐々に失われていく時期に、以前から愛読していた雑誌『ロッキング・オン』のインタヴューで、ECDは崇拝するジョン・ライドンがヒップホップを賞賛していることに気がつく。当時の『ロッキング・オン』は他の日本のポップ音楽プレスと同様にセックス・ピストルズの物騒なファッションを脱いだジョン・ライドンを含むボーイ・ジョージやジャパンといった――シンセ・ポップの台頭した新しいUKのロック/ポップ・アイコンを多く現在のK-ポップ・アイドルのように扱っていた。
ライドンは「アメリカのミュージシャンであなたと同じ資質を持っている人はいますか」という質問に、「同じ資質というか、好むのはラップだ」[5]と答える。
ある日、それまでYMOには全く興味を示したことのなかった山本が、突然稽古場で「今度出た『増殖』は絶対聞いた方がいい」と劇団のメンバー全員に向けていった。〔……〕『増殖』には曲間にスネークマン・ショウの寸劇が収められていた。僕が反応したのはスネークマン・ショウの方だった。[6]
当時は「スネークマンショーは76年の春にラジオ番組として生まれたが、実に長い間、その正体は不明」[7]だったその時期、ECDは音楽以外の芸術形式にも目覚めていく。
『HEAVEN』は内容的には、その前身である『X・マガジン』『 JAM』を引き継いだものだったが、表紙が大きく変わっていた、羽良多平吉氏による蛍光色を効果的に使った目がくらむようなアート・ディレクションに僕は目を見張った。丁度その頃、僕は劇団が発行するミニコミの制作をまかされていた。当時、出始めたばかりのカラー・コピーを使って、羽良多平吉のような色彩が出せないか模索したりした。〔……〕アート・ディレクションを本格的に勉強したほうが自分にとって良いのではないかと本気で考えた。そしてシュールやダダの画集や写真集を買い漁った。[8]
こうした「自分たちがやっていることを評価できずにひとがやっていることばかりよく見えるという最悪の状況がさらに深刻に」[9]なっていった時期、ECDにとっての「八三年は僕が本格的にヒップホップと出会った年」[10]となった。
パンク=ニューウェイヴを核として哲学や前衛美術運動の影響によってロック・バンドという形態のアクチュアリティのみならずその華やかに喧伝された意義に隠されたコンサーヴァティヴな本質が暴かれていったこの時期、書かれた言葉ではなく話される言葉が重要になると同時に身体性がよりクロース・アップされていく。
それは美術かぶれのミュージシャンがダダから未来派、コンセプチュアル・アートにポップ・アートまでの流儀やボキャブラリーで、自分たちの音楽を恣意的に飾り立てたというだけでない。繰り返しになるが、ロンドンでも1968年の急進的政治運動の敗北を美大生として経験したマルコム・マクラレーンとジョニー・ロットン/ジョン・ライドンにヴィヴィアン・ウエストウッドが、そしてセックス・ピストルズが、彼らの親衛隊が、彼らの溜まり場のショップの存在がそのほぼ10年後のUKの社会に対したことは、発達したテクノロジー=マス・メディアを通してロック・スターなる階級社会の或る種義賊的な仮想が承認された社会を前提に、実にファッションが意味することを思う存分に利用して実行に移されたオペレーションであった。
そのことは遥かその後の2000年代、東京の一角を舞台に、野心的で才気に溢れた日本人の若者たちの「裏原宿」と呼ばれる動きにまで波及するが、マルコム、ピストルズ、意識的なパンクたちがやってのけた全体が社会に与えた文化的影響は、それまでの伝統的な油絵や彫刻や工芸といった媒体や拵えものでは代替不可能な、3コードのロックン・ロールやストリート・ファッションといったブルジョワ社会の美の規範が侮っていた領域から吹き上がった不測の出来事[11] であったといえる。油絵、彫刻、工芸、もしくは小説とか批評で同じ主題を扱うことができる――例えば「今日の英国における無政府主義」とか「君主制反対」とか題して――しかし同様のインパクトは到底得られなかっただろう。
書かれた言葉と話される言葉、1970年代の終わりから80年代にかけて大きな空白のあることに自覚的だった言葉は、その役割に従って変化していた。イエズス会司祭にて英文学教授、ウォルター・J・オングは彼の『声の文化と文字の文化』で、「コミュニケーションや思考が声にもとづいて組み立てられている世界」は「文字によって組み立てられている世界」の「一変種」ではないとして「ことばの声として性格(オラリティー)と書くことwritingの関係」について分析していた。主にこの著書ではその昔、西欧の芸術の源泉として詩文がどのようにできあがっていったかそのなりたちの過程の枠組みを記し、その最後の部分で「ことばの技術化」がなされた20世紀後半に輝かしくも君臨した「メディウム」への考えの誤りに触れる。彼のいう「第二次声の文化」の重要性は、ラップとDJのみならずソーシャルメディアが隈なく普及し誰もが自らの事情について口を開くことに躊躇いがなくなった21世紀の状況の明らかな先取りである。
既にサウス・ブロンクスでは疎外された少年・少女たちがマイクを握り始めていたその同じ時の裡に、日本のパンク/ニューウェイヴの文脈でも新しい言葉の胎動があった。例えば、古くはECDに衝撃を与えたSSやフリクションの異化効果、もちろん山崎春美のガセネタからタコの鮮やかな芸術の試行の軌跡、竹田賢一のA-Muzik、また吉祥寺マイナーの闇のなかの黒い馬の如くのバンド群の幾つも、そして他にもだ。
八一年の三月にはINUの『メシ喰うな』がリリースされている。〔……〕このアルバムは僕を完全にノックアウトした。前後して町田町蔵本人を間近に見る機会にも恵まれた。山崎春美や工藤冬里のライブ、それにケネス・アンガーの『ルシファー・ライジング』や石井聰亙の『高校大パニック』のオリジナル版の上映等盛り沢山のイベントの中、町田町蔵と遠藤みちろうがステージに並んで「メシ喰うな!」「メシ喰わせろ!」を交互に歌うというシーンがあったのだ。出番前、町田は同行した女の子に会場のベンチでひざ枕をしてもらっていた。そんな無頼な様子も含めて、僕は町田に惚れこんだ。町田は僕よりも二歳も若く、その時まだ十九歳だった」
このアルバムについて、2023年、町田町蔵改め作家・町田康がゆっくり語る動画がある――「いわゆる型から外れたような、まぁ大体こういう風にすんのやでっていうことを、全部無視して、好きなように、自分らのやりたいように自分らでやろうやないかいみたいな、そんなような流れのなかで、まぁ色々な意味で無茶苦茶やってた」[12]という。その無茶苦茶とは、「歌詞やなんかでも、いわゆる語彙、それまでの日本語の歌詞と呼ばれる範疇にはなかった他からの語彙を持ってくる。大阪という地域性もある。大阪というのは雑食性というか、なんでもミックスしていく文化ですから、純粋性を追求していくというか、物事をミックスして混ぜて拵えていくというところがございます。それゆえにロックをやるんやパンクをやるんやというなら、ロックを突き詰めてロック的な語彙に純化していくとか、そういうことをやるんではない」[13]。
町田康「INU メシ喰うな!」を語る Vol. 1(YouTube)
その例として、 “おっさんとおばはん”という曲の歌詞の一部は上方落語からの流用だと町田は挙げる。その後の1980年代の町田町蔵は、パフォーマティヴにならざるをえない”話される言葉“、すなわち”声の文化“に係る即興を含む演奏との関係の信頼を試すかのごとくの幾つものプロジェクト、人民オリンピックショウ、至福団、北澤組といった名称の下に、それこそ山崎春美や和田哲郎といったECDの身近な才能とコラボレーションを続けていった挙句沈黙し、その後1992年に詩人として、96年に小説家として、町田康として再び登場するだろう。
[1] サエキけんぞう『さよなら!セヴンティーンズ』、クリタ舎、2007年。
[2] 田中雄二『シン・YMO』DU BOOKS、2022年P. 47。
[3] 松本俊夫『Mona Lisa』(ヴィデオ作品)1973年。
[4] 桐山襲『パルチザン伝説』河出書房新社、2017年。
[5] 『rockin’ on』9月号、1983年、p. 37。
[6] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p. 85。
[7] 『これ、なんですか』桑原茂一2監修、新潮社、2003年、p. 10。
[8] ECD『いるべき場所』、p. 84。
[9] 同前、p. 89。
[10] 同前、p. 90。
[11] つまり、その意味を掴んでいたのは、日本では必ずしもロック・ミュージシャンには限らず、藤原ヒロシ、高橋盾、滝沢伸介、Skate Thing、NIGO、そして裏原宿と呼ばれるムーヴメントに属していた人々であった。
[12] 町田康「INU メシ喰うな!」を語る Vol. 1、YouTube(https://youtu.be/EWSx5hCyyMY?si=tzZCzpDLHV5dNj-p)。
[13] 同前。