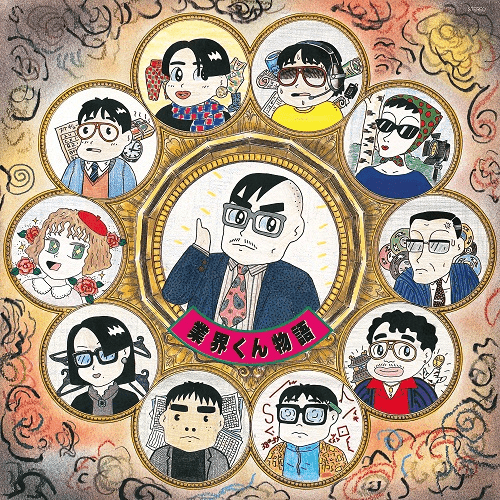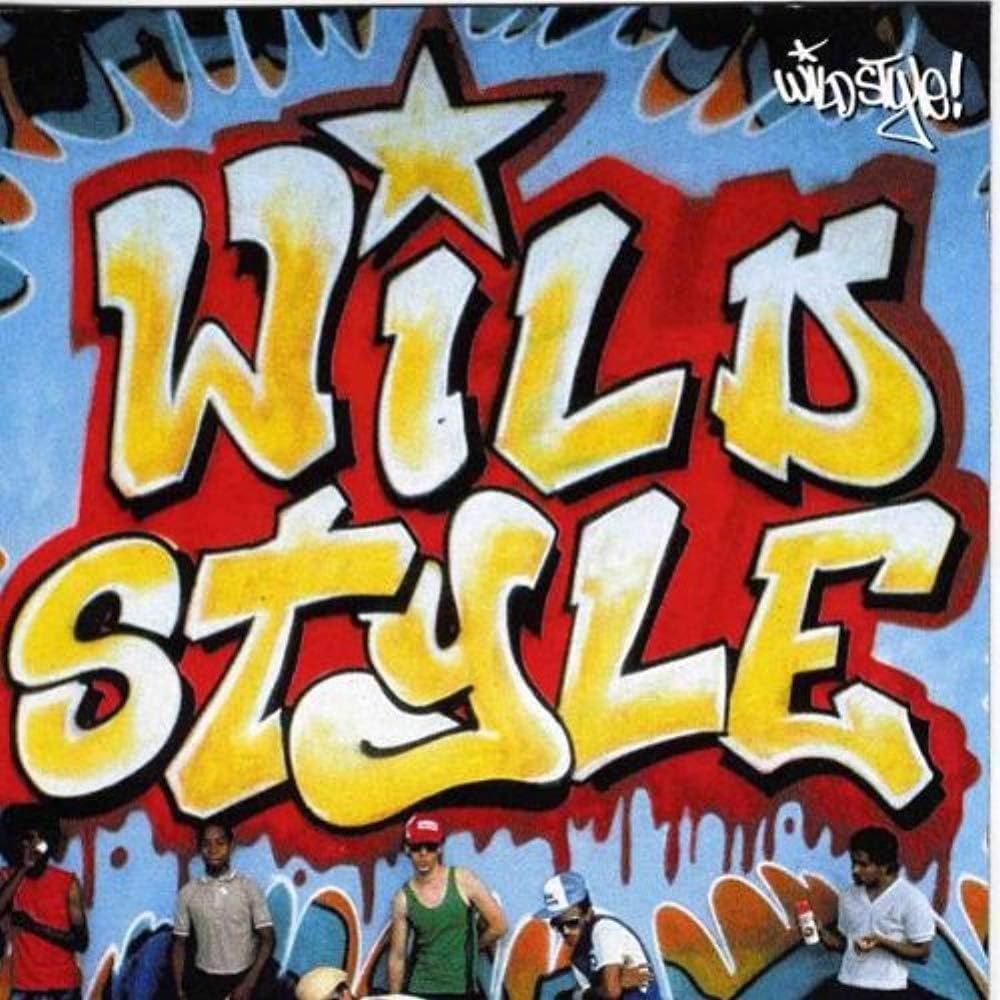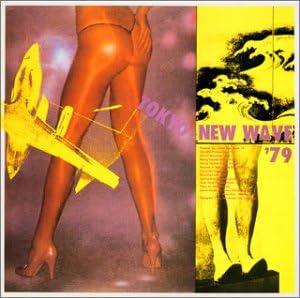僕はといえば中学を卒業してすぐに、やはりボウイが縁で同い歳の女の子三人組と知り合うということがあった。彼女達はそろって家庭に問題を抱えていた。〔……〕僕は三人の中の一人の家出を手伝ったりして、相手の親から「ウチの子をたぶらかして!」なんて電話がかかってきたりした。[1]
「お宅の息子にたぶらかされたって言ってたよ」電話を切った母が僕にそう言った。エノモトさんが家出したのだ。電話はエノモトさんの母親からだった。[2]
僕は行方を探すことより、ひとりになったエノモトさんこれからの生活を助けることを考えた。[3]
それから数日後、アラカワさんから『ロッキング・オン』の編集部でオノモトさん[4]と会うことになったという電話があった。当時『ロッキング・オン』の編集部は東中野にあった。僕もオノモトさんに会うために東中野に向かった。編集部には渋谷陽一がいて、「ダメだよ、家出は、ホントに」と慣れた口調で僕たちを諭した。当時、『ロッキング・オン』読者の家出が続出していたのだ。[5]
もう家には帰らない、ひとりで自活してゆくというオノモトさんの生活を援助するために僕は次の週から新聞配達のアルバイトを始めた。[6]
家出したエノモトさんはあちこちを泊まり歩いていた。「今、三鷹にいるから」と、電話でよびだされていった部屋にはアフロディス・チャイルドやプリティ・シングスのレコード・ジャケットが飾ってあった。〔……〕そこが誰の部屋なのか、エノモトさんは言おうとしないし、僕も聞こうとはしなかった。夏休みが終わり、二学期が始まってからも新聞配達は続けた。朝の三時半に起きて朝刊を配ってから学校へ行き、その帰りに夕刊を配る。授業中は足りない睡眠時間を補うために眠るだけの時間だった。[7]
当然、成績はガタ落ちした。僕はもう、そのまま、次の年も高校生活を続ける気がなくなっていた。[8]
彼が高校を辞めてしまうきっかけになったのは、『ロッキング・オン』のライターとしても読者によく知られていた松村雄策を中心としたバンド、イターナウ(Eternow)のカセットテープに同封された、当時のECDが崇拝していた『ロッキング・オン』のライター/思想家、岩谷宏の檄文を読んだからであると、彼は繰り返し記し遺している。
食にまつわる仕事で生計を立てていくという思いつきは、デヴィッド・ボウイの兄弟が船乗りであるというトリヴィアが彼をして船上でオーガニック・フードを供するコックになるという、10代初めの少年らしい、しかし、食の革命がカウンターカルチャー最大の遺産とするならば特異に「68年」らしくもある空想の放物線の行き着いた現実との接触点ゆえによる
その時、頭にはあったのは、岩谷宏の文章で登場した三鷹の「江ぐち」のようなラーメン家を将来自分で始めることだった。〔……〕朝、学校に行くふりをして家を出て都内のラーメン店を食べ歩く、そんな日々が続いた。やがて、学校に来ていないという連絡が担任教師から親に伝わり、それを契機に僕は自分の決心を両親に打ち明けた。[9]
学校は三学期いっぱいで辞める。そう、父と母に打ち明けた。父は保証人になってくれた仕事上の恩人、Kさんに顔が立たない、と取り合ってもくれない。母も高校だけは出てほしいと涙を流した。僕は譲歩することにした。高校は辞めないけれど昼間は働きたい。だから、二年目からは同じ石神井高校の定時制に編入する。[10]
七六年の四月から僕は、それまで通っていた都立石神井高校の定時制の二年生となり、十時から五時まだは吉祥寺の東急デパートの裏手にあった「バンビ」というレストランの厨房で皿洗いとして働くことになった。[11]
レストランの洗い場の仕事は一日中立ちっぱなしだ。ランチタイムは戦場のように忙しい。何も考えていられない。昼間の仕事と、夜の学校、家には寝に帰るだけだ。一週間が過ぎるのが早い。[12]
そうやって何はともあれ自分で行動を起こし自分の人生の方向を変えることができたことに僕は満足を感じていた。僕が引っ掻き回した家の中もとりあえず平穏を取り戻したように見えた。僕はこのまま仕事と学校という日常に埋没していくかのように思えた。そして、ひとりで外で酒を飲むこともおぼえた。最初は吉祥寺駅北口のパチンコ屋のとなりの立ち飲み屋のホッピー屋に始まり、やがて、ピザを食べさせるようなバーにバーボンを入れたりするようになった。[13]
学歴を放り投げた後にECDが満足を覚えていたという現実の日々は、実際には、父親と母親を通して最も馴染みの深い労働者階級のモノトナスな暮らしであり、彼もまた齢17を前にしてその暮らしに参入したということに尽きる。
そこで親から放任されたのと同然の――一体、他にどのように形容できるか――労働者階級の子弟に相応しくアルコールの味とその及ぼす酩酊の感覚は若くして彼に植えつけられた。彼の過ごしていた吉祥寺や八王子のその日々は、例えば、その少し前の時代の“怒れる若者たち”と呼ばれたアラン・シリトーやシェラ・ディレニーが『土曜の夜と日曜の朝』や『蜜の味』で暴き立てたノッティングヒルやサルフォードの同じ階級の少年や少女の暮らしぶりと、結局、寸分も違うことはなかったろう。
だとするならば、なにを馬鹿なことをしているとその外部からは考えられたとしても、いつまで経ってもいつまで待ってもマジメであることが貧しいということを打破しない現実への彼の幻滅が、その実際の事態の把握へではなくて逆に彼の内側へと、10代半ばの少年が酒の味を覚え「舐めることを至上の喜び」とする、はっきりとした自傷へと向かったのである。この自傷/自虐が、その後長い期間に渡っていくことを今の私たちは知っている。
両親共にマジメな働き者だった。そのマジメさを僕は誇りに思うことさえあれ、キュークツだとかツマラナイとか思ったことはなかった。ただ、家族四人が六畳一間で暮らす自分の家が貧しいという自覚はあった。マジメなのに、貧しい、そのことに理不尽を感じ始めてもいた。[14]
普通なら、そこで「金持ちになってやる」と思うのだろうが、僕は違った。[15]
僕には実際に酒を飲む年齢に達するずっと前から「ヨッパライ」に対する強い憧れがあった。[16]
なぜ「ヨッパライ」なんかに憧れるようになったのか?
キッカケはいくつかある。その中で最も古いと思われるのがフォーク・クルセイダーズの「帰ってきたヨッパライ」を聴いたことだ。〔……〕とにかく徹底的にフマジメな歌である。ヨッパライ運転で死んでしまった「オラ」は長い階段を登り天国にたどりつく。「酒はうまいしねえちゃんはきれい」な天国で「オラ」は酒を飲み続ける。この歌では「もっとまじめにやれ」という神様にたてついて酒を飲み続けたおかげで、あろうことか生き返ってしまうのだ。さらにそんなフマジメな内容の歌がテープを高速度で再生させたヘンテコな声で歌われる。前衛という「マジメ」になるはずの新手法が「ヨッパライ」の声を表現するために使われたことも実に「フマジメ」だと思う。それは「現実」ではなく「非日常」、あくまで想像の産物として僕の中に住みついたのだった。「帰って来たヨッパライ」から「マジメにやってもソンするだけだ。フマジメにやったほうがトクだ」というメッセージを受け取った僕は「フマジメになってやる」と思うようになる。〔……〕実際に酒を口にしたのは、小六か中一の正月。お屠蘇代わりの日本酒を飲ませてもらったが最初だった。飲んでどう感じたのかはよく憶えてない。ただ、飲んだらどうなっちゃうんだろうとふくらんだ期待の大きさだけははっきり憶えている。[17]
同時に、酒以外の酩酊への強い嗜好についても彼は記している。
それからもうひとつ、当時の僕には「シビレ」ることへの強い興味があった。
「シービレちゃった、シービレちゃった、シービレちゃったよー」
そう歌い踊るお笑い芸人の姿は「シビレ」ることがどんなに気持ちよいことなのか、子供にもわかるように伝えていた。若い女性達はグループ・サウンズの演奏に「シビレる!!」と歓声を上げた。麻痺することを意味する「シビレ」が快感の表現として大流行する背景にサイケデリック・カルチャーやドラッグ・カルチャーがあったのは間違いない。そして、僕ははからずも「ラリ」ることを覚えてしまう。少六から中二くらいにかけて僕は戦車や戦闘機などのミリタリー系のプラモデル作りに熱中していた。最初はただ組み立てるだけで満足していたのが、やがてリアルな塗装を施すようになる。僕は閉め切った部屋の中で食事を摂ることも忘れるほど塗装作業に夢中になった。[18]
「当時のプラモデル用の塗料にはまだ有機溶剤が使われていた」、そして「熱でも出たみたいにジンジンと『シビレ』たように」[19]なったというのだ。
しかし、「ラリ」ることのできる溶剤はすぐに規制されていつも買っていた模型店では買えなくなった。僕もさすがに「ラリ」るためだけに溶剤を手に入れようとまではしなかった。[20]
僕たちが何よりも心待ちにしていたのが、アメリカ公開から一年後、やっと日本公開が決まったデビッド・ボウイの初主演映画『地球に落ちてきた男』の封切りだった。僕はオノモトさんと二人で七七年二月の公開初日にテアトル新宿で観たのだが、あとにも先にも、映画を観るのにあれほどワクワクしたことはない。この映画でデビッド・ボウイが演じた宇宙人は地球よりはるかに進歩したその母星の技術によって数々のビジネスを成功させる。しかし、政府上層部からその存在を危険視されて幽閉され、最後にアル中になっているという物語だった。僕はデビッド・ボウイのアル中姿にあこがれた。ラスト・シーンにデビッド・ボウイがオーダーした酒は ジンだった、僕はそれから家の冷蔵庫の製氷室にいつもタンカレーを凍らせておくようになった。[21]
サイモン・フリスが『サウンドの力』でロックは快楽主義と余暇の価値にあるとしたが、その始まりからその多幸感のチープな代替としての酩酊への横滑りは既に予見されていた――フリスのいう通りエルヴィス・プレスリーの音楽が10代をそもそも卒倒させたのは、それまでの思春期をまとめていた様々な社会的な記号を溶かしてしまい、それまでのどのシンガーよりも官能的に、肉感的に自らのシンボルを創造するという行為そのものを賛美することに成功したからなのだ。
そもそもその起源を辿るならば、不安定な十代であることのアイデンティティを「そのままで問題はない」とでも耳元で囁くかのようなシンボルを性的なエネルギーで補強する官能の合成性に払いきれない胡散臭さがあるのも事実だが――例えば、哲学者アラン・ブルームの『アメリカン・マインドの終焉』(1987年)ではそのことははっきりと指摘されロック・ファンはニンフォマニアまがいの無能力者扱いをされているし、レコード会社もメディアも彼らを食い物にしたのも事実だろう――しかし、ブルームは、マジメであることが何も現状に働きかけない経験によって心に巣食っていく敗残の感情については語っていない。
ところで当時のECDには、未来の彼がアーティストとしてだけではなくポリティカル・アクティヴィストになるということをどのくらい予想しえていたか。つまり美しいものを作ること、その政治性についてどれだけ感得していたか。
時は1977年。その数年前からマルコム・マクラーレンと彼のパートナー、ヴィヴィアン・ウェストウッドはそれまでロックンロールのメモラビリアと1950年代の古着を売っていた彼らの小さな店舗の名前を次々と変えていたが、この年には「SEX」から「SEDITIONARIES」(註:扇動者たちの意)へと変えていた。マルコム・マクラーレンを詐欺師扱いするのは彼の失敗した自己宣伝的なスタントや韜晦に惑わされすぎではないだろうか。実際、彼はロックン・ロールが何で出来上がっているかを驚くほど熟知していた。彼がセックス・ピストルズのアイデアを女装を厭わないニューヨーク・ドールズから得たことも、「SEX」から「SEDITIONARIES」への変化も、またその後のセックス・ピストルズ/パンクからヒップホップへの転身も、ひと繋がりのナラティヴであり、それは労働者階級出身の教師であった故ヴィヴィアン・ウェストウッドともに性のドライヴを極度に挑発的なコラージュへと拡張していく過程で階級闘争の政治性をあからさまに視覚化し、直接的に制度の現状を堅持しようとするスペクタクルの転覆へと、そして一国的な視域に縛られることをよしとせずグローバルなマイノリティの点在について目を瞑ったままでいるな、そのごた混ぜの美学は明らかにそう宣告しているのだ。ひととき流行ったマルコム・マクラーレン気取りのロック・マネジメントの醜悪な自己正当化は、なによりもまずその美学の政治的な貫通の確かさにおいて比較の対象にすらならない。
前衛パンクはそういう音楽的関連を芸術的な目的に転用した。彼らは音楽言語の「自然性」を疑った。すべての音楽は作られたものだという前提から出発して、音楽の根底までさらけだそうとした。さまざまなジャンルの規則ときまりを並列した。聴き手はそれまでは聴けなかった効果が音楽的に現れているのに注意を向けるようになった。ロックのファンが最も軽蔑していたポップのクオリティである人工性を評価した。彼らはリズムの規則(ディスコ、ファンク、レゲエ)に関心を持ったが、それはリズムが主観主義的・現実主義的に最も記述しにくい音楽要素だからだ。[22]
この時代にECDはパンクになる。彼はツーリストとしてロンドンに出かけていきセックス・ピストルズのライヴを見ることはない。しかし、地元の吉祥寺でガセネタのライヴを体験するだろう。
[1] ECD『何もしないで生きていらんねぇ』本の雑誌社、2011年、p. 216。
[2] ECD『暮らしの手帖』扶桑社、2009年、p. 27。
[3] 同前。
[4] エノモトさんとも記される。ECDの遺した文章では実在の人物の名前は常に少しずつ変えられている。アガワさんはアラカワさんとも記され、サトウさんはカトウさんでもある。
[5] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p. 49。
[6] 同前。
[7] ECD『暮らしの手帖』、p. 27。
[8] ECD『いるべき場所』、p. 49。
[9] 同前、p. 50。
[10] ECD『暮らしの手帖』、p. 28。
[11] ECD『いるべき場所』、p. 51。
[12] ECD『暮らしの手帖』、p. 29。
[13] ECD『いるべき場所』、p. 52。
[14] ECD『何もしないで生きていらんねぇ』、p. 238。
[15] 同前、p. 236。
[16] 同前。
[17] 同前。
[18] 同前。
[19] ECD『何もしないで生きていらんねぇ』、p. 238
[20] 同前、p.239
[21] ECD『いるべき場所』、p. 53。
[22] サイモン・フリス『サウンドの力』細川周平、竹田賢一訳、晶文社、1991年、p. 196。