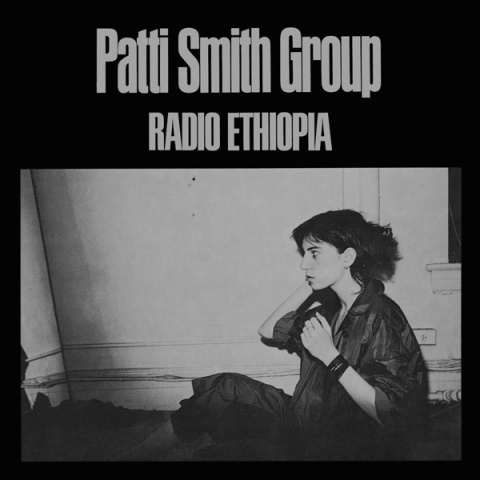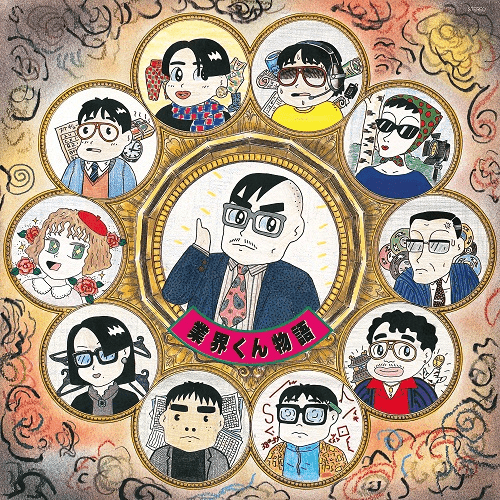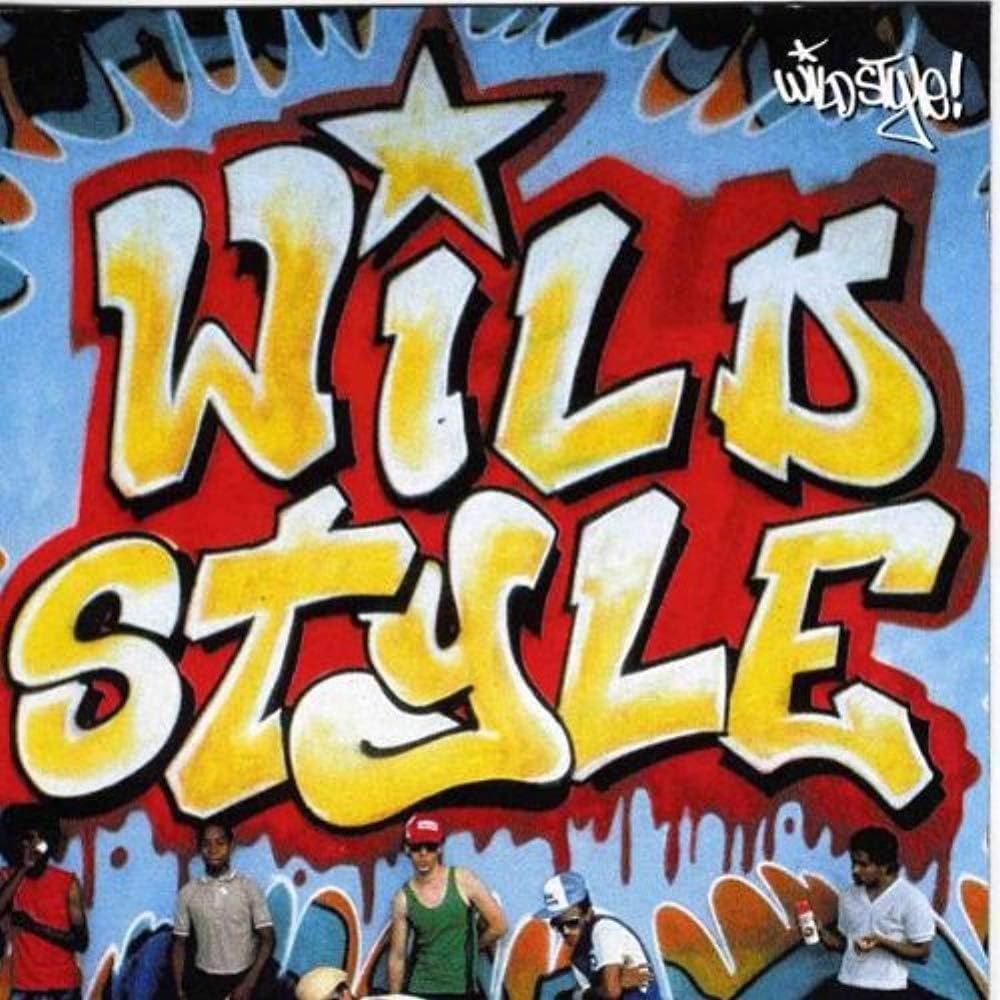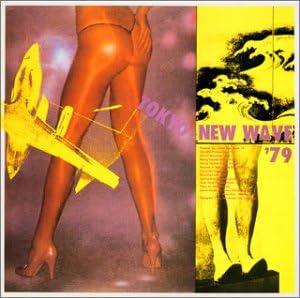1976年、ラモーンズはマーロン・ブランド由来のフェティッシュなデニムにレザー・ジャケットお揃いでの無愛想なポートレートがフロントを飾るファーストをリリースし、パティ・スミスも既に詩的な言葉と時にノイズに近づくサウンドを持つ自身のグループとしてのアルバム『ラジオ・エチオピア』をリリースしていた。
その2月には、セックス・ピストルズは旧態依然とはいえそれでも他の多くの反動的なロック・バンドに比較するならマシなエディ&ザ・ホットロッズのサポートをつとめ、既に公共の場に少し顔を出すだけで穏やかならぬ物議を醸す風態のジョーダンをはじめとしたフォロワーも少数だが集まり始めていた。11月には“Anarchy in the UK”がリリースされる。ジョン・ライドンは19歳で同曲や“God Save the Queen”の歌詞を書いてのけたということになる。
1968年からようやく10年が過ぎ去って“性と政治の季節”が過去のものとして葬りさられると思いきや、ネオ・リベラリズムへ向かう金メッキの道標が時代の標として立てられるのと前後する1970年代終わりから80年代初めの世界中の幾つかの都市を筆頭に、イデオロギーとジェンダー・ポリティクスがポップ音楽を巡って急展開を始める。もちろん、同時期のアメリカ-イギリスでは産業ロックに代表される白人の男性数人がバンドを組むという形式において階級的な居直りが始まっており、日本の主流ロック・ジャーナリズム/ポップカルチャー批評は基本的にこうした変化に為す術を持ちえなかった。以前記したように『ロッキング・オン』にしても『ミュージック・ライフ』にしても、ポップ音楽に持ちえる普遍的な美があるとしてその認定の作業と、消え去ったと思った政治的急進主義を結びつける言葉を持っていなかったからだ。
パンクだけではない。ECDはまだ気がついていなかったが、1977年には、そもそも70年代初めに氾濫していた空回りする政治状況とそれに対する冷笑的な態度へのカウンターから生まれたディスコ・サウンド(“Love is the Message”)が意外な方角――ミューヘンからポップ音楽においてのジェンダー・ポリティクスと人種の結びつきを決定的に、おそらく永遠に、変えた。当時ベルリンでアルバム『Heroes』のレコーディングにデヴィッド・ボウイと共に取り組んでいたブライアン・イーノが一聴してそのことに気がつき、リリースされたばかりのジョルジオ・モローダーとドナ・サマーの”I Feel Love”に驚愕し(「今後15年のサウンドを変える!」)ボウイに聴かせたエピソードは、いつまでも後世に伝えられていくだろう。
Donna Summer – I Feel Love (VJ’s Edit) [Remastered in HD](YouTubeより)
「新宿レコード」の店内でラモーンズのファースト・アルバムやダムドのファースト・シングル「ニュー・ローズ」を見つけ、パンクという新しい音楽が生まれつつあったのを知ったのはまだ七六年のことだった。しかし、ラモーンズのアルバムもダムドのシングルもその時点では買うことはなかった[1]
その頃、イギー・ポップの『イディオット』ばかり聞いていた僕は」[2]「最初に買ったパンクのレコード」[3]「クラッシュのファースト・アルバム『白い暴動』」[4]「の大半を占めるストレートなロックン・ロールに最初、何の新鮮味もなかった」[5]
「しかし僕のそんな思いは『白い暴動』を聞いてからたった二ヶ月後、あるレコードをきっかけに見事にひっくり返される。それが七七年六月にリリースされた『The ROXY London WC2 ( Jan-Apr77 )』というライヴ盤だった。タイトル通り、それはロンドンのロキシーというライブハウスで七七年の一月から四月にかけて行われた様々なパンク・バンドのライブ演奏を収めたレコードだった。このアルバムにはセックス・ピストルズもダムドもクラッシュも収録されてはいない。そのかわりにバズコックスやワイアー、X・レイ・スペックス、それにアドバーツといった面々の演奏が収録されていた。このレコードにはライブの曲間に観客が上げる異様な叫び声や演奏者と観客が何か言い合っている様子などが生々しく録音されていた。僕は何よりもその混沌とした雰囲気に、初めて「これがパンクか」と思い、確かにそこで何か新しいことが起こっていると確信したのだった」[6]
セックス・ピストルズのレコードで僕が最初に買ったのは「アナーキー・イン・ザ・UK」でも「ゴッド・セイヴ・ザ・クィーン」でもなく七七年の七月にリリースされたシングル「プリティ・ベイカント」だった。〔……〕新宿レコードは丁度この頃、それまで店を構えていた小滝橋通りの東側のビルの二階から、同じ小滝橋通りの反対側を少し入った公園の近くのビルの一階に移り、売り場も広くなり、なんと、パンクの7インチのコーナーが新設されていた。「プリティ・ベイカント」によってパンクのシングル盤のアート・ワークの素晴らしさに魅了された僕は、それから毎週欠かさず入荷日には新宿レコードへ行き、入荷したばかりのパンクの7インチをジャケ買いするのが何よりの楽しみになった。その頃のロンドンのパンク・シーンは大袈裟でなく週単位で何かが起こっている、という雰囲気があった[7]
多摩川沿いの町で共産党や在日コリアンといったアイデンティティに悩んでいた女友達を追いかけて右往左往しながらデヴィッド・ボウイに憧れ、ルー・リードの退廃的な描写や音を知り彼の来日公演に出かけていき、それまでの昼の世界とは異なるどこかへ属そうとしていた「夜の人々」を目撃したECDは、ピストルズやクラッシュのストレートなロックン・ロールであることが試験的な曲に何が託されようとしていたか、WIREやX・レイ・スペックスがヴェルヴェット・アンダーグラウンド やイギー・ポップから何を受け取り、何を表現し変えようとしていたのかを感知していく。彼はそれらを飽きたらない、つまり彼が拭いきれない違和感として「のっぺらぼう」と評した新開発され仕上がった吉祥寺と一体の、当時流行の「ニュー・ミュージック」や「戦後民主主義」の後に来たるべき風景の、未来からの響きとして受けとめただろう。
七七年のパンクがリアルタイムに日本に与えた影響は意外に小さかった。八六年のヒップホップが日本に与えた影響はそれに比べると大きかった、と書いた。
その理由を考えてみた。六〇年代にはGSブーム、フォーク・ブームがあった。八〇年代にはバンド・ブームがあった。七〇年代はその間に挟まれて、あまり音楽が盛んでない、いわば、音楽にとっての冬の時代だった[8]
のではないか、とECDはかつて記していた。
僕の通っていた中野の小学校の卒業式で卒業生によるバンドの演奏があった[9]
のに
中学に入ってみたら、バンドをやってる奴なんかひとりもいない。ロックを聴いてる奴もクラスには自分の他にひとりしかいなかった。高校に入ってもそれは変わらなかった。ロックだけではない。フォークもそれまでアコギ一本でできたのが、ユーミンの登場でニュー・ミュージックと名前を変えてからはシロウトが簡単に手を出せる音楽ではなくなっていた[10]
パンクはその時期に楽器を弾けなくても良い、などと喧伝され登場した。ECDはアメリカの植民地としての日本のポップの規則にも適用された巧みに反動的で男性支配的なロック・バンドと彼らのロマン主義を都合よく利用した芸術観以外の道筋の存在に気がついていた。その道筋を日本の音楽のありようの限界に働きかける可能性とするには、海の向こうでパンクやデヴィッド・ボウイがやってのけたように音楽の範疇を超えて広くエゴとその外界、すなわち実際の社会のありようと関わらざるをえない。ECDが後に「ネットワーク」、もしくは「ミニ・メディア」とも形容した「シーン」がそこで問題になる。シーンとは聞き手をステージの下の側にいるお客さまもしくは無名のシロウトとして軽視したり消去するのではなく、音楽の生産と消費されるまでのなくてはならない重要な参加者として見ることで初めて顕れる。ECDが記したよう、パンクがもし日本で振るわなかったとしたら、より大きな変更/書き換えの可能性に賭ける必要を多勢の人々が感じなかったということだろう。
これらに踏み込んでいった点でなによりも次の時代を切り拓いていった、そのことを一時的な白人の表現としてのロックではなくグローバルなアートの素、つまりはロックン・ロール、その固有性として取り組んだデヴィッド・ボウイ、イギー・ポップ、ロキシー・ミュージック、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、またクラウト・ロックやガレージ・ロック、そしてレゲエのアーティストに影響を受けたという点で、ロンドンのパンク/ポスト・パンク、もしくはニューウェイヴの世代とECDの求めていたヴィジョンは連動していた。
僕が初めてセディショナリーズの服を買ったのはまだ七七年だったか、もう七八年になっていたか、いずれにせよ十七歳か十八歳のことだった[11]
その頃、パンク・ファッションを売り物にする店はチラホラできはじめてはいたけれど、セディショナリーズを入れておいたのは赤富士だけだったと思う。後にア・ストア・ロボットになる極楽鳥という店があって、そこに行くといつも上から下までセディショナリーズのカップルがいて、僕は「カッコいいなぁ」と見とれていた。しかし、極楽鳥でもセディショナリーズを売っているのを見た記憶はない。その二人がプラスチックスのトシちゃん(中西俊夫)とチカさん(佐藤チカ)だったことに気がつくのはもう少し後だ[12]
(高木)完ちゃんが当時、赤富士でセディショナリーズを買っていたという話はずっと後になって知るのだが遭遇することはなかった。赤富士にセディショナリーズの新作が入荷してもそれでパンクスが押し寄せてあっという間に売り切れる、なんてことは一切なく、本当にひっそり売られていた[13]
そんな赤富士で僕が買っていたのはセディショナリーズといっても主にTシャツとガーゼ・シャツだ[14]
セディショナリーズの服を買って帰ると、袋から出しても、自分で着るよりも先ず広げてあきずにいつまでもアート作品を見るように鑑賞したものだった[15]
十枚ぐらいは集めたと思うけれど、ボンデージ・パンツやパラシュート・スーツまでは手が出なかった。僕は髪質のせいかどうやっても格好よく髪を立たせることができなかったこともあり、オルタナティヴTVのマーク・ペリーのように基本は古着、Tシャツだけをセディショナリーズみたいなスタイルを自分のものにしようとしていた[16]
労働者階級のパンクと移民のレゲエの連帯が可能だったのは、彼らがヒットチャートを占有していた巨大なロック・バンドが実際に英国社会の「バビロン」 側に加担していたという事実にうんざりしていたからだ。その後のポストパンクの世代の一部、ABC、ブロンスキー・ビート、ディペッシュ・モード、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッド、ゲイリー・ニューマン、ヒューマン・リーグ、OMD、ペット・ショップ・ボーイズといったバンドの多くは“I Feel Love”に勇気づけられたのかのように、マンスプレイニングのごとく冗長なソロ・プレイを旗印としていたギターを実際に見限り代わりにシンセサイザーを前面に押し出した。このように音楽の内と外で変革は具体的かつ身体的に実行に移されていったので、実際、ECDもこの時期、従来のロックが欲しいままにしようとした生/性の同質性を拒否する方向へ向かったパンク/ポスト・パンクの日本のアーティストたちと知り合い、彼らのパフォーマンスを目撃する。
『ロッキング・オン』に岩谷宏主催の読書会が催されるという知らせが載り、僕はその会場である、岩谷宏の自宅のあった立川の団地の集会所を訪ねた。そこで同席したのが山崎春美だった。山崎春美については七六年に創刊された『ロック・マガジン』に寄稿していたことでその名前だけは知っていた。もちろん、岩谷宏の顔もそれまで全く知らなかった僕は、岩谷宏よりも先に会場に来ていた山崎春美を見て、これが岩谷宏ではないのか、と早とちりしたのを覚えている[17]
何が読まれたのかはっきりしないこの読書会の後に彼から誘いの電話がかかってきて、『ロッキング・オン』では例外的なイデオローグ岩谷宏の結成した劇団にためらいなく彼は参加する。また、パンク・シーンに足を突っ込むことで、主に吉祥寺のマイナーという場で「ミュージック」そのもの「民主主義」を問うそのものであるはずの――そうではなくては何か――自らの肉体を捧げて行われる儀式めいてと今からは思えてしまう無数の演奏会や、彼らとも繋がりのあった『JAM』や『HEAVEN』といった地下出版の周囲に作りあげられた密やかなネットワークの遭遇していく。
[1] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p. 53。
[2] 同前、p. 54。
[3] 同前。
[4] 同前。
[5] 同前。
[6] 同前、p. 55。
[7] 同前、p. 56。
[8] ECD『何もしないで生きていらんねぇ』本の雑誌社、2011年p. 218。
[9] 同前。
[10] 同前。
[11] 同前、p.166。
[12] 同前。
[13] 同前、p.167。
[14] 同前。
[15] 同前、p.168。
[16] 同前。
[17] 『いるべき場所』、p. 58。