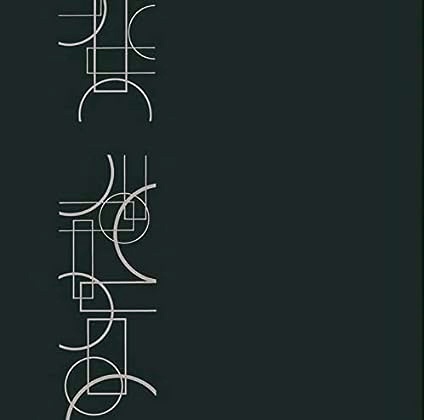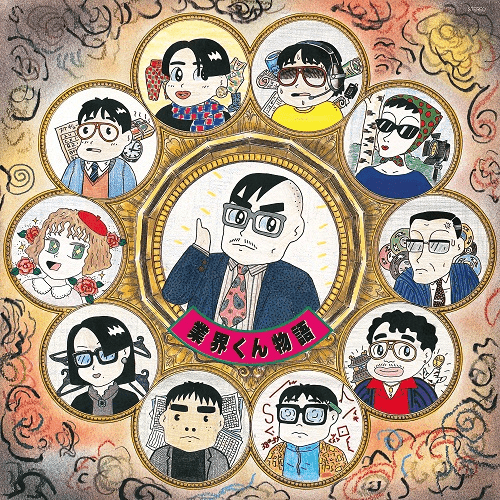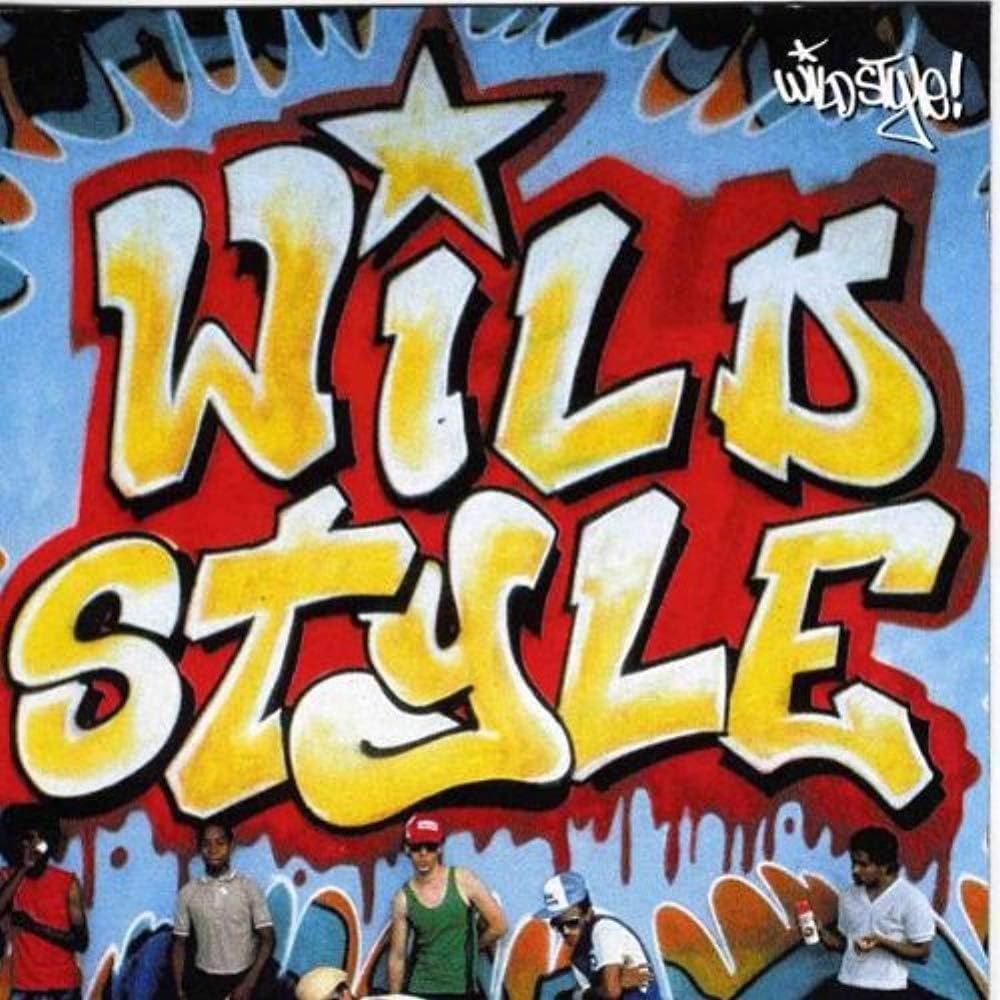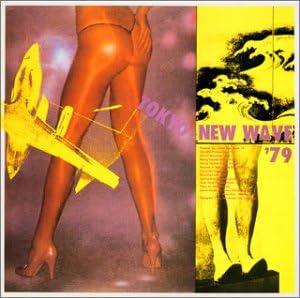世代間闘争よろしく岩谷宏を追い出すようにして始まったECDを含む10代の子供中心による演劇の活動は、まずなによりも代理店の社員がプロデュースを引き受けて経済的な支えの目論みも当初あって、なんと、断続的にだがその後10年にわたって続いていく。その最初の数年間、ECDはといえば「学校に行く時間には何かしら劇団関連で動いて」[1]、夜になると山崎春美の紹介で劇団に入ってきた彼の友人、山本哲に「連れられて、赤坂や六本木で遊んでいた」。
キラキラ社としての最初の公演は七八年の秋に新宿のディスコ「ツバキハウス」で行われたと記憶する。この公演で美術を担当したのが〔註:劇団をプロデュースしていた代理店〕「マーケティング・コンビナート」の社長、今井俊博氏の実弟で、日本のアンフォルメル画家として著名な今井俊満氏だった。[2]
今井アレキサンドル(通称アレキ)もまた劇団に出入りし始めていた。アレキはロンドンでデヴィッド・ベイリー〔註:ECD原文ではマーク・ベイリーと記しているが間違い〕の元で修行してきたという写真家志望だった。[3]
当時、山本には都内の有名私立女子校に通うガール・フレンドがいて、そのガール・フレンドの友達の女子高生たちのグループもいつも山本の周囲にいた。いつの間にか彼女達は「マーケティング・コンビナート」にも出入りするようになっていた。彼女たちは僕たちが劇団の用事が終わるのを待っていて、用事が済むと一緒に赤坂や六本木のディスコに繰り出すのだった。初めて行ったのは、山本も彼女たちも一番のお気に入りだった赤坂のビブロスだ。[4]
その頃、ビブロスに集まっていたのはサーファーが多かった。山本はさすがにサーフィンはやらなかったが一緒に行った女子高生の中には朝までビブロスで踊ってそのまま海へ向かう子もいた。ビブロスではロックがよくかかった。エリック・クラプトンの「コカイン』は必ずかかったし、何より僕たちキラキラ社のメンバーがうれしかったのは一晩に一回は必ずロキシー・ミュージックの「ラブ・イズ・ザ・ドラッグ」がかかることだった。イントロの車のドアを閉める音が聞こえると僕達は争うようにフロアへ飛び出して踊った。六本木のスクエア・ビルにあった黒人客の多いディスコに行くこともあった。僕は黒人が踊る後ろにピッタリ貼り就いて、そのバネの効いた踊りをマスターしようとしたりした。[5]
「「マーケティング・コンビナート」は若者の消費動向を調査することも重要な仕事」[6]だったのでECDたちは鍵を預かって好き勝手に出入りして「ディスコで遊んだ後に皆で朝まで仮眠」[7]したり、「社員がいなくなる深夜に集まって酒盛りすることもしょっちゅうだった」[8]また、高校にも行かずに、彼は「TV中継が入る歌謡ショーなども手懸けて」[9]いた照明のアルバイトを通じて「沢田研二や山口百恵など当時、第一線の歌手をバック・ステージで間近に見る機会も多かった」[10]という。
印象に残っているのは小林旭だ。出演直前まで舞台袖でゴルフの素振りをする白いスーツ姿の巨大な背中は化け物のようだった。[11]
2001年、アルコール中毒の離脱症状から文字通り生還したばかり、覆いかぶさった苦しみの記憶が生々しく残っているはずの時期の取材で、ECD は1970年代の終わりを振り返って次のような言葉を遺している。
「高校を辞めたときから、普通でないなにか一歩踏みだしたわけですよ。まっとうな生き方を拒否して踏みだした、それは一生貫かないと」[12]
その少しばかり芝居がかったトーンのせいなのか、読者はこれらの言葉を目にして、彼が自分の周囲で巻き起こっていた事態を正確に把握していたのかどうかその判断に困惑する。このインタヴューまでの年月も経ているとしても、彼が自分の責任であることを引き受けているようで自虐的にだがその実エゴセントリックで――そこでは論のすべては抽象に過ぎる。そのことを実は彼も知っているからこそ、この言葉の指し示す「普通でない」という領域も、特段彼にとって見知って安心できるわけではないことが匂わされる。現実には、ここに滲み出ている子供じみた自己耽溺が失った社会へと向かう美学を一から改めて構築するために、その生涯の後の方に彼はポリティカル・アクティヴィズムへと向かうだろう。
それにしても、「普通でないなにか」とは――高校にも行かず、バイトをしながら、酒を飲んでは詮なき芸術談義と都内私立女子校生のグループと六本木のディスコで朝までの戯れに時を費やすことか。それとも、例えば、彼自身にも定かではない、吉祥寺マイナーで観たという、劇薬の過剰摂取の眠れない続きのなかぽかっと或る晩のみに見てしまう夢のような、光束夜のライヴの途切れかかった記憶だろうか。
「速度をもっと速くもっと速く」と繰り返す女性ヴォーカルは確かに吉祥寺マイナーで聴いたものだ。僕がこの時期の光束夜を観たことがあるのは間違いない。そして、シンセサイザーを揺さぶるように痙攣しながら演奏する男の姿は、僕が吉祥寺マイナーを思い出そうとする時、最初に浮かぶ光景だ。[13]
しかもそれが光束夜なのかそれとも白石民生なのか、ECDにはその最後まで確かではない。数えきれないほど繰り返して聴いたというNOISEの『天皇』や『愛欲十時人民劇場』というアルバムも、「かなりのライブを観に」[14]行ったはずの吉祥寺マイナーの様子も彼にはとても覚束ない。
そのうえ1978年に開店したばかりの、マイナー自体さえも瞬く間に変貌していかざるをえない。既に1980年、無数/ひとつの歌の実践にいそしむA-Musikの竹田賢一はこう記している。
マイナーが開店した当初は、壁には絵の額が飾られ、卓上には花が置かれて、カレーの味を誇る(?)小綺麗なジャズ喫茶だった。それが数ヶ月後には、かかるレコードも“ニュージャズ、現代音楽、プログレッシヴ・ロック等の周辺”となり、自主コンサートに場所を提供しはじめる。もちろんコンサートの際は、テーブルなどが邪魔になるので、壁面に積み重ねられたり、廊下へ運び出されたりする。その情景が、ジャズ喫茶としての“マイナー”の解体の始まりを告げていただろう。以後、コンサートやワークショップの比重はどんどん高まり、レコードがかかるのはそれら合間のレコード・コンサートの時ぐらいになり、演奏の役に立たないテーブルや椅子やカウンター、厨房は次第に破壊され、いつしか“マイナー”は“フリー・ミュージック・ボックス”と自らを規定するようになった。[15]
光束夜の音楽は狭義の意味でのパンク・ロックではない。ただ、巨大な産業になってしまったロックを自分達の手に取り戻そうとしたのがパンクだったのなら、当時、吉祥寺マイナーで演奏していたバンドは全てパンクだったと言える。[16]
マイナーも解体されていくうちに現実から無くなってしまったではないか。ならば、巨大な産業になってしまったロックのどこが悪いのか。彼の精神を病んでしまった挙句に亡くなってしまった母親によるなら、いくら大規模になっても、つまるところ「チンドン屋のようなもの」だからかも知れない。
僕は引き裂かれていた。バイトでは華やかな芸能界をのぞき見ながら、そんな世界とは全く無縁な吉祥寺マイナーに出入りする。そして、自分がいる劇団は、そのどちらにも向かおうとしているのかもわからない。その中途半端さにひとりでイラ立っていた。〔……〕自分はといえば、役者というものになりたいのかどうかさえもはっきりしない。ただ、公演を重ねるうちにモノを作ること、表現することを自分の仕事にしたいという欲求はたかまっていた。そして、それは演劇などではなく、やはり、音楽を通してかなえたい、という思いが強くなっていった。[17]
ECDが2015年に発表したアルバム『THREE WISE MONKEYS』に収められている”1980”にこんな一節がある。
そうさ、俺はウォークマンの発案者でもある。17(歳)のある日考えたアイデアをイラストに描いた/とある確かなルートを使い間違いなくSONYに届いた
その3年後の1980年、彼が二十歳になった際に世界で初めて商品化された携帯用カセットテープ再生機、ウォークマンが発売されたのだと彼は主張する。ウォークマンを発案したことは、繰り返し彼の小説やエッセイに登場する。
ヘッドフォンで音楽を聞くことに特別の価値を見出していた僕は〔……〕スピーカーを搭載しないヘッドフォンだけで音楽を聞く新しい形のラジカセの想像図を描いたこともあった。〔註:小型の携帯用カセットテーププレイヤーは存在しなかったので〕実際に大きなラジカセを抱えて外出し、電車の中でヘッドフォンで音楽を聴くということも実験済みだった。車窓を過ぎ去る見慣れた光景が映画の一コマのように現実感のないものに変った。[18]
彼は公衆のうちに紛れながらヘッドフォンでひとり音楽を聞くことを心待ちにしていたことは確かだ。ちなみに、ECD がウォークマンで聞いたカセットのうち一本は「ジャックスのライブのテープだった。それはファン・クラブ向けに四〇〇枚だけプレスされたというレコード「LIVE 68.7.24」からダビングにダビングを重ねて何人もの人の手を経たテープだった」[19]という。このような人間が当時どのぐらい世界にいたのだろう。
雑誌『 HEAVEN』が創刊され創刊記念イベント『天国注射の昼』が新宿ACBホールで開催された。この年、キラキラ社も同じACBホールで公演を打っていたが、僕はこの種のライブにキラキラのメンバーと一緒に行くことはなかった。僕はACBホールでステージでのたうち回る春美の姿を観ながら、改めて、やはり自分には芝居なんかよりこっちの方がいいのだ、と思い、焦燥感にかられた。[20]
そんな積み上がっていくような息苦さのなかで、ECDはこんな言葉を母が口にするのを聞いた。
「『クレマツの家から出た者が、そんなチンドン屋のようなものになるわけがない』
あれは僕が二〇歳を過ぎた頃のことだった。久々に家に帰った僕を前に、母が独り言のようにつぶやいた。僕がいまだに劇団に関わり、役者をやっていることを言っているのだ」[21]
「十五の時に、僕は入ったばかりの高校を辞めると宣言した。父は反対したが、母は理解してくれた。母は僕の味方だと思っていた。だから、ふいに聞こえてきたその一言は衝撃だった。〔……〕母の言葉が正しいことは自分でもわかっていた。人前で歌ったり踊ったりするようなことが自分に向いているとは僕も考えていなかった。それはラッパーになってからの今に至るまで変わっていない」[22]
内職をしていた彼女が軍国主義的映画の主題歌のほんの一節を口にしていた、そんな彼の幼少時の記憶のなかでのみ、ECDは唯一彼女と音楽/アートを結びつけられる。ゆえに母親に音楽的な知識も関心もないことは彼も了解済みのはずだが、彼は彼女と自分が切り離せないか、少なくとも自分と母親を切り離せるかどうかについて逡巡し、30数年にわたって苦しみ自らを責め続ける。
「チンドン屋のようなもの」と半ば自身に言い聞かせるような聞こえよがしの嫌味を狭い畳の部屋でECDの母親がふっと口に出した頃、既に彼女の精神状態は通常ではないこと傍目にも明らかで、その2年半後、その心臓は発作的に止まる。そのことを彼は考え続ける。どうすれば、母の死を前に自分が「チンドン屋みたいなもの」、それで生計を立てている訳もないのは明瞭な「みたいなもの」を正当化できるのだろう。そのいったんの答えさえも、母の死と同年の1983年、雑誌『ロッキング・オンの誌面にECDがヒップホップを発見するまで先延ばしされるだろう。
[1] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p. 69。
[2] 同前、p. 68。
[3] 同前、p. 69。
[4] 同前。
[5] 同前、p. 70。
[6] 同前。
[7] 同前。
[8] 同前。
[9] 同前、p. 79。
[10] 同前。
[11] 同前。
[12] 「言葉の爆弾を投げ続ける孤独なテロリスト ECD INTERVIEW」『BURST 6月号』コアマガジン社、2001年。
[13] ECD『何もしないで生きていらんねぇ』本の雑誌社、2011年p. 100。
[14] 同前、p. 13。
[15] 竹田賢一『地表に蠢く音楽ども 竹田賢一音楽論集』月曜社、2013年、 p. 359。
[16] ECD『何もしないで生きていらんねぇ』、p. 98。
[17] ECD『いるべき場所』、p. 81。
[18] 同前、p. 82。
[19] 同前、p. 82。
[20] 同前、p. 84。
[21] ECD『失点・イン・ザ・パーク』太田出版、2005年p. 109。
[22] 同前。