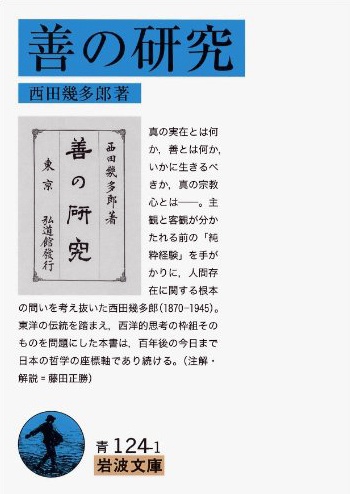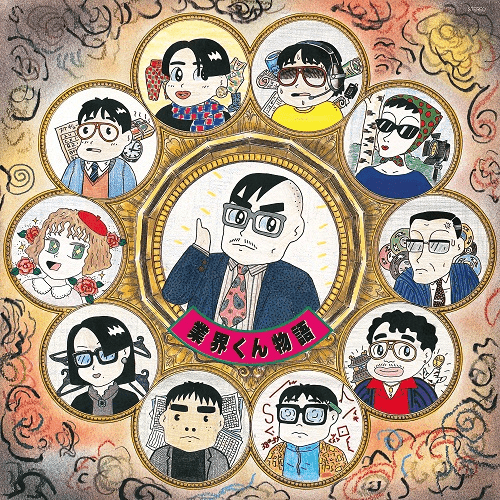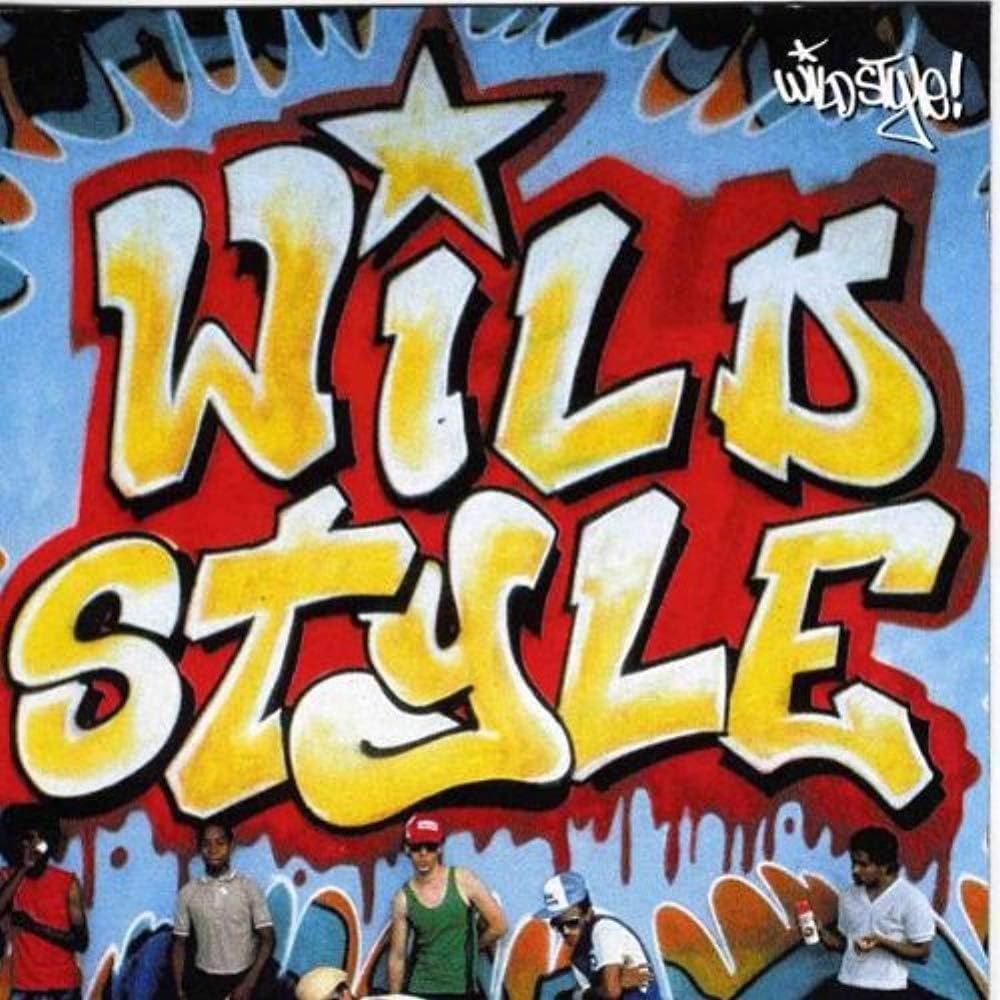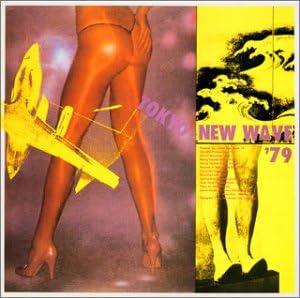ロックを聞くようになってから孤立したのか、孤立を感じるようになったからロックにのめり込んだのか、それはわからない。 [1]
ロックとは商業的な都市の余暇のことだ[2]、と前回の終わりに紹介したポップ音楽研究の古典的な『サウンドの力』でサイモン・フリスは事態をはっきりさせようとする。1950年代以来、未曾有の商業的なポテンシャルが確認された労働者階級の働き手とその予備軍たるティーンたちの手にした余暇という限界付き“自由”は、当然、彼らがその時間を得るためにどうしてもしなければならない単調な労働及びその体験への批判的な面を持つのだという。
「何をするにも行動はいつもひとりだった」[3]「そしてロック・ファンは皆、自分と同じように孤独だと『ロッキング・オン』は教えてくれた」[4]という当時のECDの思いは、フリスによると彼が実は独りだったのではなく将来の労働の担い手としてまた消費者として期待される彼ら労働者階級の少年の成長する時間が持つパラドクス、すなわち、自由の知覚が孤独の知覚の引き剥がせない裏返しになることに根差しているのであり、ロックはその思いに応答するアートであったとの結論にいたる。
1960年代半ばのロンドンを舞台とした映画『さらば青春の光』で描かれたように一週間の退屈な労働が与える彼らの余暇の時間と金のためにありとあらゆる商品が用意され始めた時代、ロックのアーティストは若くして「人生に勝利したことを見せびらかしている」存在として姿を現す。若いリスナーたちのロックを聴くという行為は、到底ありえそうもないが実際に起こっている同世代か少しだけ年長のスターたちが手にした“勝利”を自分の部屋から仰ぎ見ながら、自由/孤独のパラドクスの“フィーリング”自体を身体的な快楽に火をつけるエロティシズムをもって強化する経験である――ヘンリーカウの創始者として知られるフレッド・フリスの兄弟である著者が、ロック・バンドを経て博士号を取得して著した『サウンドの力』は、ロックという形式のアートの魔術的な力を過不足なく描写しながらその中心に位置する複雑に絡み合ったメカニズムをひとつひとつ解き明かしていく。
しかし、この多面的に獲得された類まれな成果を読み進めていくとフリスのひとつの態度に気がつくのは、その後の彼の著書も含めて検討してのジャッジでなければフェアではないとしても、1960年代半ばに興ったロックがリズム&ブルーズをはじめとした“ブラック”ミュージックに多くを負う歴史を政治と社会の連なる文脈においても紐解きながら、ここではとうの“シーン”で起きていた奇妙だが見逃せない矛盾には触れないということだ。すなわち、ロック・ミュージシャンの多数が“ブラック”ミュージックに尊敬の念を示しながら、同時にせっせと励んでいた “ピン撥ね”は『サウンドの力』を通して事実上無視されている。
1960年代のブルーズの流行をその好機として巨大な名声を獲得したエリック・クラプトン、ロッド・スチュワート、ローリング・ストーンズなどなど、ECDにとっても親しみのあるロックの巨人たちの“アート”の多くは、創造においての窃盗行為の結実との際どい境界線上に成立していた。1970年代のチェス・レコードのレッド・ツェッペリンへの訴訟以来、ロックの初期の成り立ちと文化的窃盗は分かち難く、レッド・ツェッペリンの歌詞の数多くはメンバーのロバート・プラントのお気に入りのブルーズ・ミュージシャン、ウィリー・ディクソンの歌詞からの“戴き物”であるし、ローリング・ストーンズについてのバディ・ガイの「彼らは自分の音楽を盗んだ。しかし、彼らが自分に自分の名前をくれたんだ」と諦念のこだまする悲痛な呟きは広く知られている。
同時に思い出すべきはノーベル文学賞受賞者ボブ・ディランが盗作の疑いで非難された際に「引用は豊かであり、伝統を豊かにする」と機嫌を損ねての返答であり、疑わしいとされた彼の行為がフォーク・アートの伝統に根差すことを指摘しているのだし、プラントの「成功した者だけが咎められる」との口吻の意識もその近くにある。ちなみに、その成功とは自家用ジェット機でのワールド・ツアーという規模の成功であり、そのビジネスのスケールとサイズは彼らが敬いながらその成果を“咎められなければ”と頂いたブルーズ/リズム&ブルーズ・ミュージシャンたちの舐めた辛酸といかにもな不均衡を誇る。
国ごとに異なっていて、誰がどのような権利を持っていて、それに従って利益を誰にどう分配すべきかを定めた法制度が現実の裡に実際どう働いているかという議論のないまま、フリスの『サウンドの力』においての態度をとりあえずここで持ち出すには幾つかの理由がある。
そもそも、ロックというアートが私たちを魅了する過程の経験“そのもの”を強化するエロティシズムとして作動する間、点けられた火の揺らめきが見えるとしてそのひとつの向こう側へまるで『鏡の国のアリス』のように通り抜けるなら、そちら側にあるのは現実の社会の裡にアート化されたロックの大部がどう構築されているかのダイナミクス、音楽というかけがえのない個人的で秘密の領域から遥か遠くに感じられる「政治」へと変わり果てたその姿であるということだ。もちろん、現実の裡にさまざまな方向へそれぞれに作用する力のありようを私たち「政治」と命名してもすべての音楽とそれを聴く経験をそこへ従属する、その襞が映されたものでしかない領域に貶めることは叶わないし、音楽経験を「政治」に“直接”従属させようというその想像力そのものが「政治」によって位置づけられいるだろう。
アリスの鏡のどちらの側にしても、革命を忌避しサブカルチャーに流れこんでいった“ロック世代”自身によって解釈が施されていたのだというのフリスの指摘は以前も記したが、その事情は“焼け跡世代”に属した『ニューミュージックマガジン』の中村とうようや“ブラック”の“ブルーズ”中心に扱っていた日暮泰文の『ザ・ブルース』のあとに創刊された、日本での『ロッキング・オン』の渋谷陽一にしてもまた戦後の軽音楽雑誌から1970年代にロックへと移行していった『ミュージック・ライフ』を率いていった水上はるこにしても例外ではなかった。もし音楽が政治であるなら、彼らの、そして私たちの想像力が現実の「政治」の裡に限界づけられているからに他ならない。
「14歳だった僕はまさしく未成年教唆される側であった」と『ロッキングオン』に掲載されていた「ロックやロック・アーティストに対する観念的な考察」「難解な文章」[5]にECDが大きな影響を受けたという。金と名声を追い求めラッパーになり世に出ながらも2000年代には“アナーキスト”を自認しポリティカル・アクティヴィストとなって倒れた彼に、初めて“サウンド”の経験を強化する悦楽から他領域へと逸脱していく解釈を与える立派な“書かれた”言葉は、こうした新しい世代のロック・ジャーナリズムによって発信されたもので、このようにその熱心な読み手のアートの知覚のありようを方向づける。
非合法な出版物でも手にしているかのように興奮した。[6]
「世界を変えろ」と言われて、自分に何ができるのかそれを見つけることが人生最大のテーマになった。試験勉強のために利用するようになった市立の図書館で、自然農法の本を見つけて読み、西田幾太郎の『善の研究』を読んだ。デビッド・ボウイの兄が船乗りだったというエピソードから飛躍して、長い航海の間、船員達を飽きさせない食事を提供するコックになることを夢想した。やがて船に乗るかはどうか別として、食に関する仕事で世界を変えるというアイデアはついに自分の進路を左右するまでになっていく。[7]
一方では、三島由紀夫が切腹によってパブリックかつポリティカルな場で自らの命を絶ったことや、もしくはもう一方では視覚的にも衝撃的なテロリズムの連続が曖昧に記憶に残され、なによりも“日本株式会社”という言葉が生まれたほどの日本の経済のありえない好調が多くの人々に“ノン・ポリティクス”という視点から世界を支持していくことを可能にした1970年代半ばに、解決すべき問題としてひろく流通し始めたのは環境問題であった。19世紀の足尾銅山鉱毒事件とも結び付けられる垂れ流された有機水銀の大量摂取による取り返しのつかない悲劇水俣はメディアによって伝播されていたし、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』の悲観的なトーンが人々の暮らしへと浸透していったときでもあった。
ならばこの時代に彼が読んだという『善の研究』が日本を太平洋戦争へ導くのに利用された“京都学派”の成果であること、また自然農法が右翼的なイデオロギーの観点から人々に支持されていることを知る人も多いだろうが、当時の彼が保守の思想に近いのかもしくは左翼的なリベラリズムと与するのかではなく、むしろ、ここでは中学生の石田少年がその契機はなんであれ、その齟齬が揶揄さえされていた理論という“書かれた”言葉と現実社会での“実践”をなんとか具体的に結びつけようとしていたことにより注目してもいい。
父の仕事を継ぐという将来も選択肢の中になかったわけではない。夏休みには自分から望んで、父の仕事の現場の下働きに出させてもらったりもした。[8]
ECDは父親の運転するダットサン( 筆者註:1986年まで日本国内でも生産していた日産自動車のブランド)に乗せてもらって現場に行き、大工の見習いとして働くこともあった。
大工のグンちゃん達と同じ現場で一緒に働くのは自分にふさわしい姿ではないかと心休まる思いがした。三時の一服で煙草をきらして買いに行くグンちゃんについてゆく。大きな屋敷の灰色の高い堀を指差してグンちゃんが「こんなところに住んでいる奴はどうせ悪いことをしているに決まってる」と言う。僕は黙ってうなずいた。[9]
石田家も6畳の家から引っ越していた。最低限の生活がどのように保証されるかどうかは既に過去の問題と目されつつあって、つまり都市部において目につく貧困は少しずつだが確実に取り除かれ公害のような問題は周縁ににしかなきものとされる流れが出来上がりつつあるなか、新しい余暇と消費の可能性は人々にラディカルなアイデア、例えば暴力革命による政府転覆ではなく中庸を良しとする社会の意識の拡りをもたらし、そのことが彼らに日本の外を向かせ、カウンターカルチャー/ニュージャーナリズムを追う雑誌『宝島』やアメリカの西海岸のライフスタイルをヴィジュアルに紹介するというコンセプトの雑誌『ポパイ』が創刊された時代。
ロッキング・オンの創刊メンバーの1人である橘川幸夫が回想するように「『ノンセクト・ラジカル』という言葉が広がってきて、政治的党派に所属しない個人の活動のゆるやかなネットワーク」[10]への「共感」の延長としてロックを解釈するその先に、マス・メディア/マス・コミュニケーションを基盤としてそれまでになかった空間と時間とその成員”ロック・ファン“が、まるで実際にはかつても今も訪れられてはいないが馴染みのある西海岸の風景のように想定され、その存在のあるべき姿の詳細がロックの教義として彼らの読者に教唆されるところへとつながっていった。
『ロッキング・オン』の少なくとも10年以上もの熱心な読者で、その記事を通じてヒップホップさえも発見したと書いているばかりか、ロッキング・オンに絡んだ劇団に役者として参加したECDのその後の歩みを追う私たちは、彼の芸術的達成の輪郭とこの『ロッキング・オン』の論理や倫理を決定的に分岐させるのは鏡の向こう側にあるポリティクスへのそれぞれの手つきであることを覚えておいていい。すなわち渋谷陽一が「ロックが常に歌=言語を音楽の中にとり込んでいった」[11]と記した解釈としての“書かれた”その言葉そのものが、一体どこの誰が誰に向かってなにを語っているのかを巡ってのダイナミクス、つまり「政治」の操作を意図したものであるということを。そしてまた、その際に政治の季節の終わりから次に来たるべき高度消費社会とテレビの時代を両手をあげて迎える言説を用意した評論家、吉本隆明が導入されたことも。
[1] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p. 36。
[2] サイモン・フリス『サウンドの力』細川周平、竹田賢一訳、晶文社、1991年、p. 103。
[3] 『いるべき場所』、p. 36。
[4] 同前、p. 37。
[5] ECD『暮らしの手帖』扶桑社、2009年、p. 19。
[6] 同前。
[7] 同前、p. 20。
[8] 同前、p. 22。
[9] 同前。
[10] 橘川幸夫『ロッキング・オンの時代』晶文社、2016年、p. 75。
[11] 渋谷陽一『メディアとしてのロックン・ロール』ロッキング・オン社、1979年、p. 66。