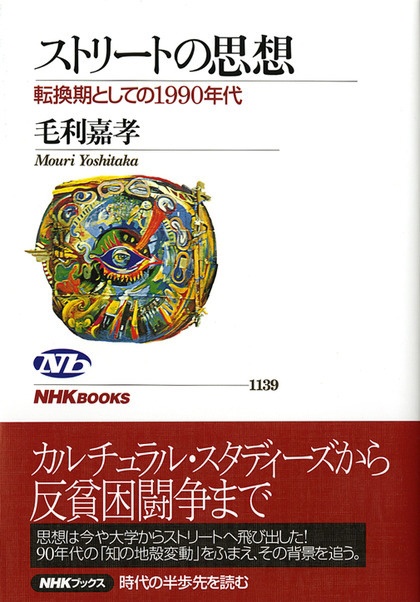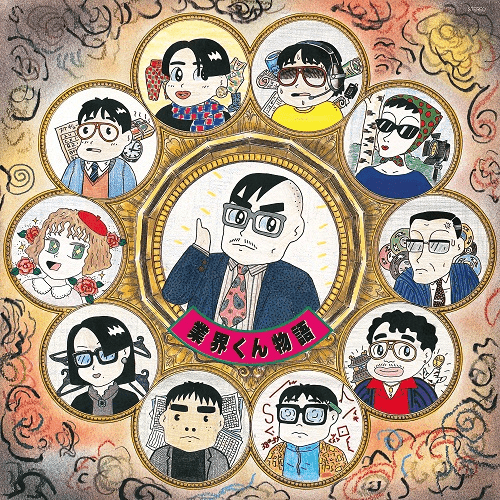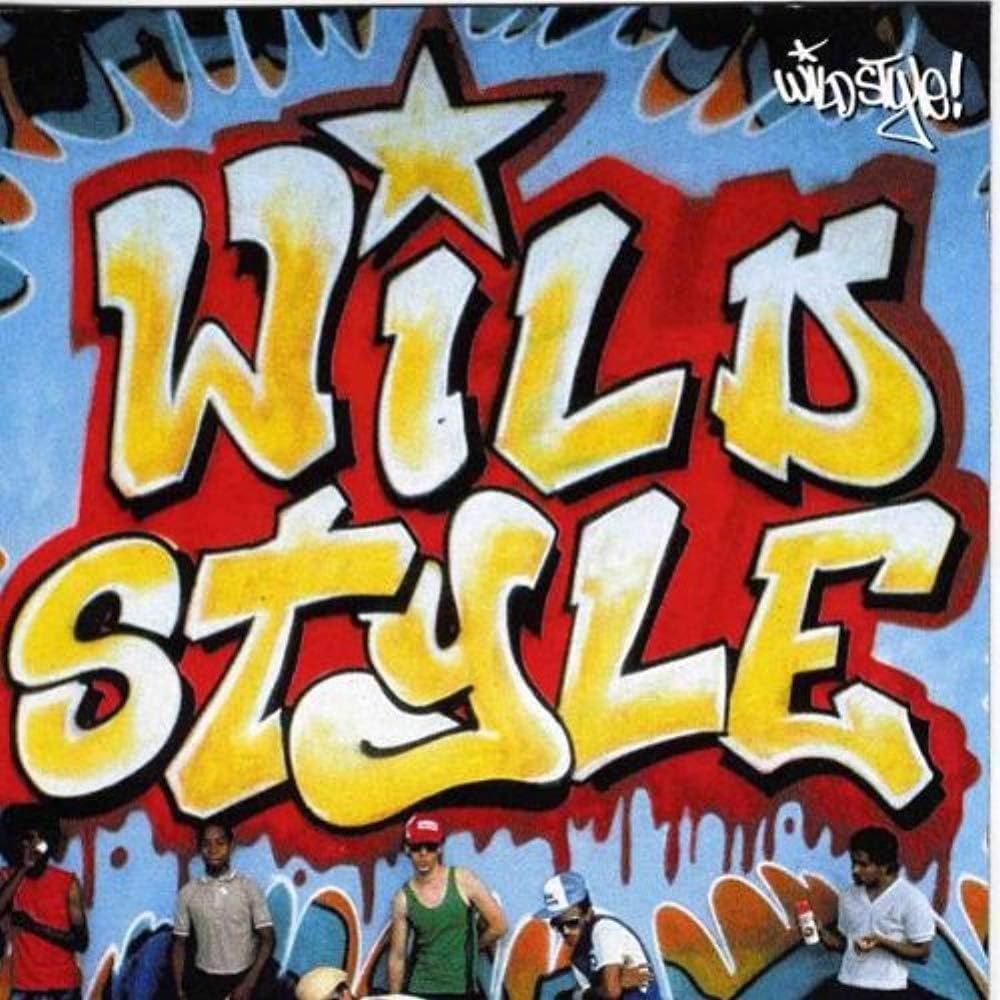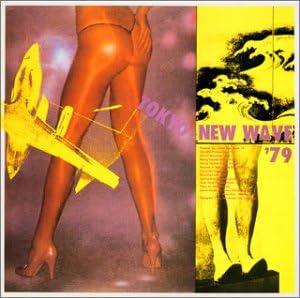昔々、あるところではなく日本で、「一億総中流」と住む人間の多くが自分たちを考えていたという。1948年から開始された内閣府による「国民生活に関する世論調査」では生活の程度を上・中・下、そして中を3つに、つまり中の上、中の中、中の下に分けたので、1960年代半ばにはこの調査に中流と答えた国民は8割を超えたという。実際には大きかったという地域における格差もその後の1970年代には縮小し、ニクソン/オイル・ショック [1]を経てなんと2003年までその格差は小さいままであったので、この状態にある“国民”の意識を「一億総中流」とマス・メディアが呼んだという。
「もはや、世界を変えるためのプランを優先すれば高校など行く意味はないはずだった」 [2]
31年前の14歳の自分がどのように将来を決めようとしていたかについて、当時既に45歳となっていたECDは雑誌 [3]に寄稿したテキストにこう要約した。事実と虚構がどのように混交されているのかが私たちには判断できないこの短編小説“独楽”を手にとって気がつくのは、現実の出来事がどう起きたかとも、また彼が14歳もしくは45歳のどちらの視点から彼自身の人生を見ているのかとも関係なく、世界を変えるためのオプションのひとつとして彼にとって恩恵であるはずの高等教育はその始まり以前から、彼自身の視域からは見えないものとして排除されているということだ。
1970年代からバブルの崩壊までの石田家が余暇のための余裕を持ちえたことと、ロックの熱に浮かされるようにしてECDの心がその奥深くに引き摺りこまれていった二つのことは、同じときの裡に起こった。東京の中心である23区の西側の端から少しばかり外れた、ECDには居心地が良くなかったという武蔵野の面影が依然として色濃く残っていた当時の平たい町並みの地域は、その後に発展しホワイト・カラーの住宅地として知られていくようになり、その街と同じように石田家もまた経済的にその頂点に向かっていて、彼の父親は自身で大工仕事をするだけでなく幾人かを雇う工務店を経営するようになっていく。4人の家族は中野の六畳間だけの小屋からその住宅地である吉祥寺の平家に移り、ECD が20代になる頃にはそれは二階建てに改築されていて、石田家は仕事用の車と余暇のための自家用車までを持てる余裕があった。
現在父が住んでいる吉祥寺の家は、実は僕が十歳から住んだ家ではない。中野から移り住んだ当時の家は六畳と四畳半の二部屋に台所、風呂場がある平家の家屋に、乗用車が一台入れば一杯という庭が付いた小さな家だった。この家を十年後、父は二階建てに建て替える。派手な造りでは決してないが、使っている建材ひとつとっても贅をつくしたものになっていることはシロウトの僕にもわかった。総檜造りの風呂が父の自慢だった。庭には白いBMWがあった。この頃が父の絶頂期だったと思う。さらにその数年後のことだ。その家の敷地の数メートル北側を新しい道路が通ることになった。家の北側にはアパートがあった。そのアパートに敷地の半分ほどが道路用地として買い取られ、アパートは立ち退くことになった。父は残された半分の土地を買い、そこに工務店の事務所を建てたのである。 [4]
しかし、中産階級の子弟が身につけるに相応しい教養たる学問もそのための経済的な前提たる余裕もまるでそこになかったかのように、数年前に中学校に入って校庭のスピーカーから響くビートルズの“ヘイ・ジュード”を耳にして「校庭で英語の曲が流れる。さすがは中学校だ。小学校とは違う」 [5]という感嘆の記憶をその後もずっと持ち続けた彼は、人生の方向を決定づけるほどに夢中になった曲のリリックが書かれた外国の言語を学ぶことも、もしくは、父親の会社の経営を助けるために役に立つであろう知識をつけることも自らの手で斥ける。
知の象徴としての本郷の時計台への自衛隊の放水のイメージを“マス”・メディアが延々と繰り返し流通させた時代のあとにやって来たポスト“68年”世代の目に、大学/高等教育の権威の失墜が焼きついていたということはもちろんあっただろう。しかし、義務教育を終えたECDは修士や博士号の取得は夢にも思わなかったどころか、まして目の前の高校に――1970年代半ばには日本の高校進学率は90%を超えていた――通うことさえにも嫌気でもさしているかのように拒否しようとしていた。
今、高校進学をしないなどと宣言したら一家は大騒ぎになるだろう。それを乗り切るだけの勇気はまだない。そんな心理状態だから、恐れたのは逆に自分のたくらみを父や母に悟られることだった。僕は父や母をあざむくために受験勉強に専念した。そして高校受験は成功した。第一志望の第34群に合格し都立石神井高校に入学することが決まった。僕は母が小さな大学ノートに日記をつけているのを知っていて、ときたまそれをこっそり見ることがあった。いつもは家計簿代わりに大きな買い物をしたことをメモしてあったりする内容なのだが、僕の合格について記されたその日だけは「義則、合格!!ヤッタ!!バンザイ!!」と鉛筆で書いた文字が躍っていた。母が「バンザイ!!」などと声をあげるのを聞いたことはない。合格を知らせた時にもホッとした顔はしたけれど「よかったねぇ」と言うだけだった。誰もいない家の中でひっそりと日記に喜びを記す母の姿を想像する。この時から僕の中に母への後ろめたさが芽生えた。 [6]
微熱を帯びたように『ロッキング・オン』雑誌を手にして岩谷宏をはじめとしたロックの文章に心酔し「デビッド・ボウイの兄が船乗りだったというエピソードから飛躍し」「自然農法の本を見つけて読み」、「やがて船に乗るかはどうか別として、食に関する仕事で世界を変えるというアイデアはついに自分の進路を左右するまでになっていく」とECDが当時を思い出していることは前に記したが、失われた革命から拡がっていったカウンター/サブカルチャーが生んだ“アート”についての世界有数の蒐集家/歴史家のヨハン・クーゲルバーグによると、食についての意識の転回こそが1968年が現在へ遺した最大の分水嶺だという。 [7]
世界戦争によって一旦破壊された経済はフランケンシュタインの怪物のように再生されて高度な消費主義へと私たちの地域――ヨーロッパから太平洋の両端まで――の人々を向かわせたが、その変化に伴って食の事情までもが二分化していったという。つまり、一方には女性の“社会進出”の事実とも関連してのいつでもどこにでも持ち運ぶことができるコンビニエントな食事のパッケージ化があり、もう一方ではカウンター・カルチャー由来の異国からの多様な食文化を導入しての全粒粉や大豆、新鮮な緑黄色野菜などオーガニック・フードの世界的な伝播である。
それにしても、彼の父親が“バケモノ”と形容したグラム・ロック期の異形のデヴィッド・ボウイに夢中になった少年が、ボウイの語ったほんの僅かなエピソードからヒントを得て自らの将来の職業を想像していくとき、世界を変えるためにその担い手たる、例えば、船員のように頭だけでなく実際に手や足を動かし働く人々の口に入り彼らの肉体と精神を作る食に着目したことは、その後のECDの生きていった時間と彼の膨大なアート作品のありようとも共鳴していく、目に見える意匠を剥ぎとっていっていくある種の鈍重な容赦のなさの萌芽がそこにあるようだ。
しかしながら、ECDの遺した“小説”の言葉の次のような一節を読むと、その萌芽は1970年代の日本の現実に絡めとられ閉ざされた視域に限定された風景の紡ぎ出す一見堅牢で平凡な日常のシーンへと、ひどくローカルに切り詰められ混濁していきかねなかったことを知ることができる。
三鷹に「江ぐち」というラーメン屋があった。カウンター席だけの小さな店だ。カウンターは檜で出来ている。客席側の角が丸くなっている。客の手が触れることで丸くなったようなその手触りが大好きだった。にこやかな笑顔を絶やさず、確実に注文を取る丸顔の親父ともうひとり、対照的にいつも仏頂面で麺の湯切りに集中する面長の親父、この二人の仕事ぶりに見とれていると、カウンターの後ろで立って待つ時間もちっとも苦痛ではない。こんな店を自分でもやろうと思った。 [8]
ECDの生涯というのものは“伝説的なラッパー”というメディアでの呼び習わしから一般的に連想されるものと異なり、彼はアメリカなど海外に頻繁に出かけていくことはなかった。彼の暮らした地域も杉並区の中野から始まり西方の武蔵野の吉祥寺へ、そして渋谷を横に見ながら南下しての渋谷区中目黒と再び世田谷/杉並へという、文化的にもローカルな特徴を保ち続けた歪な形をした四角形から出ることはなかった。しかしながら私たちが思い出すべきは、東京23区の西の端でもあるこの地域は遥か2000年代以降には「批評の運動化」 [9]を促した機軸となったということである。
いわゆるこの「ストリートの思想」が現実においての“ふるまい”によっての“出来事”もしくは“運動”として当初は決して多くない人々によって始められた時代の終わりに、まさに『ストリートの思想』と名づけられた書籍において――時代に注意するなら致し方ないネットへの言及部分はとりあえず措くとして――社会学・文化研究者の毛利嘉孝はその枠組みをはっきりさせるためにこう記す。
「ストリートの思想」と対照的なのは、「オタク的な思想」である。ここで、「オタク的」と私が呼んでいるのは、アニメやライトノベル、テレビゲーム、コンピュータやインターネットなどを中心に社会のあり方を論じる一連の若手批評家の議論である。ポストモダン理論をしばしば援用している点では共通の基盤がないわけではないわけではない。〔……〕「ストリートの思想」と「オタク的な思想」は、二つの点で対立している。ひとつは、同じく文化を参照軸にしながら、そもそも見ている「文化」が決定的に異なっている点だ。「オタク的な思想」が、アニメやライトノベル、ゲームを「文化」の中心にしているとすれば、「ストリートの思想」は、音楽やファッション、そして日常生活の経験――人としゃべったり、料理をしたり、歩いたりといった身体的な営み――をもとにしている。 [10]
典型的なラッパー像から少し距離をおいてみること自体が彼の芸術的な意思の拡張によって実現されていったことは間違いない。だからこそ、ここで私たちが辿るECDの57年間はよくある物語から逸脱し、どこかが“正常”とか“普通”などと人が呼びたがる何かから脱臼したように異なったうえで、しかし紛れもなく現生の充実した知と体躯のありようをも求め続ける。
例えば、それは経済的な条件をただ不問にするだけでなく、マイナスとされ否定的とされる貧困からの発想をむしろよしとして、互いに仲間となりうる人間を発見しそれまでになかったコミュニティを目の前の視域に現出させようとする「ストリート」の思想の実践の試みで、そこで泣いたり笑ったり酒を飲んだり愛しあったりするだけでなく、その人生の後半に彼が赴かねばならなかった「ストリート」の闘争の合間に1人でいることもできる場/サイトを構築する試行であったともいえる。
ここで“場/サイト”と記さざるえなかったのは、通常の「一億総中流」の世界ではそれが誰にでも持てると考えられていた「家」と呼ばれ流通していたイメージから少し外れる場合があるということに他ならず、戦後の焼け跡を忘却した東京にもその可能性がありうると彼自身が知り抜いていたからこそ、ECDは道路脇の六畳の実家だった跡地の草叢を訪れる「家」についてのあっけからんと悲痛が放り出されている短編『中野区中野1-64-2』においてそれを描かねばならなかったのである。
ECDの試行は音楽でも、文学でも、ストリートの政治的アクティヴィズムでも、多くの人々がマイナスをプラスへ戻そうとする徒労の過程においてせいぜいゼロに近づけて終わるのと対称的に、そうした、まさしく想像力の貧困から生み出される慣習とがんじがらめになって身動きのとれない物言いそのものを現実から解放することによって、返す刀で現実をも断ち切るダイナミクスたらんとするものであり、ゆえに彼は自分が遺していったテキストをノン・フィクションともドキュメンタリーともルポルタージュとも呼ばず、小説と呼んだのだろう。そのことを想像力における鈍重な容赦のなさとここでは呼ぶ。
[1] 1972年から74年、また1979年にイラン革命の際に石油価格が高騰した第二次オイルショックもあった。
[2] ECD『暮らしの手帖』扶桑社、2009年、P. 23。
[3] 文芸雑誌『en-taxi』扶桑社、2006年。
[4] ECD『他人の始まり 因果の終わり』河出書房新社、2017年、p. 11。
[5] ECD『暮らしの手帖』、P. 17。
[6] 同前、P.23。
[7] 2014年、筆者へ本人談。
[8] ECD『失点・イン・ザ・パーク』太田出版、2005年、P. 111。
[9] 『ゲンロン 4 現代日本の批評』株式会社ゲンロン、2016年、p. 111。
[10] 毛利嘉孝『ストリートの思想 転換期としての1990年代』NHK出版、2009年、p. 25。