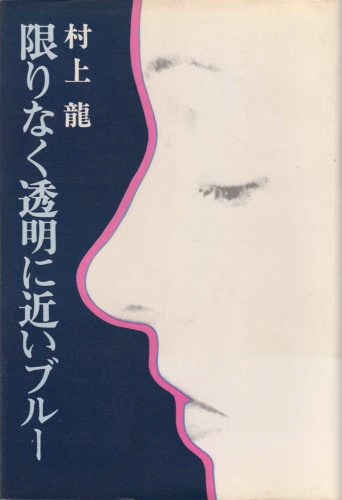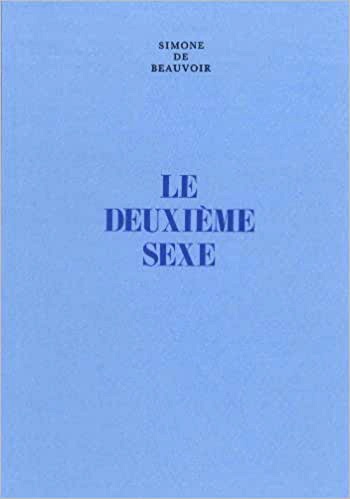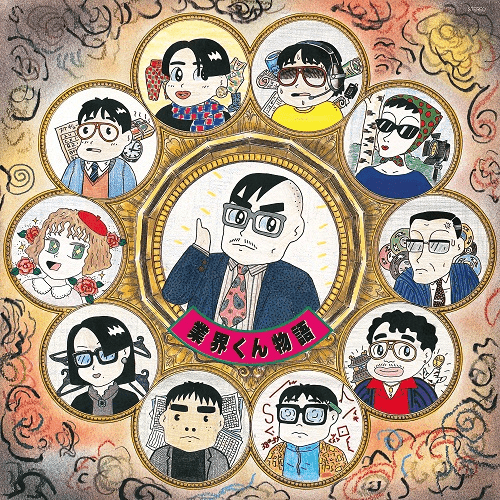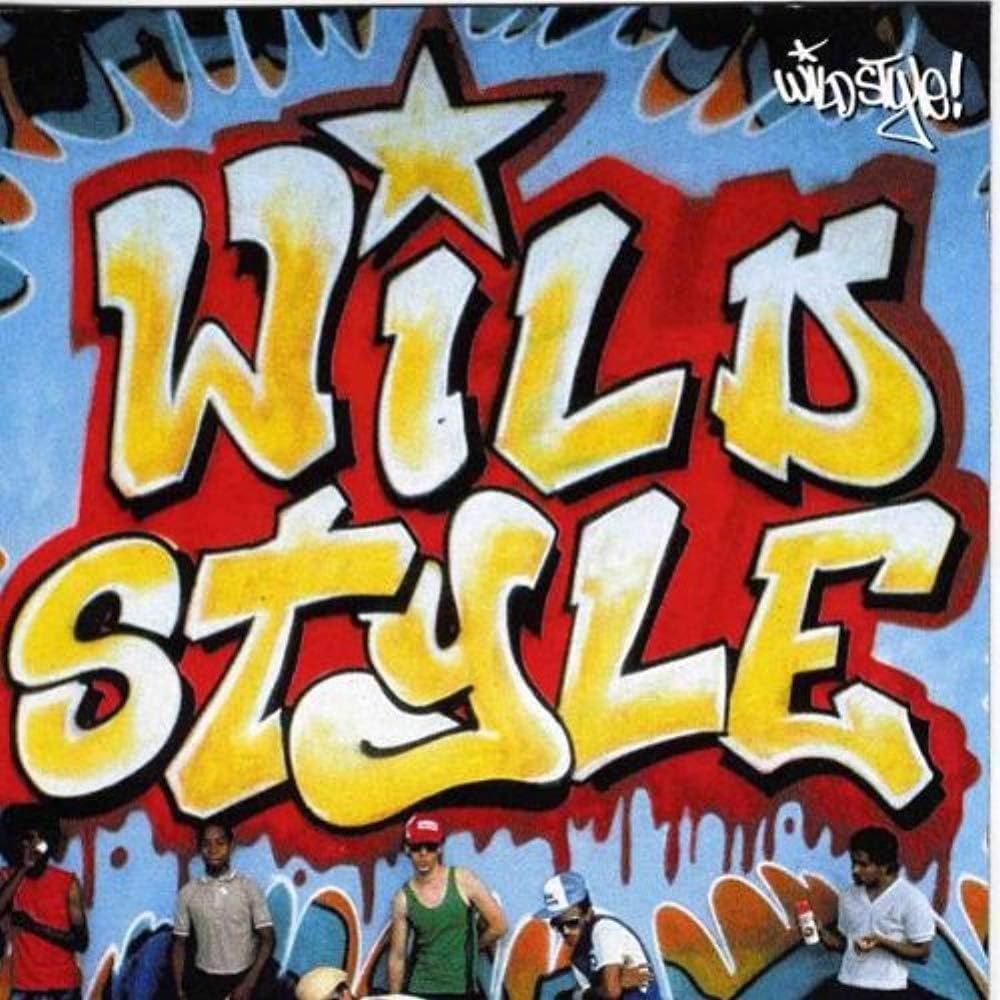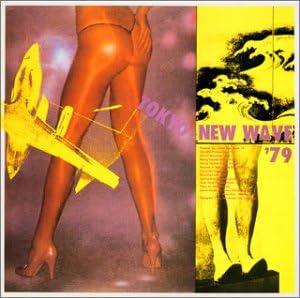ステージに現れたルー・リードは黒いTシャツにジーンズという、素っ気ないいでたちで化粧もしていなかった。グラム・ロッカーとしての姿を期待していた僕はその姿を見た時点で、これから始まるライブをどう楽しんだらいいかわからなくなっていた。 [1]
1975年、彼の地元の中野サンプラザでECDが間近に経験したルー・リードは、初めてのアジア、初めての日本においてのステージを派手な衣装も毒々しい化粧もなく、さして長くないセットで終えている。ロックンロールとポップ(音楽)からスペクタクルの要素を排してやってのけたわけだが、そのことは詩文がどうしようもなく持つ磁力に導かれながら、20世紀後半のアメリカの大衆社会の空々しさにその一員としての愛惜を持って臨んだアーティストにとって、ポスト・ニクソン時代の裡にありきわめて相応しい振る舞いだったといえる。
「みんなが軽くなった」という変換を1980年に振り返って指摘したトム・ウルフの利発でユーモラスなエッセイでは触れていないことがあり、それが武智鉄二の『黒い雪』や今村昌平の『日本戦後史 マダムおんぼろの生活』へもインターネットさながらに通じていくのは、民主主義の用意した時と空間の裡にいるのに忘れられたように扱われた人々と、彼らの暮らしとそこから生まれてくる芸術の形式へも関わっていくからだと、私たちはそのうち見ることになるだろう。
まさしくサイモン・フリスが書いていなかったように、革命的だったはずの「ロック」は「ポップ」へとあたかも何もなかったように白白と書き換えられたのだが、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとルー・リードがその書き換えを、まさにスキャンダラスにさえ響くことを厭わずに徹底して意識することで後進に大きな影響を与えたことは、リードの師がデルモア・シュワルツであると固有名詞を出すまでもなく、ヴェルヴェッツにしてもリードにしても、芸術の形式としてのポップ音楽の構造に敏感であり、書かれた言葉と歌われる言葉それぞれの歴史とそれらを形作ってきた主体の交わりや距離のありようはもちろん、言葉が紛れもなく私たちを腑分けするのだという事実を無視しなかったからである。
その同じ時の裡に小説――書かれた言葉の大衆的な発展――を発表し始めた二人の作家、村上春樹と村上龍が日本に登場している。
この二人の”ムラカミ”を巡ってのクリティカルな要諦が初心者にも部外者にも面白く分かり易く紐解かれている『ポスト・ムラカミの日本文学』を読んでいくと、当時、この”ムラカミ”に糸井重里、栗本薫、筒井康隆という名前を並べていくことで高橋源一郎の『さようなら、ギャングたち』こそが「優れた達成が無意識に踏まえられて」の「現在までのポップ文学の最高の作品だと思う」だとする吉本隆明の賛辞が紹介されている。
「ポップ」という言葉は、吉本隆明にとって、かつての「大衆」にかわるものでした。 [2]
日本文学『さようなら、ギャングたち』をここで評価しているのではない。そしてもちろん、吉本隆明は「日本」の「文学」のことを書いたので「アメリカ」の「ロック」について書いたわけではないだろう。しかし、「大衆」の「ポップ」への変換、すなわち吉本の「転向」への「こだわり」が可能になったのは日本独自の事情によるものではないこと、そしてまた同時にその事情の通用する範囲が実際には当時”ワールドワイド”から程遠くまだまだ限定された、いってみればルーラルな現象であったことは既に記した通りで、そのことへのリズミックであるばかりでなく、細やかにまっとうに誰かがやらねばやらなかったことを避けずに描いた村上龍の、例えば『限りなく透明に近いブルー』といった作品について、ここでは退化した読みがなされているとしか思えない。その読みを「ポップ」という合言葉が不透明に包み込み、そのことは日本の文芸批評の流れを読んでいくとしばしば出会う、批評家江藤淳の『限りなく透明に近いブルー』と『なんとなく、クリスタル』への異なる評価へも水平に手を結ぼうとする。
このように先行する文学を見習うようにしてロック世代は日本のポップ音楽を包み込むこと可能なマスターナラティヴを造作したことも記したが、忘れてはならないのはもちろんマスターナラティヴの当然といったしたり顔だ。しかしルー・リードのサウンドと言葉は、日本とアメリカで幾重にもジャーナリスティックに、つまり「大衆」もしくは「ポップ」的に置き去りにされ漂白された事実――すなわちロックに言葉があるのはブルーズに言葉があったからだというそもそもの始まり――を、アメリカの都市の暗部とされていたハードドラッグの常習者たちの暮らしぶりや我が物顔のヘテロセクシャルとは異なってストリートに存在する性の、つまり当時の「はずれ者」たちのありようを材料に「ポップ」や「大衆」からおためごかしの欺瞞が剥離される瞬間へ貫通しようとする。
ECDがローカルで目撃した”アンダーグラウンド・シーン”は、私たちが日常と受けとっている世界からそのまま降りていくことのできる下にある層のことではなく、「大衆」や「ポップ」という言葉が要求する抑圧に耐えかねるゆえにサウンドと言葉を契機に見つけることができる、ハリボテのように危うくも構築されている別の世界に移住することを決意し実際にそこに移住した人々の姿だったし、彼らの周囲に翻る影の華々しさではなかったか。
高校入学後に、急に少年であることをやめるように一足飛びに大人の世界とそれを支える制度に分け入っていくECDを追って、ここではその後の彼が飛び込んでいく総合芸術たる地下演劇と、そのことと関係がなくもない吉祥寺のマイナーというスペースに出入りする前衛的なミュージシャンたちのパフォーマンスに私たちは近づいていく。その少し前、ECDはずっと後の彼の人生にとっても重要である少女たちと出会う。そして少女たちにせよ成熟した立派な女たちにせよ、彼らは男たちに比べて明らかにECDのメモワールに記された世界において大きく重要な位置を与えられている。
受験を目前とした僕に、受験など吹き飛んでしまうような一大事が起こった。
七五年の年が明けて最初に出た『ロッキング・オン』誌上に「ROの会」発足の告知を見つけたのだ。「ROの会」は『ロッキング・オン』の読者同士の交流を深めるための機関で、『ロッキング・オン』の編集部が運営に関わることもないかわりに会費等もないということだった。入会すれば、会員として『ロッキング・オン』誌上に名前と連絡先が掲載される。会員はそれを頼りにお互いに連絡を取り合う、そういうことになっていた。僕は迷わず入会を決め編集部に入会申し込みの葉書を出した。そして、次の号の『ロッキング・オン』に自分の名前と電話番号、住所が掲載された。僕の会員ナンバーは確か十四番だったと思う。既に受験は終了し、僕は第一希望だった都立第三四群に合格して、四月からは都立石神井高校に入学することが決まっていた。そんなある日の夜、「ROの会」三多摩支部のコバヤシと名乗る男から電話があった。「ROの会」三多摩支部発足にあたりその第一回の会合を開くという知らせだった。会合当日は僕は中学の卒業式の日だった。僕は卒業式の出席を終えると、その足で、学生服を着たまま、八王子の会合会場へ向かった。[3]
中学では結局、ロックを聴く人間には二人しか出会えなかった。一年の時の同級生カワバタ君、三年になってクラスが一緒になったマサキ。マサキは『rockin’on』でも紹介されたスパークスの『キモノ・マイ・ハウス』をいち早く、手に入れていた。
「これ、本当にキスしてる音だよ」とチーチ・アンド・チョンの『ウェデイング・アルバム』というレコードをかけたり、プレイヤーの針がレコードに降りる音から始まるドイツのロック・バンド、ノイ!のレコードを聴かせて僕を驚かせた。マサキは変わった男だったけれど『rockin’on』には興味を示さなかった。電車に揺られながらこれから会う『ROの会』の人達を想像する。それは恐らくカワバタ君ともマサキとも違う僕が会ったことのない人種のはずだ。 [4]
会場に到着した時は予定の時間をもう十分以上過ぎていた。しかし、まだ何も始まってはいないらしい。会議用の長机が並べられたレンタル・スペースのその一番奥の窓際の席で女の子が三人並んで煙草を吸っている。[5]
僕の通っていた中学でタバコを吸うような連中は当時の呼び方で「ツッパリ」今で言う「ヤンキー」以外いなかった。しかし、彼女たちはそんな風には見えなかった。 [6]
僕はその三人組の隣に座った。他の人達はお互いに距離を置いてひとりずつバラバラに席に着いている。全部で十人ぐらいか。やがて、ハヤシと名乗るサングラスの男がホワイト・ボードの前で喋り始め、めいめいの自己紹介が始まった。何と、隣の三人組は僕と同学年だった。 [7]
お互いにその日集まったひとたちの中で最年少だと知った僕たちはすぐに打ち解けた。 [8]
次の週末、僕は再び八王子に来ていた。三人組に会うためだ。
「何だ、今日は学生服じゃないんだ」三人の中では一番の美人、アガワさんが僕を見るなり、そう言って笑う。「そりゃ、そうだよ。あれは卒業式から直行したからで」と言い訳しようとする僕をさえぎって、カトウさんが「学ラン、よかったよ。ショックだったもん」と助け船を出してくれる。「わざとじゃなかったんだ」とエノモトさんが大きな目で僕を見る。待ち合わせた喫茶店を出ると三人は「アサカワに行こうか」と歩き出した。商店街を抜け、広い街道を渡り、中心地から遠ざかる。アサカワは浅川という川の名前だった。枯れたススキが茂る土手を降りると大きな石が転がる河原が広がる。川の向こうには山並みが見える。四人はその河原を川上の方角へ歩いた。「あっちが私のうち」とエノモトさんが橋の向こうを指差す。土手を渡って橋を渡る。角にある交番の前を通り過ぎてからエノモトさんが言った。
「あそこのオマワリ、いつもうちを見張ってるんだ」 [9]
オノモト[10]さんは父親が共産党の活動家、アラカワさんは両親共に教師、サトウさんは両親のどちらかが韓国人だということだった。多少貧乏でも何の問題もない家庭に育った僕から見ると彼女たちはそれぞれに深刻な問題を抱えているように思えた。そんな彼女たちこそ自分がロックを通じて出会いたかった仲間だと強く思った。 [11]
次の週もやっぱり八王子にいた。京王八王子駅の近くにあるその店はまるで天国のようだった。元はスナックか何かだったのだろう。幹線道路沿いの一軒家。飲み物も食べ物も持ち込み自由、払うのは最初に入る時のチャージだけ。リクエストしてレコードをかけてもらって踊る。その日、僕は向き合って踊っていたアガワさんと初めてのキスをした。踊りながら自然に顔が近づいた一瞬、くちびるとくちびるが触れ合った。小鳥が嘴を合わせるような軽いキスだった。アガワさんは何もなかったように踊り続ける。終電で帰ってきた吉祥寺の駅の階段を降りながら柔らかいくちびるの感触がよみがえる。 [12]
そしてまた、偶然のいたずらにしては残酷すぎるけれど、この時期に彼の人生においてもうひとり、重要であるとまずなによりも彼自身が感じ考えていた女性、彼の母親の精神の均衡は蝕まれていく。
十七歳になった頃、僕の母親は明らかに精神を病んでいた。 [13]
家計を支える内職にいそしむ彼女が口ずさんでいた軍歌の切れはしがECDの音楽にまつわる最も古い記憶だという母親、お互いに困ることがなければ連絡をとらなかったという父親、二人の弟、彼の結婚した植本一子という女性、彼らの子供たち、もしくは話すことがうまくできなかった父親の兄(ECDの叔父)、この世を去った母親の代わりに家庭という空間に入り込んできた他人の女性との諍い、彼女の子供への異物感――ECDがこの世を離れていくその直前まで書き続けた小説やエッセイにこうした人々が生む波紋の織りなす模様が繰り返し顕れる。
例えば、女性は作られていくという過程の仕組みが隠された茂みの裏を追った『第二の性』を著したシモーヌ・ド・ボーヴォワールと想像力と、文学/政治の問題に取り組んだ哲学者/作家のジャン=ポール・サルトルのカップルをやはり思い起こしてしまうECDと植本との婚姻のありかたはそんな織物の模様のひとつだが、彼は彼の「家」もしくはそれを構成する人々という「家族」からアートやドラッグ(アルコール)や男たちを通じて一旦離れてしまったように見えても、「家」や「家族」それぞれのイシューは彼の頭のどこかにへばりついていた。人工衛星が逸れてしまった軌道にまた向かうプログラムが施されてるようにECDは何度でもそこへ戻っていったので、彼の記憶にあったはずの「多少貧乏でも何の問題もない家庭」は彼の10代の半ば以降消失し、その始まりから実にそれは「多少」の「貧乏」だったのか、もしくは「家庭」に「何の問題」もなかったかどうかさえもすこぶる怪しく両義的にすらなっていく。
[1] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p. 48。
[2] 仲俣暁生『ポスト・ムラカミの日本文学』朝日出版社、2002年、p. 50。
[3] ECD『いるべき場所』、p. 44。
[4] ECD『暮らしの手帖』、p.25、扶桑社、2009年。
[5] 同前、p. 25。
[6] ECD『いるべき場所』、p. 44。
[7] ECD『暮らしの手帖』、p. 25。
[8] ECD『いるべき場所』、p. 44。
[9] ECD『暮らしの手帖』、p. 26。
[10] エノモトさんとも記される。ECDの遺した文章では実在の人物の名前は常に少しずつ変えられている。アガワさんはアラカワさんとも記され、サトウさんはカトウさんでもある。
[11] ECD『いるべき場所』、p. 44。
[12] ECD『暮らしの手帖』、p. 26。
[13] ECD『他人の始まり 因果の終わり』河出書房新社、2017年、p. 6。